いまいちピンとこなかった。
私は人がタブーと思うことは宗教ありきではなく、
コミュニティのタブーが宗教の教義に反映されると思うので、
西洋人が思う「人間が抑圧と感じること」についてが
あんまり理解できないんだよね。
狩猟民族の家長制度と農耕民族の母系社会じゃ
抑圧する人と内容も異なるじゃない?
まあその辺は置いといて。
理論で取り繕っても本能には逆らえないし、
ユダヤとアーリア人との確執が
とっても根深いのはわかった。
精神分析は、いまでは普遍的(という言葉は正しいのかな?)だけど
当時は「新しい科学」だったんだろうな。
新しい科学で未知の領域を切り開く
そんなエキサイティングな取組だったんだろうな。
キーラが名演だった。
彼女はこういう、精神の振り幅が大きい役が良く似合う。
メインは博士二人の接近&喧嘩別れで、
とてもスリリングだった。
ファスベンダーのユングは、
ある種の微妙な俗物感が絶妙。
学問的な野心があり、
禁忌だなんだを商売のネタにする癖に
患者と愛人関係になりながらも
裕福な妻とは別れない。
(そのうえ子供もたくさん作る)
科学の中にオカルティズム取り込もうとするのも
なんだかとっても納得できる風貌&雰囲気。
ヴィゴのフロイドは大家族の長で、
ユングが心酔するのもわかる父性がある。
それは同時に抑圧する者でもあり
自分の学説と違うことは認めない圧力も感じる。
その2人が出会い、蜜月期間があり
やがて別れる、ってあたりが主題かと思うと
別にそんなわけでもない。
結局なにが描きたかったのか良くわからない作品でした。
父なる存在から離脱する話じゃないよね?
せっかくヴィゴとファスベンダーが
コスプレして同じ画面にいるのに
それ以上の魅力がないのが残念。
キーラ演ずるザビーナの位置もよくわからなかった。
なにかの決定打になるほどじゃないし。
それにしても、やっぱり、フロイトの
人間の心理を全て性衝動で説明できるという発想は
わからんなーー。
ヴァンサンはやっぱりいつもの役だった。
こういう役以外も見たいけど、
実際見たら「コレじゃない」と思うんだろうなあ
美術はすごくステキ。
これだけでも見る価値はある。
私は人がタブーと思うことは宗教ありきではなく、
コミュニティのタブーが宗教の教義に反映されると思うので、
西洋人が思う「人間が抑圧と感じること」についてが
あんまり理解できないんだよね。
狩猟民族の家長制度と農耕民族の母系社会じゃ
抑圧する人と内容も異なるじゃない?
まあその辺は置いといて。
理論で取り繕っても本能には逆らえないし、
ユダヤとアーリア人との確執が
とっても根深いのはわかった。
精神分析は、いまでは普遍的(という言葉は正しいのかな?)だけど
当時は「新しい科学」だったんだろうな。
新しい科学で未知の領域を切り開く
そんなエキサイティングな取組だったんだろうな。
キーラが名演だった。
彼女はこういう、精神の振り幅が大きい役が良く似合う。
メインは博士二人の接近&喧嘩別れで、
とてもスリリングだった。
ファスベンダーのユングは、
ある種の微妙な俗物感が絶妙。
学問的な野心があり、
禁忌だなんだを商売のネタにする癖に
患者と愛人関係になりながらも
裕福な妻とは別れない。
(そのうえ子供もたくさん作る)
科学の中にオカルティズム取り込もうとするのも
なんだかとっても納得できる風貌&雰囲気。
ヴィゴのフロイドは大家族の長で、
ユングが心酔するのもわかる父性がある。
それは同時に抑圧する者でもあり
自分の学説と違うことは認めない圧力も感じる。
その2人が出会い、蜜月期間があり
やがて別れる、ってあたりが主題かと思うと
別にそんなわけでもない。
結局なにが描きたかったのか良くわからない作品でした。
父なる存在から離脱する話じゃないよね?
せっかくヴィゴとファスベンダーが
コスプレして同じ画面にいるのに
それ以上の魅力がないのが残念。
キーラ演ずるザビーナの位置もよくわからなかった。
なにかの決定打になるほどじゃないし。
それにしても、やっぱり、フロイトの
人間の心理を全て性衝動で説明できるという発想は
わからんなーー。
ヴァンサンはやっぱりいつもの役だった。
こういう役以外も見たいけど、
実際見たら「コレじゃない」と思うんだろうなあ
美術はすごくステキ。
これだけでも見る価値はある。
























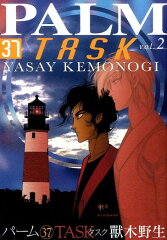

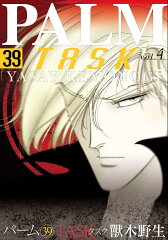
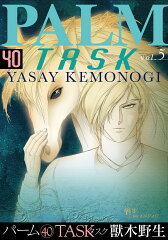
![Wings (ウィングス) 2013年 06月号 特別付録 永久保存版小冊子「プチ・パームブック」[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61in8ViynvL._SL160_.jpg)

