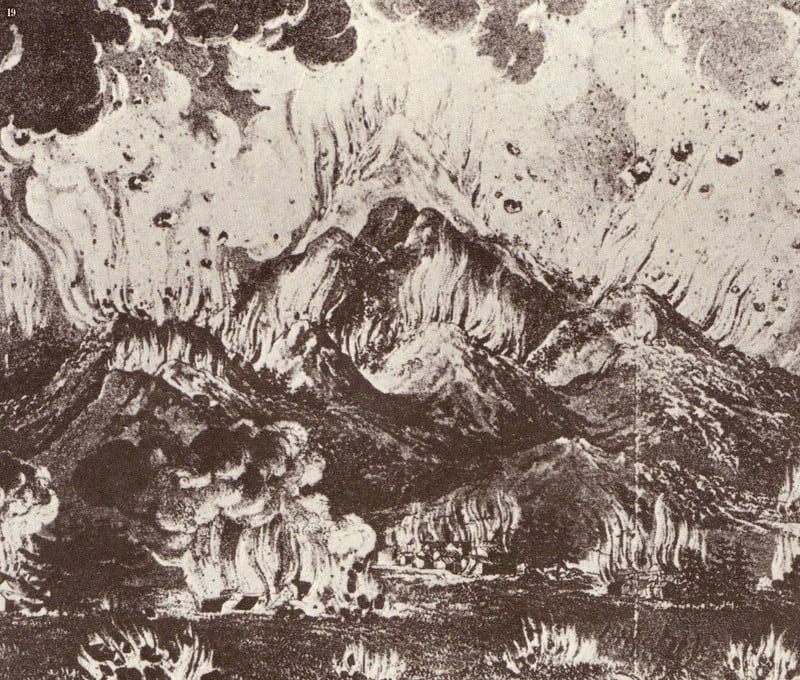今回の「志方町を歩く」は、以前に「西神吉町探訪・旧北条街道」を少し手直ししたものです。
円福寺の前の道は、志方町横山から続いた旧北条街道の一部です。
旧北条街道
 加古川市米田町平津の国道2号線の交差点からさらに、北へ道はのびています。
加古川市米田町平津の国道2号線の交差点からさらに、北へ道はのびています。
この道は、西神吉町あたりで大池・新池の東を通り、志方町投松(ねじまつ)へぬけます。そして加西市北条へと伸びる幹線(主要地方道・北条高砂線)です。
明治18年(1885)に完成しました。
それ以前の旧北条街道は、神吉村から西神吉町宮前の宮山の麓と大池の間を通っていました。
作家の猪瀬直樹氏は、三島由紀夫伝『ペルソナ』の取材のため、三島の先祖の出身地である横山を訪れておられます。
『ペルソナ』で、旧北条街道にも触れておられるので、少し引用が長くなりますが、読んでみます。
この時、猪瀬は横山へ志方側から入っておられます。
・・・・道幅は狭いけど、かつて北条街道とよばれ人馬が盛んだった。坂は赤坂と呼ばれている。
江戸時代から明治初頭、播州平野の奥から牛に引かせた車が米を積んで港へと向かった。その際、この赤坂を喘(あえ)ぎながら登ったところで一服した。
モータリゼーションの時代でもドライブインやスーパーマーケット、土産物店等が固まっているような場所が必ずある。
横山(志方町)は、江戸時代末期のそうしたスポットだった。『志方町誌』の記述に従えば、以下のようになる。
「昔の北条街道は、この山の東を通り神吉(西神吉町)の大池の西へ出たもので、この街道にできた集落が横山で、上富木(かみとみき)の小字である。・・・道の東側に北から塩物屋、くすり屋、焼もち屋、綿打屋、植木屋、いかけ屋と商売屋がならんでいたそうである」
三島由紀夫の祖父・平岡定太郎(さだたろう)が樺太庁長官となって故郷に錦を飾るというので、賑やかにみなで出迎えた。
宝殿には駅が設置されておらず、加古川駅から人力車の列がならび、さながら大名行列のようだった。
もう北条街道に新道(現在の北条・高砂線)ができていた。その道からやってきた。
・・・・
旧北条街道は、主役の座を降りて久しくなりました。
円福寺の前の道は、横山から続く旧北条街道です。そして、細工所へ・北条へとのびていました。
*写真:旧北条街道(円福寺前より少し西あたり)