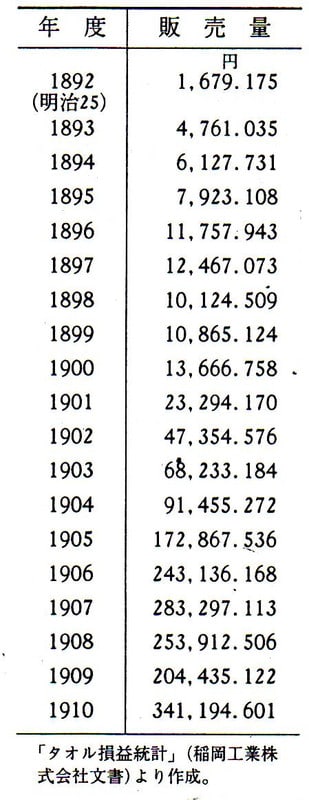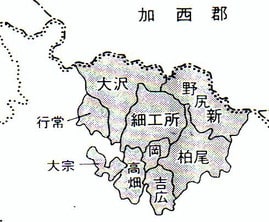「志方町を歩く」は、しばらく休憩
その後「志方町を歩く」を企画したのは、生まれが志方町であったことが大きな理由でした。
「志方町を歩く」は、それだけの理由でスタートさせました。
企画したというものの、思いついたことを秩序なく並べただけですが、前号で328号になりました。
この間、志方町をよく歩きました。
志方町について新しいことをいっぱい知ることができました。
志方町が好きになってきました。
「志方町を歩く」では、それらをみなさんに押し付けただけのような気がしています。
お付き合いくださいました読者の皆様にお礼申し上げます。
ここで、このシリーズはいったん急停車します。
しばらく「お休み」です。
次のシリーズ「新野辺を歩く」の後に、このシリーズ「志方町を歩く」を再開したいと考えています。
その間に志方町についての新たな史料をあつめます。
「志方町を歩く」では、多くの志方町の方にご協力をお願し、ご迷惑をおかけしました。
本当にありがとうございました。そして、お詫び申し上げます。
*写真:円照寺(広尾)のノウゼンカズラ
シリーズ「新野辺を歩く」スタート!
「志方町を歩く」をお休みにした理由は、以前にも「新野辺探訪」を少し書いたのですが、もう少し「新野辺(しのべ)」(加古川市別府町)の歴史を続けてみたかったからです。
というのは、いま、新野辺の方が町内会を中心にした、新たな動きがあります。
その内容は、追って紹介します。
もちろん、シリーズ「新野辺を歩く」は、直接、新野辺の方々の運動とは関係はありません。
私からの一方的なお節介です。
しばらくお付き合いください。
志方町でも稲美町でも、身近な歴史を知ることの大切さを改めて知ることができましたので・・・