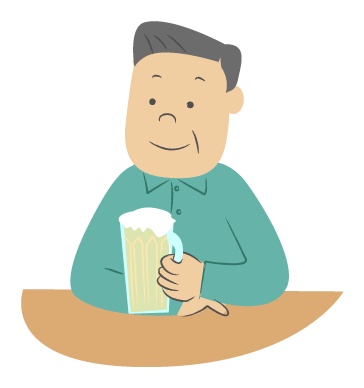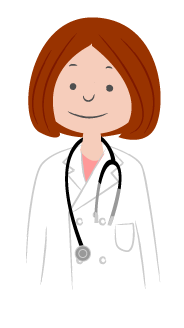一人親世代の貧困率先進国ワースト二位。
子供の貧困は、なぜここまで深刻化したのか、理由はいくつか考えられるが、なかでも大きな要素は母子家庭の増加だろう。
「全国母子世帯調査」によると、母子世帯数は03年で122万世帯。10年間で1.5倍に増えた。実に17人に1人が母子世帯の子供である。
いまや三組に一組の夫婦が離婚する時代なので他人事ではない。
NPO法人しんぐるまざず、ふぉーらむの赤石千衣子理事によると「日本の母子家庭は元祖ワーキングプア」だという。就労率は84.5%と高いが、平均就労収入は171万円で手当等を含めても平均年収213万円、国民全世帯の平均年収の40%にも満たない。
当然、貧困率も高くなる。阿部氏の推計によれば、両親と子供のみの世帯では11%、それが母子世帯では66%に跳ね上がる。日本の1人親世帯の貧困率は先進国の中でトルコに次いでワースト二位という酷さだ。
「特にバブル崩壊後、男女を問わず急激な非正規化が進み、シングルマザーはなかなか安定した職業に就けない」(赤石氏)。
週刊ダイヤモンド誌09/03/21より抜粋引用。
私はこの記事を拝見し、他人事ではないことを実感している。私の近所にも離婚からシングルマザーになり、小学生を抱えて、実家に戻ってきた人が二組も居られるのです。
まだ、実家に戻れるケースは良いとしても、アパートで親子二人暮らしや子供二人の場合は、金銭的にも大変である。
また、例え実家に戻ったとしても親が高齢な場合も大変である。
特に昨年頃からこの3月頃まで派遣社員、契約社員のリストラがされている。
これらから子供の貧困の格差は拡大しており、母子世帯に限らず、両親の居る家庭でも子供の貧困差は深刻な問題でもある。
私がこれら子供の貧困差で危惧しているのは、子供達の「心の問題」である。
中には、学校に同じ洋服を着ていたり、給食費を払えないのでいじめにあったり、不登校になったりする子供達が急増している現状である。
病気に疾患しても医療費が払えない、例えば母子家庭の高校生が怪我をして救急車を呼ぼうとしたら、私の家では医療費が払えないので乗りたくないと断ったのである。
また、これらの影響は学力の低下にも繋がる。進学を諦める子供達が増えているのである。高校進学や特に大学進学を諦める子供達が急増しているのです。
アルバイトをしながら1人親を助けている子供たち、アルバイトしながら学校に通うには大変である。
これらから子供の貧困差は身体的にも、精神的にも成長段階である子供達に悪影響を与えるのです。
他にも、海外から日本に出稼ぎに来ている人達はもっと子供の貧困差は深刻化している。
昨年頃から製造業、工場関係では派遣社員、契約社員などリストラされ、工場の寮から追い出され、生活費もままならないところに、子供の学費など金銭的な悩みを多く抱えている。
母国に戻るにも交通費が無い。子供が日本での生活が長いなどの諸問題もあり、日本で働く外国人は日本での再勤務を希望している。中には、一ヶ月の月給を減らしてでも働きたいと申し出、採用され、景気の復活を祈りながら働いている。
日本で働く、外国人の子供の多くは小学校(インターナショナルスクール)に通っていないのである。
つまり、授業料が払えないのである。
日本国内では両親と子供のみの世帯での貧困率は11%だが、これは今年のデータではない。今年は20%近くまで貧困率が上がっていると予想されるのです。
これらに対して日本政府が政策を打ち出しておらず、取り組みも具体的に進んでいない。
このままでは私は間違いなく「日本人の学力が低下する」。と提言している。
社会の活力を削ぐ子供の貧困差!
これらの貧困差は「教育格差」を生み出し、貧困世帯に育った子供とそうでない子供に比べたら、スタートラインから不利である。身体的にも心理的な影響など考えられる。
そこで私は、日本政府にこれらの現状を訴え、また金融関係者、地銀協会、メガバンクなど生活支援、教育支援対策として、学校関係では母子家庭や年収200万円以下の子供達には入学金の無料化、教育ローンの税率削減などの取り組みをして欲しいと願っている。
これらの問題に産学官民一体となって取り組まないと、日本の未来も危ないと私は提言いたします。
貧困格差が益々広がろうとしている現在、子供達の貧困は子供達には責任はない。成長段階の子供達において、身体的にも精神的にも影響を及ぼす。週刊ダイヤモンドでは「7人に1人が苦しむ(日本病)」と題して紹介しているが、このまま日本政府がこれら貧困格差に真剣になって取り組まないと、この日本病は蔓延するだろう。
五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、
子供の貧困は、なぜここまで深刻化したのか、理由はいくつか考えられるが、なかでも大きな要素は母子家庭の増加だろう。
「全国母子世帯調査」によると、母子世帯数は03年で122万世帯。10年間で1.5倍に増えた。実に17人に1人が母子世帯の子供である。
いまや三組に一組の夫婦が離婚する時代なので他人事ではない。
NPO法人しんぐるまざず、ふぉーらむの赤石千衣子理事によると「日本の母子家庭は元祖ワーキングプア」だという。就労率は84.5%と高いが、平均就労収入は171万円で手当等を含めても平均年収213万円、国民全世帯の平均年収の40%にも満たない。
当然、貧困率も高くなる。阿部氏の推計によれば、両親と子供のみの世帯では11%、それが母子世帯では66%に跳ね上がる。日本の1人親世帯の貧困率は先進国の中でトルコに次いでワースト二位という酷さだ。
「特にバブル崩壊後、男女を問わず急激な非正規化が進み、シングルマザーはなかなか安定した職業に就けない」(赤石氏)。
週刊ダイヤモンド誌09/03/21より抜粋引用。
私はこの記事を拝見し、他人事ではないことを実感している。私の近所にも離婚からシングルマザーになり、小学生を抱えて、実家に戻ってきた人が二組も居られるのです。
まだ、実家に戻れるケースは良いとしても、アパートで親子二人暮らしや子供二人の場合は、金銭的にも大変である。
また、例え実家に戻ったとしても親が高齢な場合も大変である。
特に昨年頃からこの3月頃まで派遣社員、契約社員のリストラがされている。
これらから子供の貧困の格差は拡大しており、母子世帯に限らず、両親の居る家庭でも子供の貧困差は深刻な問題でもある。
私がこれら子供の貧困差で危惧しているのは、子供達の「心の問題」である。
中には、学校に同じ洋服を着ていたり、給食費を払えないのでいじめにあったり、不登校になったりする子供達が急増している現状である。
病気に疾患しても医療費が払えない、例えば母子家庭の高校生が怪我をして救急車を呼ぼうとしたら、私の家では医療費が払えないので乗りたくないと断ったのである。
また、これらの影響は学力の低下にも繋がる。進学を諦める子供達が増えているのである。高校進学や特に大学進学を諦める子供達が急増しているのです。
アルバイトをしながら1人親を助けている子供たち、アルバイトしながら学校に通うには大変である。
これらから子供の貧困差は身体的にも、精神的にも成長段階である子供達に悪影響を与えるのです。
他にも、海外から日本に出稼ぎに来ている人達はもっと子供の貧困差は深刻化している。
昨年頃から製造業、工場関係では派遣社員、契約社員などリストラされ、工場の寮から追い出され、生活費もままならないところに、子供の学費など金銭的な悩みを多く抱えている。
母国に戻るにも交通費が無い。子供が日本での生活が長いなどの諸問題もあり、日本で働く外国人は日本での再勤務を希望している。中には、一ヶ月の月給を減らしてでも働きたいと申し出、採用され、景気の復活を祈りながら働いている。
日本で働く、外国人の子供の多くは小学校(インターナショナルスクール)に通っていないのである。
つまり、授業料が払えないのである。
日本国内では両親と子供のみの世帯での貧困率は11%だが、これは今年のデータではない。今年は20%近くまで貧困率が上がっていると予想されるのです。
これらに対して日本政府が政策を打ち出しておらず、取り組みも具体的に進んでいない。
このままでは私は間違いなく「日本人の学力が低下する」。と提言している。
社会の活力を削ぐ子供の貧困差!
これらの貧困差は「教育格差」を生み出し、貧困世帯に育った子供とそうでない子供に比べたら、スタートラインから不利である。身体的にも心理的な影響など考えられる。
そこで私は、日本政府にこれらの現状を訴え、また金融関係者、地銀協会、メガバンクなど生活支援、教育支援対策として、学校関係では母子家庭や年収200万円以下の子供達には入学金の無料化、教育ローンの税率削減などの取り組みをして欲しいと願っている。
これらの問題に産学官民一体となって取り組まないと、日本の未来も危ないと私は提言いたします。
貧困格差が益々広がろうとしている現在、子供達の貧困は子供達には責任はない。成長段階の子供達において、身体的にも精神的にも影響を及ぼす。週刊ダイヤモンドでは「7人に1人が苦しむ(日本病)」と題して紹介しているが、このまま日本政府がこれら貧困格差に真剣になって取り組まないと、この日本病は蔓延するだろう。
五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、