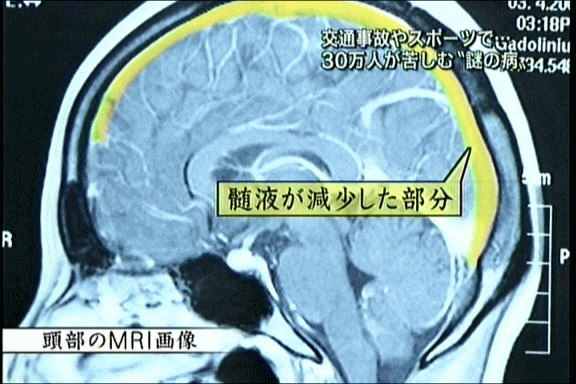脳脊髄液が増えて脳の中心にある脳室が拡大し歩行障害、尿失禁、痴呆症状を呈し、たまった脳脊髄液を手術で腹腔に導くことにより劇的に症状が改善する正常圧 水頭症という病気は比較的知られています。反対に脳脊髄液が減少することにより様々な症状を呈する脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)は殆ど知られていませ ん。この病気が初めて報告されたのは1938年のことですが長いあいだ注目されずにいました。いまから15年くらい前に脳MRIで診断できるようになって から症例の報告が多くなりました。しかしながらきわめて稀な病気と認識されています。現在知られているのは特発性低髄液圧症候群といって明らかな原因なし に立っているか座っていると激しい頭痛がして横になると改善し、腰椎穿刺で髄液圧を測定すると正常より低く、造影脳MRIを行うと脳を包んでいる硬膜が肥 厚していることが特徴です。これまでの報告は比較的急性期(発症して1ヶ月以内)が多いのですが慢性期の脳髄液減少症ははるかに多く、上に述べた3つの特 徴がそろわないことが多いので見逃されている患者さんの数は膨大です。交通事故の後遺症ことに鞭打ち後遺症で苦しんでいる患者さんは数十万人に上ると推定 されますが脳脊髄液減少症が多くふくまれていることがわかってきました。約7割の患者さんは適切な治療で症状が改善し仕事や日常生活が何とかできるように 回復しています。また慢性疲労症候群や線維筋痛症といった難治性の病気と関連があることもわかってきました。しかしこの疾患はまだ解明されていない部分が 多く今後の研究により病態解明や治療法が進歩すると思われます。以下これまでにわかっていることを述べます。
■どのような症状を呈するか脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩です。いわゆる不定愁訴がそれに相当します。いくつかの症状群に分けてみると、第一に痛みです。初期には起立性頭痛が特 徴的です。起きていると頭痛が強く横になると治まる。ただし慢性期になると横になっても頭痛が治まらないことがしばしばです。頭痛の性質はさまざまで片頭 痛タイプであったり緊張型頭痛であったり三叉神経痛様であったりします。多くは鎮痛剤の効果が乏しいようです。頭痛以外にも頚部痛、背部痛、腰痛、手足の 痛みなどまさに痛みのデパートです。多くの患者さんは頚部、肩、背部の筋肉が石のように硬くなっています。
第二に脳神経症状です。もっとも症状が出やすいのは聴覚に関連した症状です。耳鳴り、聴覚過敏、めまい、ふらつきなどでメニエール病や特発性難聴と診断 された患者さんも多くみられます。つぎに目に関連した症状です。ピントが合わない、光がまぶしい、視野に黒い点や光が飛ぶ、視力が急に低下した、物が2重に見えるなどの症状です。そのほか三叉神経が障害されると顔面痛、しびれ、歯痛、顎関節症になることがあります。顔面神経が障害されると能面のように無表 情になる、顔面痙攣、唾液や涙が出にくいなどの症状がでます。そのほか嚥下障害、声が出にくい、味覚・嗅覚異常もみられます。
第三に自律神経症状です。自律神経のひとつである迷走神経は脳神経の一部ですがあえてここで述べます。微熱、体温調整障害、動悸、呼吸困難、胃腸障害、頻尿などの症状がでます。特に胃腸症状は迷走神経の機能異常が原因で胃食道逆流症、頑固な便秘が多くみられこれらの症状は治療阻害因子でもあり治療はしば しば難渋します。いわゆる更年期障害に症状が一致するのでそのように診断されることがしばしばです。
第四に高次脳機能障害があります。脳挫傷の後遺症としての高次脳機能障害ほど症状は強くないのですが、仕事や家庭生活を営むうえで大変不自由します。記憶障害の特徴はなにげなく話をした内容をわすれてしまうとか読んだ本の内容を覚えられないので読書ができないとか、忘れ物が多くなるなどです。ひどくなる とメモを取るまもなく数秒前のことを忘れてしまうこともあります。このほかに思考力、集中力が極度に低下してスムーズに仕事ができなくなることがありま す。いつも頭がボーとしてもももやがかかっているようだと訴えます、うつや無気力もよく見られる症状です。精神科や心療内科で治療を受けている患者さんがたくさんおられます。髄液が減少すると脳の機能とくに海馬や脳梁の機能が落ちるのだろうと推測しています。
第五に極度の倦怠感、易疲労感、睡眠障害、免疫異常により風邪をひきやすくなる、アトピーの悪化、内分泌機能異常として性欲低下、月経異常、子宮内膜症の悪化などの症状がでます。脳脊髄液減少症はひとつの症状のみを訴える患者さんは少なく、いくつかの症状が組み合わされるのが大部分です。見た目にはどこも悪くなさそうなので気のせいとかなまけ病とか言われることが多いのですが一旦この病気にかかると深刻です。まわりの人に理解してもらえない苦しみは病気の苦しみを倍増させます。
これらの症状にはある特徴がみられます。一つは天候に左右されることです。ことに気圧の変化に応じて症状が変化します。雨の降る前や台風の接近により頭痛、めまい、吐き気、だるさなどが悪化する傾向があります。体をおこしていると症状が悪化し横になると軽快する傾向もみられます。二つ目は脱水で症状が悪化することです。十分な水分が摂れないときや下痢、発熱時のような脱水状態で症状が悪化することが多く見られます。
■どうして脳脊髄液が減少するのか脳脊髄液が減少するメカニズムは3つ考えられます。ひとつは髄液の産生低下です。熱が高くなり十分に水分を補給しないと脱水状態になり脱水になると髄液産生 が低下します。極端に水分を取らない患者さんで典型的な髄液減少症状を呈し、脳MRIでも髄液減少所見がみられ、1日1500mlの水分をとるようにした ら3ヶ月ですっかり症状がよくなった方がおられました。つぎに過剰な髄液吸収です。実際にこのようなことが起こっているのかはっきり確かめたことはありま せん。多くは髄液の漏出です。RI脳槽シンチで髄液の漏れを見ることができます。治療により漏れがとまることから脊髄レベルで髄液が漏れることは確かで す。転倒して頭部を打撲しその後脳のクモ膜に裂け目ができて髄液が硬膜下に貯留することはよくみられます。脊髄レベルでも鞭打ち症のように比較的軽微は外 傷でクモ膜に裂け目ができることは容易に想像できます。
鞭打ちの場合は一時的に髄液圧が急上昇し圧が津波のように下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられます。解剖学的 神経根の部分でクモ膜と硬膜の間が疎な場合は神経根の硬膜末端から髄液が漏れるのではないかと考えています。この点に関しては今後の研究の成果を待ちたい と思いますがいずれにせよ髄液が硬膜外に漏れるのはまちがいないようです。漏れを引き起こす原因としては交通外傷、スポーツ外傷、転倒転落、出産などがあげられます。
インターネット「脳髄液減少症」より抜粋引用、
脳髄液減少症患者は全国で30万人以上が症状に悩まされている。めまい、吐き気、特にひどい頭痛など多くの症状に悩まされている。
脳髄液減少症の主な原因は、全体の70%以上が交通事故による鞭打ち症による脳髄液減少である。
人の脳は脳髄液に満たされて少し浮いている状態である。これが少しでも減少したり、漏れ出したら、めまい、頭痛と時には、視覚も見えにくくなる。
現在では、医療機関の認識も低く、治療も確立されていない。雄一「ブラットパッド」治療という、脊髄液や脳髄液の漏れ出している場所に血液を注入し、血液の凝固作用によって漏れを食い止める方法である。
これも決して患者さんすべてに効果がある訳ではない。3割程度の患者さんには効果がないことがわかっている。
また、保険対象外治療なので、一回の治療に30万円前後の治療費が患者さんたちは負担をしなければならない。これを何度か定期的に行うことは治療費の工面も大変な負担になる。
そこで、厚生省などに保険対象治療としての認可を求めているが、当の厚生省は、日本医師会の見解を求めている。医師会では、医師各自の治療認識の違いや、治療する側の病院の数不足など、また、ガイドラインが作成されていないので、当分の間時間もかかり、ガイドラインが決まれば、そこで「病気の認知」が可能となる。
現在、30万人にも人にも及ぶ、患者さん達が悩まされている「難病」にも関わらず、厚生省や日本医師会はのんびりしている。
また、病院スタッフの病気に対する認識不足もあり、多くの患者が交通事故の後遺症や鞭打ち症と簡単に診断されてしまう。
ところが、脳髄液減少症と診断されると今度は治療ができないと医師から告げられ、何件も病院をたらい回しされることになるのである。
今のままの推移で行くと、5年後には、35万人、10年後には40万人を超え、そして15年後には50万人にも及ぶ「脳髄液減少症」の患者が増加し、症状に悩まされることになるだろう!
私共はこれらを鑑み、来年以降に北関東で構想している、医療施設でこの脳髄液減少症の新たな治療法や保険対応治療など多くの患者さんが苦しんでいる現状を見逃すわけには参りません。
私でできることなら、全力で取り組み、もしかしたら明日には貴方達が交通事故に遭遇してこの脳髄液減少症に疾患するかも知れないのです。
一日も早い医療関係での認知と法的な面での改善を強く望むものです。
五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、
■どのような症状を呈するか脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩です。いわゆる不定愁訴がそれに相当します。いくつかの症状群に分けてみると、第一に痛みです。初期には起立性頭痛が特 徴的です。起きていると頭痛が強く横になると治まる。ただし慢性期になると横になっても頭痛が治まらないことがしばしばです。頭痛の性質はさまざまで片頭 痛タイプであったり緊張型頭痛であったり三叉神経痛様であったりします。多くは鎮痛剤の効果が乏しいようです。頭痛以外にも頚部痛、背部痛、腰痛、手足の 痛みなどまさに痛みのデパートです。多くの患者さんは頚部、肩、背部の筋肉が石のように硬くなっています。
第二に脳神経症状です。もっとも症状が出やすいのは聴覚に関連した症状です。耳鳴り、聴覚過敏、めまい、ふらつきなどでメニエール病や特発性難聴と診断 された患者さんも多くみられます。つぎに目に関連した症状です。ピントが合わない、光がまぶしい、視野に黒い点や光が飛ぶ、視力が急に低下した、物が2重に見えるなどの症状です。そのほか三叉神経が障害されると顔面痛、しびれ、歯痛、顎関節症になることがあります。顔面神経が障害されると能面のように無表 情になる、顔面痙攣、唾液や涙が出にくいなどの症状がでます。そのほか嚥下障害、声が出にくい、味覚・嗅覚異常もみられます。
第三に自律神経症状です。自律神経のひとつである迷走神経は脳神経の一部ですがあえてここで述べます。微熱、体温調整障害、動悸、呼吸困難、胃腸障害、頻尿などの症状がでます。特に胃腸症状は迷走神経の機能異常が原因で胃食道逆流症、頑固な便秘が多くみられこれらの症状は治療阻害因子でもあり治療はしば しば難渋します。いわゆる更年期障害に症状が一致するのでそのように診断されることがしばしばです。
第四に高次脳機能障害があります。脳挫傷の後遺症としての高次脳機能障害ほど症状は強くないのですが、仕事や家庭生活を営むうえで大変不自由します。記憶障害の特徴はなにげなく話をした内容をわすれてしまうとか読んだ本の内容を覚えられないので読書ができないとか、忘れ物が多くなるなどです。ひどくなる とメモを取るまもなく数秒前のことを忘れてしまうこともあります。このほかに思考力、集中力が極度に低下してスムーズに仕事ができなくなることがありま す。いつも頭がボーとしてもももやがかかっているようだと訴えます、うつや無気力もよく見られる症状です。精神科や心療内科で治療を受けている患者さんがたくさんおられます。髄液が減少すると脳の機能とくに海馬や脳梁の機能が落ちるのだろうと推測しています。
第五に極度の倦怠感、易疲労感、睡眠障害、免疫異常により風邪をひきやすくなる、アトピーの悪化、内分泌機能異常として性欲低下、月経異常、子宮内膜症の悪化などの症状がでます。脳脊髄液減少症はひとつの症状のみを訴える患者さんは少なく、いくつかの症状が組み合わされるのが大部分です。見た目にはどこも悪くなさそうなので気のせいとかなまけ病とか言われることが多いのですが一旦この病気にかかると深刻です。まわりの人に理解してもらえない苦しみは病気の苦しみを倍増させます。
これらの症状にはある特徴がみられます。一つは天候に左右されることです。ことに気圧の変化に応じて症状が変化します。雨の降る前や台風の接近により頭痛、めまい、吐き気、だるさなどが悪化する傾向があります。体をおこしていると症状が悪化し横になると軽快する傾向もみられます。二つ目は脱水で症状が悪化することです。十分な水分が摂れないときや下痢、発熱時のような脱水状態で症状が悪化することが多く見られます。
■どうして脳脊髄液が減少するのか脳脊髄液が減少するメカニズムは3つ考えられます。ひとつは髄液の産生低下です。熱が高くなり十分に水分を補給しないと脱水状態になり脱水になると髄液産生 が低下します。極端に水分を取らない患者さんで典型的な髄液減少症状を呈し、脳MRIでも髄液減少所見がみられ、1日1500mlの水分をとるようにした ら3ヶ月ですっかり症状がよくなった方がおられました。つぎに過剰な髄液吸収です。実際にこのようなことが起こっているのかはっきり確かめたことはありま せん。多くは髄液の漏出です。RI脳槽シンチで髄液の漏れを見ることができます。治療により漏れがとまることから脊髄レベルで髄液が漏れることは確かで す。転倒して頭部を打撲しその後脳のクモ膜に裂け目ができて髄液が硬膜下に貯留することはよくみられます。脊髄レベルでも鞭打ち症のように比較的軽微は外 傷でクモ膜に裂け目ができることは容易に想像できます。
鞭打ちの場合は一時的に髄液圧が急上昇し圧が津波のように下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられます。解剖学的 神経根の部分でクモ膜と硬膜の間が疎な場合は神経根の硬膜末端から髄液が漏れるのではないかと考えています。この点に関しては今後の研究の成果を待ちたい と思いますがいずれにせよ髄液が硬膜外に漏れるのはまちがいないようです。漏れを引き起こす原因としては交通外傷、スポーツ外傷、転倒転落、出産などがあげられます。
インターネット「脳髄液減少症」より抜粋引用、
脳髄液減少症患者は全国で30万人以上が症状に悩まされている。めまい、吐き気、特にひどい頭痛など多くの症状に悩まされている。
脳髄液減少症の主な原因は、全体の70%以上が交通事故による鞭打ち症による脳髄液減少である。
人の脳は脳髄液に満たされて少し浮いている状態である。これが少しでも減少したり、漏れ出したら、めまい、頭痛と時には、視覚も見えにくくなる。
現在では、医療機関の認識も低く、治療も確立されていない。雄一「ブラットパッド」治療という、脊髄液や脳髄液の漏れ出している場所に血液を注入し、血液の凝固作用によって漏れを食い止める方法である。
これも決して患者さんすべてに効果がある訳ではない。3割程度の患者さんには効果がないことがわかっている。
また、保険対象外治療なので、一回の治療に30万円前後の治療費が患者さんたちは負担をしなければならない。これを何度か定期的に行うことは治療費の工面も大変な負担になる。
そこで、厚生省などに保険対象治療としての認可を求めているが、当の厚生省は、日本医師会の見解を求めている。医師会では、医師各自の治療認識の違いや、治療する側の病院の数不足など、また、ガイドラインが作成されていないので、当分の間時間もかかり、ガイドラインが決まれば、そこで「病気の認知」が可能となる。
現在、30万人にも人にも及ぶ、患者さん達が悩まされている「難病」にも関わらず、厚生省や日本医師会はのんびりしている。
また、病院スタッフの病気に対する認識不足もあり、多くの患者が交通事故の後遺症や鞭打ち症と簡単に診断されてしまう。
ところが、脳髄液減少症と診断されると今度は治療ができないと医師から告げられ、何件も病院をたらい回しされることになるのである。
今のままの推移で行くと、5年後には、35万人、10年後には40万人を超え、そして15年後には50万人にも及ぶ「脳髄液減少症」の患者が増加し、症状に悩まされることになるだろう!
私共はこれらを鑑み、来年以降に北関東で構想している、医療施設でこの脳髄液減少症の新たな治療法や保険対応治療など多くの患者さんが苦しんでいる現状を見逃すわけには参りません。
私でできることなら、全力で取り組み、もしかしたら明日には貴方達が交通事故に遭遇してこの脳髄液減少症に疾患するかも知れないのです。
一日も早い医療関係での認知と法的な面での改善を強く望むものです。
五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、