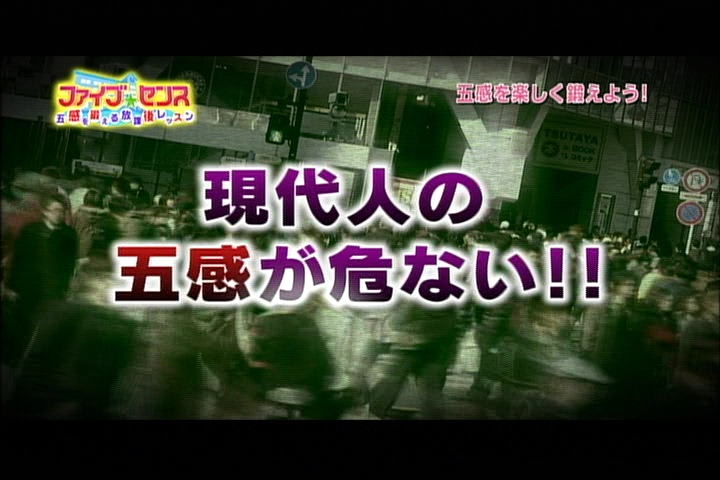11/25(水)ケンウッドスクエア丸の内において、101歳のウクレレマイスター「ビル・タピア(BillTapia)」氏のビデオコンサートが行われ、私も気になり以前から予約をしていたので拝見した。
簡単にビル・タピア氏のプロフィールを紹介しよう!
1908年1月1日、ハワイ・ホノルルにて、ポルトガル系の両親のもとに生まれる。ウクレレの創始者のひとり、マニュエル・ヌネスの工房の近所に住んでいたビルにとってウクレレはとても身近な楽器であった。
7歳のとは、75セントで最初のウクレレを手に入れたビルは、10歳でプロミュジシャンとなり、1927年には、ワイキキの象徴ロイヤルハワイアンホテルのオープニングセレモニーでバンドの一員として演奏した。22歳でメインランドに渡り、その1930年代当時「ジャズ」「ハワイアンスイウイング」など主流だった。ハリウッドのミュージックで、ジャズギタリストとして活躍、様々なバンドを世渡り歩いた。著名なジャズミュジシャンとセッションをしたのである。
このようにビル・タピア氏は、ウクレレを習っている人たちには神様的な存在なのである。
私が彼の演奏を知ったのは、27年前の新婚旅行の宿泊していたハワイのホテルでのディナーコンサートで初めて彼のハワイアンウクレレを聞いたのである。私はそのときのことをはっきり覚えている。当時から高齢者だった。当時74歳のお爺ちゃんがリズムカルなウクレレを演奏していたことに感銘を受けたのである。そして現在はなんと101歳になった現在も元気で演奏を続けていることに驚きと感動すら覚える。
何より、私が感心するのは、手の器用さと耳(聴覚)が素晴らしいのである。普通なら、80歳を過ぎた頃から補聴器がなければ耳が遠くて聞こえない感覚になるのだが、ビルは補聴器も付けて無く、左耳は聞こえづらいようで、右側に首を傾げながら音を聞いている。
歌声もはっきりしているし、リズム感も若き頃のままである。
普通に見たままなら70歳代のお爺ちゃんだと思ってしまうほど若いのである。彼がなぜ、元気に若々しく居られるのかは、音楽の力としか言いようがない。
現に、今年の7月24日~8月9日まで、東京、横浜、名古屋、大阪など10ヵ所ほどを回ってコンサートをしたのである。
また、彼は元気なだけでなく好奇心、気力がある。お金が好きで、若い女性も好きで、日本でも若い女性とツーショットの写真が多いのである。
白髪頭にサングラスが似合い、格好良いお爺ちゃんなのである。私の憧れの老人である。私も100歳まで元気に少しスケベに、女性を好み、元気に人の五感研究を100歳まで続けることを彼から学んだのである。
私の目標の人であり、好きなことを死ぬまでやって行けることは本当に幸せだと思う。このような人生を私も送りたいものだと、彼の演奏を聴いていると感動するだけでなく、人生そのものを学び、体験出来る数少ないプロミュジシャンである。
世界最高齢のプロミュジシャンは、人生そのものが格好良く素敵な男性なのである。私も格好良く素敵な老人になりたいと願っている。
来年は、まだビル・タピア氏の日本でのコンサートは予定されていないが、来年の2月にはハワイで予定されている。
この11月には、今年の夏の日本でのコンサートの模様を一部映像と演奏の模様が収録されたCDも販売されているので、関心のあるひとは購入して聞いて欲しい。きっと貴方も彼のファンになると思う。彼には不思議な魅力とパワーが感じられる世界でも数少ないプロミュジシャンてもあることは間違いのない史実である。
簡単にビル・タピア氏のプロフィールを紹介しよう!
1908年1月1日、ハワイ・ホノルルにて、ポルトガル系の両親のもとに生まれる。ウクレレの創始者のひとり、マニュエル・ヌネスの工房の近所に住んでいたビルにとってウクレレはとても身近な楽器であった。
7歳のとは、75セントで最初のウクレレを手に入れたビルは、10歳でプロミュジシャンとなり、1927年には、ワイキキの象徴ロイヤルハワイアンホテルのオープニングセレモニーでバンドの一員として演奏した。22歳でメインランドに渡り、その1930年代当時「ジャズ」「ハワイアンスイウイング」など主流だった。ハリウッドのミュージックで、ジャズギタリストとして活躍、様々なバンドを世渡り歩いた。著名なジャズミュジシャンとセッションをしたのである。
このようにビル・タピア氏は、ウクレレを習っている人たちには神様的な存在なのである。
私が彼の演奏を知ったのは、27年前の新婚旅行の宿泊していたハワイのホテルでのディナーコンサートで初めて彼のハワイアンウクレレを聞いたのである。私はそのときのことをはっきり覚えている。当時から高齢者だった。当時74歳のお爺ちゃんがリズムカルなウクレレを演奏していたことに感銘を受けたのである。そして現在はなんと101歳になった現在も元気で演奏を続けていることに驚きと感動すら覚える。
何より、私が感心するのは、手の器用さと耳(聴覚)が素晴らしいのである。普通なら、80歳を過ぎた頃から補聴器がなければ耳が遠くて聞こえない感覚になるのだが、ビルは補聴器も付けて無く、左耳は聞こえづらいようで、右側に首を傾げながら音を聞いている。
歌声もはっきりしているし、リズム感も若き頃のままである。
普通に見たままなら70歳代のお爺ちゃんだと思ってしまうほど若いのである。彼がなぜ、元気に若々しく居られるのかは、音楽の力としか言いようがない。
現に、今年の7月24日~8月9日まで、東京、横浜、名古屋、大阪など10ヵ所ほどを回ってコンサートをしたのである。
また、彼は元気なだけでなく好奇心、気力がある。お金が好きで、若い女性も好きで、日本でも若い女性とツーショットの写真が多いのである。
白髪頭にサングラスが似合い、格好良いお爺ちゃんなのである。私の憧れの老人である。私も100歳まで元気に少しスケベに、女性を好み、元気に人の五感研究を100歳まで続けることを彼から学んだのである。
私の目標の人であり、好きなことを死ぬまでやって行けることは本当に幸せだと思う。このような人生を私も送りたいものだと、彼の演奏を聴いていると感動するだけでなく、人生そのものを学び、体験出来る数少ないプロミュジシャンである。
世界最高齢のプロミュジシャンは、人生そのものが格好良く素敵な男性なのである。私も格好良く素敵な老人になりたいと願っている。
来年は、まだビル・タピア氏の日本でのコンサートは予定されていないが、来年の2月にはハワイで予定されている。
この11月には、今年の夏の日本でのコンサートの模様を一部映像と演奏の模様が収録されたCDも販売されているので、関心のあるひとは購入して聞いて欲しい。きっと貴方も彼のファンになると思う。彼には不思議な魅力とパワーが感じられる世界でも数少ないプロミュジシャンてもあることは間違いのない史実である。