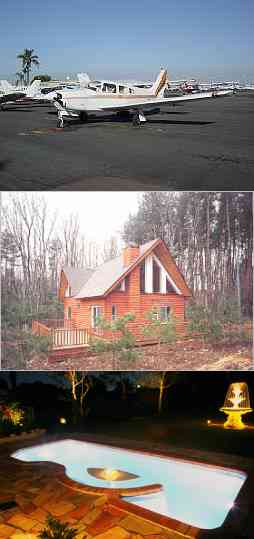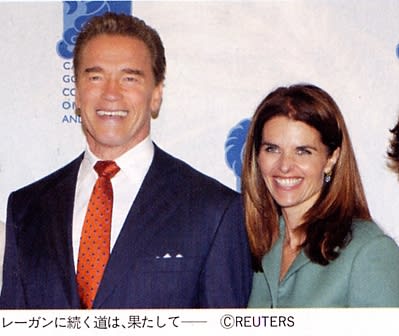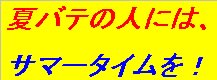 先週後半、品川でサマータイムの講演会があった。講演するのは東大名誉教授で生活構造改革フォーラムの茅陽一氏(肩書き多数)。講演は1時間15分。その後が質疑の予定だ。後援は日本経団連。
先週後半、品川でサマータイムの講演会があった。講演するのは東大名誉教授で生活構造改革フォーラムの茅陽一氏(肩書き多数)。講演は1時間15分。その後が質疑の予定だ。後援は日本経団連。講演は、「京都議定書」の周辺状況から始まる。政府の目標をブレークダウンしていくと、家庭部門が大きな問題であることが主張される。まあ、1990年には存在しなかった大型テレビやパソコンやら乾燥&洗濯機など次々に新製品は登場する。そして、このあたりが後半の枕になっているのだが、後で考えれば不要な時間だった。誰も省エネに反対しているわけではないからだ。
そして、肝心のサマータイム問題では、推進派の茅先生の主旨は、
1.サマータイム導入すると、ライフスタイルが変わらない限り、省エネ(石油93万Kl分)になる。
2.明るいうちに、帰宅でき、余暇が利用できる。
3.欧米はすでに導入している。
4.治安の向上
5.労働条件は劣悪にならない(はずだ)
6.昭和23年から数年実施されたサマータイム制の廃止は、単に占領軍政策への反発。
7.老人は早起きなので、起きてすぐに活動できる。(老齢化対策か?)
8.滋賀県庁で試験的に導入したら、好評だった。
ということ。
そして、この件は経団連でアンケートを行っていて賛成が64%で反対が29%と言われている。(後述)
アンケートでの賛成理由は、1の省エネと2の余暇利用が非常に多い。
そして、茅先生の講演が終わり、質疑になると、驚いたことに、次々に質問する普通の人たちの意見はほとんどサマータイム反対論。こういう質疑があった。
Q:家の中の多くの時計を合わせなければならないが、大変だ。
A:全部合わせなくても、2・3個だけでいいのではないか。そんなに多くの時計は見てないでしょ。
Q:中緯度国ではほとんどやっていないのでは?
A:ハワイでもやっている。確かに高緯度国の方が効果はあるが・・
Q:切り替え日に外国にいたが、交通事故が多くなる(あわててクルマが飛ばすから)。
A:聞いたことが無い。
Q:首都圏では、限界的通勤をしている人が多く、1時間早くなるのは朝が苦しい。
A:もっとのんびりとした生活が必要。
Q:昭和23年からのサマータイム時には大変あわただしい生活だった。
A:そんなはずはない。
Q:フレックスタイムと整合しないのではないか。
A:フレックスタイムはやめないと・・・
Q:滋賀県庁でうまくできたからと言っても、首都圏の普通の生活とは違うではないか。
A:都会の生活は忙しすぎるのが問題で、そういう問題を考え直す機会になる。
というような話が続いたあげく、先生は切れてしまい、
「反対意見しか出ないのだが、みなさんは省エネに反対なのか?」と怒り出すと、まばらな拍手。
質問者も切れてしまい、
Q:もっと省エネに重要なことを先にやって、こんなケチな話は後にしたら。と笑いを取る。
まあその辺で時間切れとなり、先生は赤い顔になり帰ってしまったのだが、感情的になってもしかたがないので、聞いた話のいくつかを考えてみる。
まず、実際どういう時間になるかというと、7月末の東京で考えると、現状では、日の出は04:50である(確かに、老人が起きる時間だ)。そして日の入りは18:47だ。17:30に会社を出ると、帰宅した時間くらいだ。
それが、サマータイムとなると、1時間前倒しになるため、05:50に日の出となり、日の入りは19:47となる。同じく17:30に退社した場合、18:30頃に帰宅できれば、1時間は照明をつけなくてもいいという考え方だ。逆にエアコン使用電力は増えるらしい。ただし通勤時間が2時間の人は、依然として、帰宅したら夜になっている。
一方、もともと変なのは、「余暇時間が利用できる」と「条件が変わらなければ省エネ」というのは矛盾していることだ。帰ってから、パチンコに行ったり、外食したり、ゴルフを半ラウンド余計に回ったりという新しい1時間は、どこから調達するかといえば、朝の(夜の)1時間をカットしたからに他ならないわけだ。と考えれば、サマータイムはせわしないという話とは合致する。また、通勤時間が1時間でかつ17時半に退社できる人でも、家に帰ると、薄暗く、暑い夕方が待っていると言うことになる。遊びに行きたくなるのは間違いない。結局、経済活動は、より活発になることから、エネルギーは消費方向に向うだろう。さらにそこにはサービス側の労働力が必要になるが、しょせんは夏季限定需要なので、社員増は行わず、残業時間増になるのではないだろうか。
外国がやっているから、というのはまったく気にすることはないだろう。もともと、欧米とは時差が離れ過ぎていて不便なのだから、彼らが1時間早まるということは、日本側の負担を軽減しているわけだ。日本も1時間前倒しする動機としては弱い。
そして、茅先生は24時間営業店舗について、「24時間営業の場合は効果はないが、夜は店を休めばいい」と言っていたけれど、それは問題が違うということ。さらにいえば、夜の方が気温は低いのだから、夜に仕事をして、昼間眠っていてもいいはずだ。昼夜交代勤務制なら会社も学校も役所も数は半分で済む。
つまり、国民が知りたいのは、「本当にどれくらい省エネ効果があるのか?」ということで、その部分に懐疑的なのだ。さらに64%対29%のアンケート結果を入手したのだが、実際は48%が賛成で16%が条件付賛成で、29%が反対で、7%がわからないということ。「条件付で反対」という選択肢がないので、「条件付で賛成」という方を「賛成」に分類してはいけないのではないだろうか。それにわからないと言う人が少なすぎるようにも思える。中間層がなく、賛成か、反対かという二元論になっている。
さらに、労働条件についていえば、正確に時間を管理している会社はいいが、中小企業や、残業時間を労使協定で「定額見なし設定」していたり、大企業でも「日が沈むまでは帰らない上司」とかいると、労働強化になる不安は大きい。
ただし、案外、沖縄のように一旦帰宅してから飲みに行くという生活が定着するのではないだろうか。アジアの夜はどこでも熱い。夜の方が涼しいからなのだが。そんなシンガポールのような町になると省エネの話はどこかへ消えてしまう。
さらに、私見なのだが、日本が本気で京都議定書を守る必要があるのだろうかとまで思ってしまう。日本は省エネの技術を開発する方が有効なのではないだろうか。日本が省エネを実施することによりコスト増で生産力が抑制され、議定書未批准国である米国や中国の生産が増えることは、世界のCO2は逆に増えることを意味するように思えてしまう。
そして、サマータイムを導入すると、経済活動は、逆省エネ方面に活気が出て賑やかな夜になりそうに思うのだが、ダメ業種もある。それは都会のビアガーデンだ。夕暮れまで2時間もあるなら、とても暑いビルの屋上へ直行する気分にはなれない(ビアガーデンが衰退していった件は以前考察したことがある)。すでに希少生物化した業態に、これでとどめが刺されるのであろう。
そして、こわいことに、サマータイム制は今国会に法案が出される寸前で、可決されれば2007年から実施が予定されていたらしいのだが、郵政民営化審議(?)が長引いているので、たぶん、一部の質問者の予測通り、すべてに「後回し」になりそうな状況なのである。