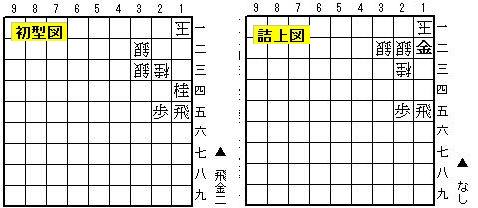焼津方面で、防災関係の話を聴く機会があり、前々から狙っていた「焼津さかなセンター」へ寄り道。

地震の話からだが、さすがに東海地震の対策を念入りに準備している静岡だけあり、宿泊したホテルにも、細かな避難方法が掲示されている。
ただし、地元の方の話では、今回の東日本大地震の結果、今までの対策をすべて見直さなければならないだろう、とのこと。確かに地元の防災センターの建物に入れてもらったが、3階建てで、屋上から海を見れば、15メートルの津波が来た場合、かなり危険だ。それに建物が小さすぎる。
土地柄、高台というのが、あまりなくところどころに丘があり、そこには、たいてい神社があるようで、地元の古老の言い伝えでは、安政の大地震(1854年)の時は夜で外が真っ暗だったが、神社に向かう道に藁を燃やして目印をつけたそうだ。
そして、本題のさかなセンターだが、焼津駅より海側だろうと勘違いしていた。高速道路に近い方だ。
さすがに、カツオ、マグロは豊富にある、というか、あり過ぎる。場内を二周して、ビンチョウマグロの冷凍を買う。一応、中トロ。聞けば、「キズもの」だということらしい。でも、なぜキズものなのか、今一つピンとこない。
もしかして「*射*汚染」。と、頭の中を仮説がぐるぐると回る。なぜ、そんな連想をしたのかと言えば、水爆に被爆した第5福龍丸がボロボロで帰ってきたのが、焼津港である。
その被爆者をモデルに岡本太郎が描いたのが「燃える人」。
どうも、話が前に進まない。
それで、中トロのキズ物を4本1000円で購入する。

解凍して食べたら、かなり高品質のマグロだった。関東のスーパーなどでは3倍の価格だ。


地震の話からだが、さすがに東海地震の対策を念入りに準備している静岡だけあり、宿泊したホテルにも、細かな避難方法が掲示されている。
ただし、地元の方の話では、今回の東日本大地震の結果、今までの対策をすべて見直さなければならないだろう、とのこと。確かに地元の防災センターの建物に入れてもらったが、3階建てで、屋上から海を見れば、15メートルの津波が来た場合、かなり危険だ。それに建物が小さすぎる。
土地柄、高台というのが、あまりなくところどころに丘があり、そこには、たいてい神社があるようで、地元の古老の言い伝えでは、安政の大地震(1854年)の時は夜で外が真っ暗だったが、神社に向かう道に藁を燃やして目印をつけたそうだ。
そして、本題のさかなセンターだが、焼津駅より海側だろうと勘違いしていた。高速道路に近い方だ。
さすがに、カツオ、マグロは豊富にある、というか、あり過ぎる。場内を二周して、ビンチョウマグロの冷凍を買う。一応、中トロ。聞けば、「キズもの」だということらしい。でも、なぜキズものなのか、今一つピンとこない。
もしかして「*射*汚染」。と、頭の中を仮説がぐるぐると回る。なぜ、そんな連想をしたのかと言えば、水爆に被爆した第5福龍丸がボロボロで帰ってきたのが、焼津港である。
その被爆者をモデルに岡本太郎が描いたのが「燃える人」。
どうも、話が前に進まない。
それで、中トロのキズ物を4本1000円で購入する。

解凍して食べたら、かなり高品質のマグロだった。関東のスーパーなどでは3倍の価格だ。














 ボストン美術館に眠る日本美術コレクション5万点の中から、特に鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽にフォーカスして全144点が日本国内で巡業中である。東京は、新装なった山種美術館である。恵比寿駅より少し歩く。
ボストン美術館に眠る日本美術コレクション5万点の中から、特に鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽にフォーカスして全144点が日本国内で巡業中である。東京は、新装なった山種美術館である。恵比寿駅より少し歩く。






 丸谷才一著のエッセイ集。彼の小説は、とても素敵である。「笹まくら」「たった一人の反乱」「女ざかり」「裏声で歌へ君が代」。ある意味、村上春樹よりも読みたい作家だが、残念なことに作品が少ない。なんとなく、没後に全集を作りにくいような気がする。
丸谷才一著のエッセイ集。彼の小説は、とても素敵である。「笹まくら」「たった一人の反乱」「女ざかり」「裏声で歌へ君が代」。ある意味、村上春樹よりも読みたい作家だが、残念なことに作品が少ない。なんとなく、没後に全集を作りにくいような気がする。