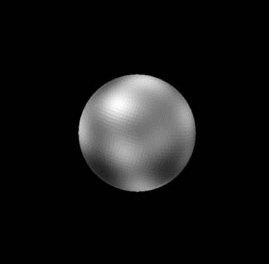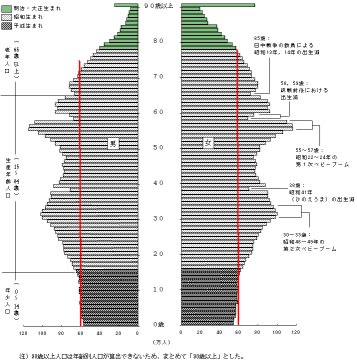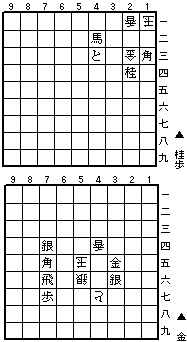藤堂高虎の家訓200箇条、やっと最後までたどり着く。思うに、200箇条ということ自体が長過ぎるのだろう。本当に心に強く残る条というものはあまりなく、一つ一つの処世訓といったものに近い。これが書かれたのは家康の死後、高虎が江戸の上野にある藩邸で生活していた頃のものということで、江戸時代が既に始まってからである。遅れてきた戦国武将である高虎が、人生を振り返り、藤堂家の今後の安寧のため、事細かに注意事項を書き連ねたものと言える。一介の豪族から10人以上も主君を乗り移り、かつ城郭作りのスペシャリストであり、江戸の町割りを担当したり、さらに故郷近江の商工業者を江戸に誘致し、とうとう家康のブレーンの座にすわり32万石という大大名になったわけだ。
その後、藤堂家は外様大名でありながら伊賀・伊勢という紀伊・尾張の御三家の間に領地を持ち、あまり目立たぬように江戸時代をまっとうする。そして、江戸時代の最後にあたる鳥羽伏見の戦いで、突如幕府方から官軍に寝返る。多くの幕軍の諸藩は、「やはり藤堂」とその裏切り行為を高虎の所業に求めたのだが、この200箇条の中にその萌芽はあるのだろうか。判断付けがたい。
そして、本来、遺訓200箇条というのは200箇条で終わりのはずなのだが、200条完成後、高虎はさらに4条を追加する。「念のため」ということだそうだ。高虎らしいと言えばそれまでだ。
第191条 他の家来なり共情らしくものいふへし仇には不可成
他家の家来であっても、情を持って接すべきだ。仇にはならないだろう。
「情をもって接する」というのもヒューマニズムからの行動ではないのは、はっきりしている。打算的である。結局、家来の扱い方については繰り返し家訓の中で触れられているが、領民(大部分は農民)のことについては一切記載がなかった。彼自身は戦国大名であったし、ほとんど領国には住まず、家康とともに駿河(現在の静岡市役所のあたりに住居を構えていた)に住み、家康亡き後は、江戸、上野の丘に住んでいた。領民の管理については、彼の末裔の手に任されたのである。
第192条 諸事に付争事なかれもし物事あらそひ募らハ言事のもとひたるへし可慎
なにごとも争いごとはいけない。もし争いがつのると、言いがかりのもとになる。慎むべきだ。
「言事」というのはどちらかというと、告げ口に近い言いがかりのことだと思う。特に領地が伊勢・伊賀となれば、紀伊家と尾張家の中間にある。なかなか気苦労で大変な場所である。
第193条 人の見廻の時ハ前方にいか程おかしき事有共笑ふべからす尤囁へからす客人の身にして悪敷ものなり
見回りのとき、前方にどんなにおかしい事があっても笑ってはいけない。また、ささやいてもいけない。客人の身になれば面白くないものである。
駅のホームに女子高の制服を着た中年のオヤジがいても笑ってはいけない。気を悪くするだろう。
第194条 座敷にて我か遁れさる者知音衆の噂か咄に出るならハ其儘私のがれす又知音なり余の御咄に被成被下候得と断へしむさとしたる悪口聞間数との嗜なり
座敷で、自分にかかわりがある者や知り合いの噂話がでたなら、それは自分の関わりがある者であり、また知り合いであるから、外の噺にしてください、と断るべきだ。いいかげんな悪口は聞かない、という嗜みである。
隣国の首相の歴史観がおかしい、と米国大統領に告げ口しても、「東アジアのことは、よくわからないから」と逃げ口上を打つようなものだ。(本当は、各国の違いについて、所在地も含め、よくわかっていないのかもしれない)
第195条 追かけ者馬上より切付ハ鐙のふみ様有之
追いかけ者が馬上から切りつけるときは、鐙(あぶみ)の踏み方がある。
この条は勿体をつけたまま、終わっている。どのように鐙を踏めばいいかよくわからない。たぶん、自転車の立ちこぎのようなものではないかと思う。
第196条 取籠り者取まき居るともむさと口をきくへからす内より詞被掛間敷との嗜なり
取囲み者を取り巻いている時は、無駄口をしてはいけない。内側から言葉を掛けることができないとの嗜みである。
取囲まれた者が、降伏するか玉砕するかを落ち着いて考える時間を与えようということだろうか、たぶんそうではなく、外に誰もいないだろうと安心させ、うかつにでてきたところをバッサリやろうということだと思う。
第197条 昼夜共に屋敷の内にても外にてもわやめく共あら増聞届出へしむさと出へからす
昼夜ともに屋敷の中で騒ぐものがいれば、よく様子を聞いてから届け出ること。むやみに届け出るのはよくない。
声高なる者に幸あれ
第198条 客を呼とも挨拶悪敷衆を不可呼吟味有へき事也
客を呼ぶときは、挨拶ができないような衆を呼んではいけない。吟味すべきだ。
パーティでスピーチを頼むと、「ところでスピーチの原稿は書いてくれるのだね。1週間前に届けてくれ」というような輩には天罰を!
第199条 走り込者有時むさと渡すべからす先隠し置子細をよく聞届其主人江常に念比成衆を頼談合づくにして断を申とも又ハ渡すとも前後の首尾再三念を入埒を可明無首尾にして難をきる事有へし
走りこんで逃げて逃げ込む者がある場合は、無造作に引き渡してはいけない。まず隠して、様子をよく聞き、その主人と常に親しい人に相談して、断るとも引き渡すとも、前後の首尾を用心して解決すべきだ。不首尾になり、難を受けることが多い。
忠臣蔵のような話だ。もっとも、彼らが後で斬られたのも当然で、浅野某が前年に死罪になったのは、吉良某のせいではなく、幕府の命令。本来、敵討ちすべき相手は幕府そのものでなければならなかったはず。腹いせに老人に対して集団暴力をふるっただけという見方も多い。
第200条 武芸の内兵法鑓弓鉄砲馬可嗜兵法にてハ切合時手も負す相手を数度切伏るを上手といふへし鑓にてハ人を数度突伏せ利を得る是上手也弓鉄砲ハよく中りあたやなきを上手といふへし馬ハ達者に片尻かけても落さる様に自由に乗を上手といふへしいかに所作を能学ぶとも兵法にてハ切られ鑓にてハ突れ弓鉄砲ハひたとはづれ馬にてハ引つられ度々落るハ下手也調法にならず能々可嗜
武芸としては、兵法のうち、槍、弓、鉄砲、馬を嗜むべきだ。兵法で、斬りあうときけがをしないで切り伏せるのを上手と言う。槍では人を数回突いて仕留めるのを上手という。弓や鉄砲では、よくあたり無駄打ちのないのを上手と言う。馬は、達者に片尻乗りでも落ちないように自由に乗るのを上手と言う。いかに所作を覚えたとしても、兵法では、刀で斬られ、槍で突かれ、弓鉄砲はまったく当たらず、馬に引っ張られ度々落馬するようなのは下手である。使い物にならない。よくよく嗜むべきだ。
200箇条の終わりは、結構地味な話で、殿様としては武術の一般的な必要習熟レベルを書いてある。要するに、上手者と下手者の二元論に分けた時に、上手者の方に入っていればいい、という程度であり、免許皆伝クラスである必要もない、ということである。要するに武士の時代は終わりつつある、という実感を持っていたのだろう。
200箇条が江戸屋敷で口述筆記の終わったあと、さらに言い足りぬと見て、後日、4つ追加した。あまり、キリのいい数字とかにこだわることはなかったようだ。結構、執拗な性格のように思える。
第201条 物毎に不知事ハ誰人にも可尋問ハ一度の恥不問ハ末代のはぢなるへし
知らない物事があれば、誰にでも尋ねるべきだ。問うは一度の恥、問わずは末代までの恥となるだろう。
現代では、「聞くは一時の恥、聞かずは一生の恥」というが、高虎は「聞かずは末代までの恥」とまで言う。
第202条 大小の長短ハ人々相応たるへし少も空鞘ふうたい成事すへからす
刀の大小の長短は、それぞれの人にふさわしくあるべきだ。少しでも空風袋であることはならない。
幕末に、藤堂藩は鳥羽伏見の戦いで幕府を裏切り官軍側に回る。大名レベルで転換したのは藤堂が最初かも知れない(薩長土肥とも殿様は表に出ていなかった)。案外、二本差しが竹光だらけになっているのを知っていたからかもしれない。いったん質流れにしてしまって、新たに購入しようとすると、現在の価格レベルで言えば、まっとうな刀剣は、1本100万円を下らない。
第203条 昼夜ともに大勢寄合之時我刀の置所に能気を可付不慮の時取ちかへ間敷ためなり
昼夜ともに大勢の寄合いの時、自分の刀の置き場所に気をつけるべきだ。不慮の時、取り違えないようにというためである。
大広間で宴会の時、突然の出火で逃げなければならないのに、あわてて自分の靴を探すようなものだ。
第204条 物事聞とも根間すへからす
物事を聞く時に、根本のことを聞いてはいけない。
家訓の本当の最後の最後に、よくわからない言葉がでてきた。第201条では、わからぬことは、他人に聞くことと書かれているのに、第204条では、根本的なことは聞くな!という。要するに物事の本質は、自分の頭で考え、それを構築するための知識は他人に聞けということなのだろう。では、その「根」とはなんだろうかということは、家訓の中で直接的には多く語られることはなかったような気もする。
了
藤堂高虎家訓200箇条は以上で終了である。正式には「高公遺訓集」という。
さて、藤堂高虎については、NHKの大河ドラマに起用するような動きもあるのだが、実際に、大衆向けとなると、なかなか難しいかもしれない。彼の行為に対しては好き嫌いがはっきりしてしまう。家訓を読むと、かなり合理主義者であったことがわかり、能無しの主君のもとをさっさと逃げ出し、すでに秀吉が天下統一を始めると、天下取りをあきらめ、城作りのスペシャリストを目指す。関ヶ原を前に、西軍側から東軍側への寝返り工作に活躍したり、その後は家康の腹心となる。そういう潔くない彼を嫌いな人がいても当然なのだが、あえて彼の肩を持てば、「登場したのが15年遅かった」ということかもしれない。
時代の奔流の中を生き抜いたのは確かであり、彼自身、秀吉と同様に「人生に精一杯感」の強く感じた人生だったと思っていただろう。
さて、藤堂高虎については、ここまで付き合っている間に、いくつかの付帯的情報を得ている。例えば、江戸上野の住居のこと。さらに、千葉県の佐倉に飛び地として領地を持っていたらしい。そのあたりは、何か面白い話もあるのではないかと思っている。また、時期を得るなら、調べて、蒸し返してみたいと考えている。
 2006年3月24日弊ブログ「風太君の新居に関する事情」で触れた話なのだが、千葉市動物園のスーパースターである直立レッサーパンダ風太クンにこどもが生まれていた。6月2日。オスとメスの二頭。公開は9月1日から。
2006年3月24日弊ブログ「風太君の新居に関する事情」で触れた話なのだが、千葉市動物園のスーパースターである直立レッサーパンダ風太クンにこどもが生まれていた。6月2日。オスとメスの二頭。公開は9月1日から。 現在、名前を募集中ということだが、くれぐれももうすぐ誕生予定の新ロイヤルファミリーの名前などで応募しないこと。二頭のこどものどちらがオスでどちらがメスかは不明だが、眼が少し鼻に寄っているのが風太に似ていて、ちょっと離れているほうがチーチーに似ている。
現在、名前を募集中ということだが、くれぐれももうすぐ誕生予定の新ロイヤルファミリーの名前などで応募しないこと。二頭のこどものどちらがオスでどちらがメスかは不明だが、眼が少し鼻に寄っているのが風太に似ていて、ちょっと離れているほうがチーチーに似ている。