先日、神奈川県のパスポートセンターに更新に行った。
パスポートの他に、神奈川県について書かれた小冊子があり、いくつかのデータが書かれていて、少し気になっていた。
「人口」と「県内総生産(GDP)」。
そこには、こう書かれていた。
神奈川県の人口は、スウェーデンの人口に匹敵する約900万人。
神奈川県の県内総生産は31兆円を超え、デンマークやアイルランドに匹敵。
よく道州制の議論で、「九州全体や東北全体が一つの国なら、・・」という言い方をするのだが、神奈川県やほぼ同規模の大阪府は、すでに一つの国と同じ規模になっていたわけだ。
ところが、人口をスウェーデンと比べ、GDPをデンマークやアイルランドと比べるのは、少し意味がわからない。比較が変わるのはおかしい。
ということで、調べようと思っているうちに、ギリシアが国家破綻の危機にある。理由は、放漫財政と国債の乱発。
実は、ギリシアと神奈川、大阪とは、人口やGDPがほぼ似通っていたわけだ。

人口は、神奈川が900万人、大阪が880万人、ギリシアは1100万人。
GDPは、神奈川が31兆円、大阪は41兆円、ギリシアは30兆円である。
予算規模は神奈川が2兆7000億円、大阪が3兆2000億円、ギリシアは「国家」だから割高だが4兆1000億円。
これに対して、国債や府債の発行残高の規模。神奈川が3兆5000億円、大阪が5兆円、そしてギリシアは40兆円である。ギリシアのソブリンリスクから利回りが10%になったそうで、40兆円に10%の利払いを行うと国家予算のほとんどが利子で消える。
ということで、危ないといわれる大阪財政と比べても、ギリシアの現状は、どうみても「ギリシア悲劇」のクライマックスに向かっていると、言えるわけだ。
ところで、ギリシア破綻のキッカケの一つが「2004年のオリンピック」と言われている。五輪を開くには経済規模が小さすぎた。しかし、一方では夏の五輪はギリシア、そして冬の五輪はスイスで永久開催しようという意見もIOCの中にはあるようだ。固定費を無駄にしないようにして、変動費で稼ぐ、ということだろう。
しかし、この話を友人としていたら、「五輪を開催するのではなく、アポロンの丘で採火する聖火を高額で(1兆円とか)開催国に売ったらどうだろう。」という意見があった。
いかにも名案だが、閉会式の時に、完全に聖火を消すのではなく、種火を残しておいて安く転売する国も出るだろう。(こども手当不正受給のような話)
ところで、アテネ国際空港。晴れた日中にエーゲ海に浮かぶアテネの空港に着陸するのは機中から眼下を見ても神秘的に美しい。外を見る乗客からは眺望税を取れるだろう。
パスポートの他に、神奈川県について書かれた小冊子があり、いくつかのデータが書かれていて、少し気になっていた。
「人口」と「県内総生産(GDP)」。
そこには、こう書かれていた。
神奈川県の人口は、スウェーデンの人口に匹敵する約900万人。
神奈川県の県内総生産は31兆円を超え、デンマークやアイルランドに匹敵。
よく道州制の議論で、「九州全体や東北全体が一つの国なら、・・」という言い方をするのだが、神奈川県やほぼ同規模の大阪府は、すでに一つの国と同じ規模になっていたわけだ。
ところが、人口をスウェーデンと比べ、GDPをデンマークやアイルランドと比べるのは、少し意味がわからない。比較が変わるのはおかしい。
ということで、調べようと思っているうちに、ギリシアが国家破綻の危機にある。理由は、放漫財政と国債の乱発。
実は、ギリシアと神奈川、大阪とは、人口やGDPがほぼ似通っていたわけだ。

人口は、神奈川が900万人、大阪が880万人、ギリシアは1100万人。
GDPは、神奈川が31兆円、大阪は41兆円、ギリシアは30兆円である。
予算規模は神奈川が2兆7000億円、大阪が3兆2000億円、ギリシアは「国家」だから割高だが4兆1000億円。
これに対して、国債や府債の発行残高の規模。神奈川が3兆5000億円、大阪が5兆円、そしてギリシアは40兆円である。ギリシアのソブリンリスクから利回りが10%になったそうで、40兆円に10%の利払いを行うと国家予算のほとんどが利子で消える。
ということで、危ないといわれる大阪財政と比べても、ギリシアの現状は、どうみても「ギリシア悲劇」のクライマックスに向かっていると、言えるわけだ。
ところで、ギリシア破綻のキッカケの一つが「2004年のオリンピック」と言われている。五輪を開くには経済規模が小さすぎた。しかし、一方では夏の五輪はギリシア、そして冬の五輪はスイスで永久開催しようという意見もIOCの中にはあるようだ。固定費を無駄にしないようにして、変動費で稼ぐ、ということだろう。
しかし、この話を友人としていたら、「五輪を開催するのではなく、アポロンの丘で採火する聖火を高額で(1兆円とか)開催国に売ったらどうだろう。」という意見があった。
いかにも名案だが、閉会式の時に、完全に聖火を消すのではなく、種火を残しておいて安く転売する国も出るだろう。(こども手当不正受給のような話)
ところで、アテネ国際空港。晴れた日中にエーゲ海に浮かぶアテネの空港に着陸するのは機中から眼下を見ても神秘的に美しい。外を見る乗客からは眺望税を取れるだろう。

















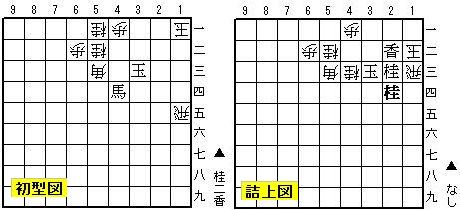
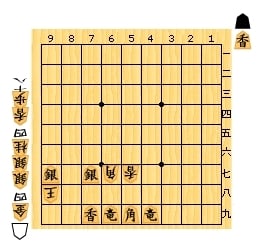


 『ひまわりの祝祭』は藤原伊織の初期の作品である。ミステリ。
『ひまわりの祝祭』は藤原伊織の初期の作品である。ミステリ。


 ところで、最近、ナショナル・ジオグラフィックの特集番組で、イエロー・ストーンのマグマ溜りの話を聞いた。世界に類のない超巨大火山であり、地下100キロより下にマントルが棒状に伸びていて、60万年に一回、超巨大爆発を起こすことで知られている。
ところで、最近、ナショナル・ジオグラフィックの特集番組で、イエロー・ストーンのマグマ溜りの話を聞いた。世界に類のない超巨大火山であり、地下100キロより下にマントルが棒状に伸びていて、60万年に一回、超巨大爆発を起こすことで知られている。 国立公文書館で開催中の『旗本御家人2 幕臣たちの実像』に行く。前回の「旗本御家人I」では、いわば公務員である彼らの仕事を中心に特集していたが、今回の「2」では、どちらかというと、こぼれ話的な変化球が多い。
国立公文書館で開催中の『旗本御家人2 幕臣たちの実像』に行く。前回の「旗本御家人I」では、いわば公務員である彼らの仕事を中心に特集していたが、今回の「2」では、どちらかというと、こぼれ話的な変化球が多い。








