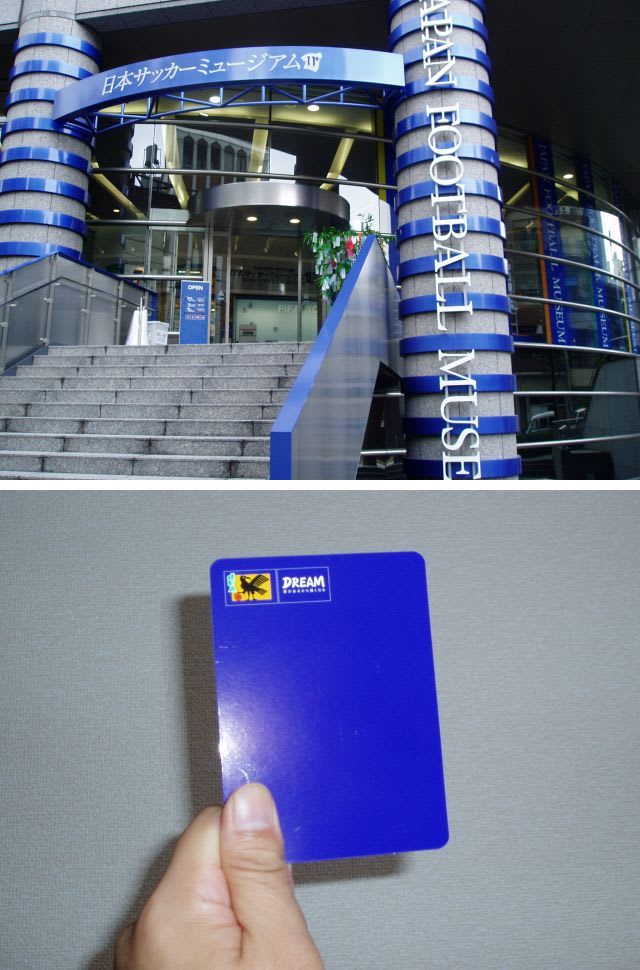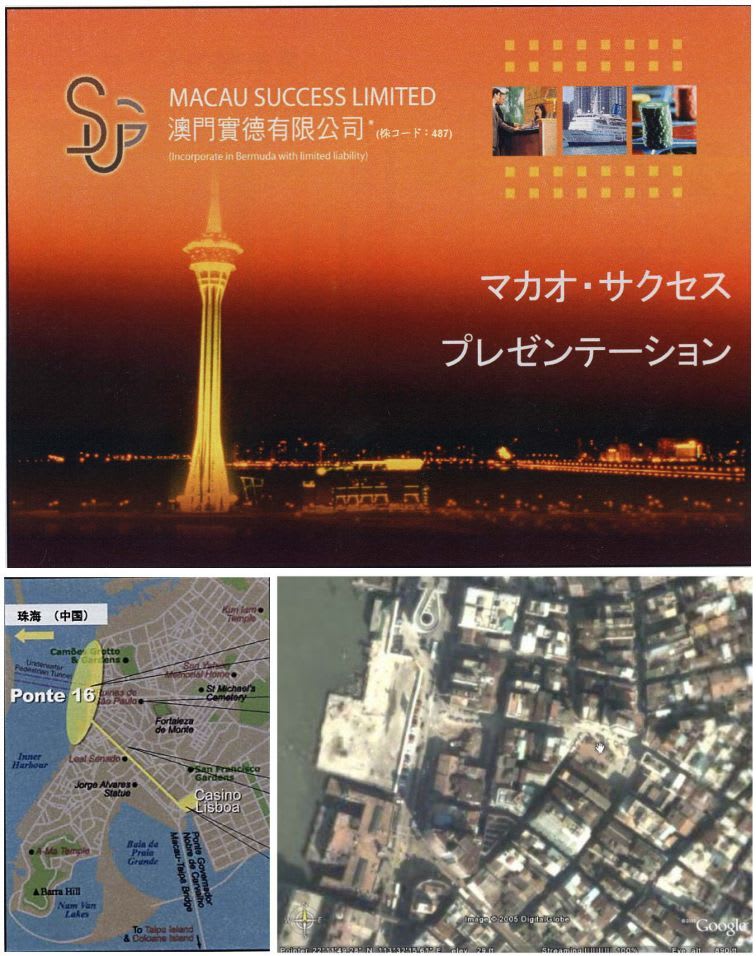第162期通常国会中である。郵政民営化ばかりに目が向いているが、6月末から急に動き出した法案がある。「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」といわれるものだが、その中の一部に、いわゆる「
共謀罪」というのが含まれている。
内容が戦前の「治安維持法」に類似しているため、反対の声も大きいし、ブログ上でも多くの専門家の方が声を上げているし、「共謀罪反対バトン」というのもあるようだ。私は、今までのところ刑法とは付き合いがなく、もとより素人ではあるが、国会の議事録などを追いながら考えてみた。おぼろげに見えてきたのは、治安維持法と同様、当初の主旨と違う目的で運用されるのではないかとの疑惑が消えない。さらに、本案については、今のところ与野党とも議員レベルでは懐疑的になっているように見える。
まず、よってくるところが、国際条約の批准のためというところにあるため、日本の法体系と不一致が多いという性質があるのも馴染めない一因だ。一部の例外を除けば、日本の刑法では、「犯罪を計画した」段階では、まだ罪にはならない。実行段階で、とりやめるかもしれないからだ。しかし、犯行を実行すれば罪になる。多くの議員が主張しているが、焼き鳥屋で3人で飲みながら上司の悪口を言って「あいつをバラしてやろう!」と口走っただけで、
懲役5年になる可能性があるわけだ。しかも宴席をちょっとはずして、携帯で警察にチクった一人は、無罪になったりするのだ!
まるで時代劇の世界だ(鹿ケ谷の謀略とか最後の晩餐とか)。
もう一つ、国際テロの防止を目的にあげているのだが、もともとの国際条約は1990年代に議論していたものなので、どうも
テロ対策を隠れ蓑にして、個人の主権を制限するような法律を作ろうとしているのではないかと疑っている人が多い(というかほとんど)のだ。
それで、法案審議はどこまで進んでいるかと言えば、昨年6月の通常国会の際、議案提示されただけで、今国会にスライドになっている。そして、今年6月24日の衆院本会議で南野法相から主旨説明がなされ、現在、衆議院
法務委員会で審議が行われている。7月12日には9時30分から17時45分まで9人の議員が質疑を行っている。自民党4名、公明党1名、民主党4名。自民党の中の1名はこの共謀罪について、ほとんど触れなかったのだが、残りの8名はかなり疑念を持った質問をし、不明確な回答を聞いただけになっている。前に書いたように、既存法令や日本の法体系と異なっていることで、こういう
法務委員会という専門的な委員会で検討すればするほど矛盾が出てくる。
では、法律の原案と主旨について調べてみる。
法令の名前は、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」というのだが、冷静に考えると、「
国際化」と「
組織化」と「
高度化」という3つの要素があげられている。このうち「共謀罪」に対応するのは主に「組織化」のところだろうが、推進派はテロの例を挙げ、「国際化」対応であることを強調するのだが、それは違うだろう。あくまで犯罪の「組織化」に対応する法案であるのだ。
次に原案だが、以下のとおりだ。刑法を以下のとおり修正(カタカナはひらがなに書き換えた)。
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
五年以下の懲役又は禁錮
二
長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
二年以下の懲役又は禁錮
つまり、特定の犯罪(たとえば国家転覆とか要人暗殺とか)に対して適用するのではなく、犯す罪の重さにより、共謀罪適用か否かを決めようということなのだ。そして、それは懲役4年以上の罪なのだが、日本の法令では、懲役4年以上とすると
600以上の犯罪が対象になる(結果として、有名な犯罪名はほとんど引っかかる)。つまり
凶悪犯罪でなくても、共謀罪が成立してしまうのである。
そして、あくまでも謀議をめぐらす段階では、犯罪は実行されていないので、「
既存法では犯罪と認定されていない段階」から有罪とできるのである。
実は、もう一つ気がかりなのは、現法務大臣の資質である。質疑をみても南野現法相の発言は、意味不明が多い。さらに
副大臣は郵政民営化に反対票を投じるために辞任してしまったため、空席のままだ。警察官僚主導型の議事運営になっているようで危険を感じる。
そして、7月12日の委員会の議事録を読むと、表に出てなかった話も次々にでてきて、国際条約というのが、難しい問題を抱えているというのが見えてきた。
まず、この法律の経緯は
1988年まで遡る。G8を中心として、国連レベルで国際麻薬取引を規制しようというところから出発している。その後、1994年にマフィアの本拠地に近いナポリで国際犯罪組織に対処しようというナポリ宣言を行い、さらに1998年から国連での協議が始まり、2000年11月に「国際組織犯罪防止条約」という形でまとまり、147国が署名し106国が締結済みということだ。
内容は、答弁を読むと、締結国に主に6つの義務を求めている。
1.重大犯罪の共謀を罪とするか、犯罪組織への参加を罪とする(この部分が
共謀罪、または参加罪となる)。
2.犯罪収益の洗浄(マネロン)。
3.腐敗行為。
4.司法妨害。
5.犯罪収益の没収。
6.犯罪人の引渡。捜査、司法協力。
項目だけみれば、当然の話かもしれないが、これを国家間でやろうとするので、難しい問題が噴出してくる。国によって、刑法の罪の軽重が異なるし、犯罪者にも一定の国民としての人権は存在するのも当然だからだ。
そこで問題を「共謀罪」に絞って考えると、「共謀罪」を規定するか「参加罪」かということになるのだが「参加罪」というのは、まったく国内法には存在しない概念ということらしい。日本にもいくつかの犯罪行為を専らとする組織(グループ)はあるだろうが、その組織に入るだけで有罪にするというのは、法的類例がないらしい。一方、共謀行為というのは、いくつかの類例があるそうだ。「凶器準備集合罪」とかかもしれないが、実際にはあまり多くない。
そして、一つの問題は、「重大犯罪の共謀」というのが何を基準にするのかというところだが、「懲役4年以上の罪」ということが国連で決まったわけだ。日本は5年以上、あるいは特定の罪に限定しようと主張したようだが3年以上派とか色々あったらしく、結果として4年以上と決まり、ほとんどの刑法上の犯罪が対象になったということだ(国会議事録から読解)。背景としては、国際犯罪の場合、犯罪行為が分業化されて、各国別には、犯罪の一要素だけが行われるようになり、最終的な犯罪効果の凶暴性にくらべ、一つ一つの犯行の重大性が少ないために一網打尽にできないということだろうか。(多国籍企業の活動とそっくりだ)
7月12日の議事録を読む限り、質疑時間の7割ほどは、この「共謀罪」に対する懸念に向けられている。それは、提出された議案をどう読んでも、国際犯罪防止のためのみにこの共謀罪が適用されるというようには解釈できないからだ。たとえば偽札作りは、重大犯罪であり最高刑は無期懲役だが、実際にはどの段階からが犯罪かどうかは微妙な問題だ。おそらく、犯行の研究をするだけではまだシロで、紙の調達とか画像の作成とか試作段階がグレーで、完成品ができた段階はクロだ。となると、共謀罪が存在すると、二人以上で「偽札でもつくらないか」と相談した段階でいきなりクロになってしまうということだ。たとえば、暗殺とかにしても、暗殺の相談をはじめた時に犯罪が成立し、ただちに密告した人間が無罪になり、その場に呼ばれただけで、まだ迷っている人間が有罪になることになる。「犯罪行為を処罰する」だけでなく「
ココロに縄をかける」法律といわれているのはその犯罪成立時期が時間的に早いところにある。
そして、すでに国会での共謀罪の議論は、「国際麻薬取引」からも「国際テロ」からも離れたところの
「一般犯罪」へ適用することを前提に行われている。かつての悪法と同じ
轍を踏んでいるわけだ。当初の目的から離れて、警察官僚が独走の気配である。要注意であり、国民の監視が必要だ。
そして、実は、当初、言い出したG8各国の反応もバラバラだ。国内に既に共謀罪という法体系を持つ、米英両国は、まだ締結していない。専門家の意見を読むと、「共謀罪」は、
普通の犯罪に対する抑止力はあると考えられている。数人で行うような犯罪は、事前連絡がやりにくいということらしい。しかし専門家たちの大勢の意見は、「
大規模犯罪の抑止力は少ない」ということでもあるようだ。テロや麻薬取引の場合は、どこかの犯罪ブレーンが練り上げた計画の一部が、犯罪行為の手足の部分に「命令」として流れてくるのであって、「共謀行為」ということにはならないからだというのだ。
私見であるのだが、この国会で、審議がどこまで進むのかよくわからないのだが、まだ
十分に論議の時間は必要だろうと思っている。
そして、おまけの話ではあるが、議事録を読んでいて一つ驚くべき発言を見つけた。KM党のA議員の発言の中にある。
我が党のある議員に、この共謀罪を話したら、「犯罪実行行為が必要でなく、合意だけで犯罪になるんです」というふうに言ったら、その人は実は主観説の論者なんですね。主観説は、もちろん「犯罪は心のあらわれだ」という徴憑と見るわけですから、心そのものを「本来、悪い心を処罰するんだ。」こういう考えですよね。その主観説の我が党の議員は、「いよいよ主観説が刑法の原則になったか」と言って喜んでおられたんですが、とんでもないことを言うなと私は思っております。
さすが、他の政党とは気合が違うな、と思うと同時に、そんな
怖い事を考えている人間が党内にいる、ということを正直にバラしてしまったA議員が、次の選挙で公認を得られるかどうか大変心配になってしまうのだ。なにしろ共謀罪と密告無罪が成立するのは、あくまでも犯罪行為に対してだけなのであり、党の幹部達が
公認を決める時の密談は法律の対象外だからだ。
 沖縄の海の水を北海道に捨てに行く男 キン・シオタニ
沖縄の海の水を北海道に捨てに行く男 キン・シオタニ