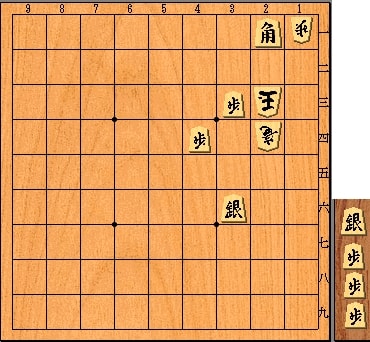第一生命ビル南ギャラリーで開催中の関根直子展へ行く。第一生命ビルとは終戦後、マッカーサーの執務室があったことで有名だが、現在では建て直され巨大金融センター風の立派すぎる生保ビルになっている。南ギャラリーは現代美術の展覧会が行われている。

今回は、関根直子さん。
ただし作品は、われわれ凡人には、なかなか理解しづらい。全作品がモノクロ画である。さらに、使用した画材が、おもに鉛筆とボールペンだ。

一方、関根直子さんだが武蔵野美術大学で油絵を専門にしていたようだ。1999年の卒業制作でこれらの作品群を仕上げたようだが、油絵を専門にしていたのに鉛筆と黒色のボールペンを用いて線を何重にも重ねていって、その意味をわれわれに問うわけだ。
白いキャンバスに果てしなく一筆書きで線を重ねる行為は、ある意味我々の人生と似ているわけだ。生か死か。そういえば、第一生命ビルであることを思い出させる。

今回は、関根直子さん。
ただし作品は、われわれ凡人には、なかなか理解しづらい。全作品がモノクロ画である。さらに、使用した画材が、おもに鉛筆とボールペンだ。

一方、関根直子さんだが武蔵野美術大学で油絵を専門にしていたようだ。1999年の卒業制作でこれらの作品群を仕上げたようだが、油絵を専門にしていたのに鉛筆と黒色のボールペンを用いて線を何重にも重ねていって、その意味をわれわれに問うわけだ。

白いキャンバスに果てしなく一筆書きで線を重ねる行為は、ある意味我々の人生と似ているわけだ。生か死か。そういえば、第一生命ビルであることを思い出させる。















 自宅に茶道具が、いささかの量で存在する。質はたいしたことはない。親戚筋からの寄贈であるが、茶はまったくやらない(今までのところ)。
自宅に茶道具が、いささかの量で存在する。質はたいしたことはない。親戚筋からの寄贈であるが、茶はまったくやらない(今までのところ)。 非まじめとは、まじめと不まじめを統合するような概念だそうだ。なんというか、考え方というのは多面的でなければならないとし、絶対的に正しいものは存在しないというような論理である。著者はロボット工学の第一人者である上に、仏教にも詳しく、そういう科学と哲学の交差する部分を、例を挙げて様々に考察する。
非まじめとは、まじめと不まじめを統合するような概念だそうだ。なんというか、考え方というのは多面的でなければならないとし、絶対的に正しいものは存在しないというような論理である。著者はロボット工学の第一人者である上に、仏教にも詳しく、そういう科学と哲学の交差する部分を、例を挙げて様々に考察する。 丸の内の出光美術館で開催中(~10月21日)の『東洋の白いやきもの』展。
丸の内の出光美術館で開催中(~10月21日)の『東洋の白いやきもの』展。