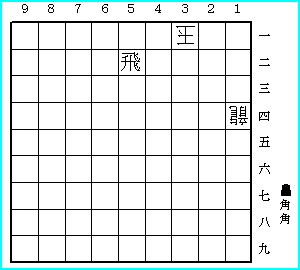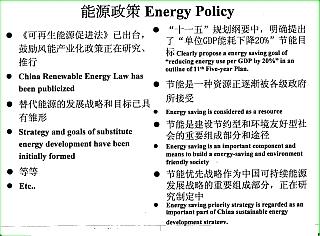勤務先は中小企業なので、都内の雑居ビルに入っている。1フロアの半分程度を使っていて、その階にはごく普通に男女別のトイレがある。男性用には、小用のための器が何個か並び、その背後に何個かのウェスタン方式の個室が並ぶ。特に、どこでもあるレイアウトだろう。
そして、ある日、昼下がりの2時頃だったのだが、トイレから帰ってきたある部下の社員が、
部下:「おおたさん、トイレが変なのです」と相談にきた。
お葉:「変って?」
部下:「個室から大きなイビキが聞こえてくるんです。」
お葉:「二日酔じゃないの?」
部下:「イビキが息を継いでいて、大き過ぎます」
お葉:「どれどれ」
よく知られている話だが、脳内出血して意識不明になると、大きなイビキを立てることが多い。さらに、トイレではよく脳内出血を起こしやすい。一方で、勤務中に昨夜のご乱行の影響で眠くなって、個室に入る人間もいる。後者はどうってことないが、前者だとたいへんだ。これもよく知られているが、直ぐに病院に運ばなければならない。
しかも対象人物は個室の中である。それに、中にいるのが誰なのかはわからない。社内をみても全員着席しているわけでもないし、別の会社のことなどわからない。違うフロアかもしれない。そして、ドアをぶち破ることも考え、もう一人肉体派社員をつれて、トイレに行く。確かに高イビキである。中を窺おうとしても、ドアの隙間は天井との間の5センチだけである。
とりあえず、ドアのそばで物音を立てると、イビキの音が変わる。しかし、少し音程が高くなった後、すぐに元の音程に戻る。起きない。
いったん、トイレから出て、緊急対策会議を開く。決定事項。
1.5分後に現場を再確認する。
2.もし、状況が同じなら、ドアを激しく叩いてみる。
3.それでも反応がない場合、携帯電話を天井の5センチの隙間に入れ、やむを得ず盗撮する。
4.人間がいる場合、ビルの管理人に連絡する。
5.すぐに管理人がこない場合、119番する。
まあ、素人がドアをぶち破っても、どうせ救急車を頼むしかない。
そして、5分後に救出チームが現場にいったところ、
個室には、既に誰もいなかったのだ。(残り香もなし。さらに、ドアは単に、5センチ持ち上げれば、外れる方式だった。)
二題目は、国政に関する重要な話題。安部首相のトイレ問題だ。発端がどこかはわからないが、週刊誌数誌が掲載した後、立花隆氏が日経BPの過激コラムで取り上げたので、噂が沸騰している。「安部短命論」が政権の話ならともかく、文字通りの短命論なので、救いのない話題だ。
もともとは、2月10日に慶応病院で行われた総理の健康診断が、「突然で、かつ時間が長過ぎる」という情報と、自民党の政治家からの「夕方までの会議の後、一杯飲まずにすぐ家に帰る」という情報があったらしい。そこに新たな情報が追加されたのだが、それがトイレに関係ある話だ。
これも自民党の政治家からの話で、会議の合間の休憩時間に自民党本部のトイレに一緒に行くと、安部総理は、常に小用器ではなく、個室に入るとのことなのである。「常に」である。これをもって、「重大な内蔵疾患説」がわきあがり、「紙おむつ説」が流れ、さらに新規情報として、立花隆氏の調査により、安部氏の父系家系の男性平均寿命は40歳台という短命家系説が加えられ、さらに首の皺の深さまで論評されることになれば、さすがに2ちゃんねる中心に立花批判で荒れた話になっているとのことだ。
しかし、トイレの個室に入るからといって、少し推測し過ぎているのではないか、とは誰しも思うところだろう。思考のジャンプ。可能性を考えてみると・・
1.最近の男性は、立ちションではなく、座りションが多いということなのだから、ただ、座りションスタイルというだけではないだろうか。
2.前の開かないトランクス型を着用しているのではないだろうか。
とかだ。あるいは、
3.奥様のアッキー以外のことを考えながら、個室で禁断の遊戯を行っているのではないか、とか・・(ビル・クリントンほどのネアカな行動力はなさそうだから・・)
紙おむつといえば、以前は三木武夫氏が有名だったが、もしも本当になんらかな処置が必要ならば、先日のNASAの凶暴女性宇宙飛行士のように長時間タイプのものを使った方がいいだろう。女性用とは構造が違うかもしれないけど・・
いずれにしても、本人が参議院選挙が終わるまでの短期政権と考えているなら、このまま、もやもやとして次の政権話になってしまうのだろうが、ちょっと気にはなる話だ。










 そして、このボールが急に話題になったのは、ボールの発明者が今、アメリカで一騒ぎしているから、ということらしいのだ。その人物の名前だが「手塚一志」氏という。れっきとしたピッチングコーチでレンジャーズの大塚投手のコーチをするため、渡米中だったそうだ。しかも、このボールの発明は今から12年も前、1995年だそうだ。阪神淡路大地震、地下鉄サリン事件、ウィンドウズ95の年である。ビッグニュースに埋もれたというわけではないが、この秘球は、ほんの一部のピッチャーが使っていたそうだ。たとえばトモキ・ホシノ、シュンスケ・ワタナベといったところで、松坂は昨年、覚えたらしい。そして、日本勢は2シーム・ジャイロを投げるそうだ。(ということは4シームジャイロも投げられるのではないだろうか)
そして、このボールが急に話題になったのは、ボールの発明者が今、アメリカで一騒ぎしているから、ということらしいのだ。その人物の名前だが「手塚一志」氏という。れっきとしたピッチングコーチでレンジャーズの大塚投手のコーチをするため、渡米中だったそうだ。しかも、このボールの発明は今から12年も前、1995年だそうだ。阪神淡路大地震、地下鉄サリン事件、ウィンドウズ95の年である。ビッグニュースに埋もれたというわけではないが、この秘球は、ほんの一部のピッチャーが使っていたそうだ。たとえばトモキ・ホシノ、シュンスケ・ワタナベといったところで、松坂は昨年、覚えたらしい。そして、日本勢は2シーム・ジャイロを投げるそうだ。(ということは4シームジャイロも投げられるのではないだろうか)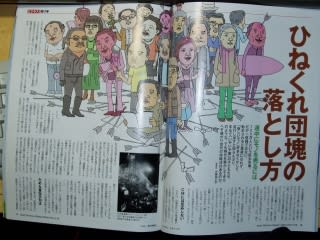

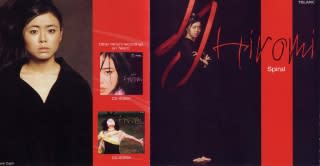
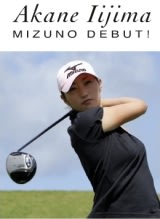
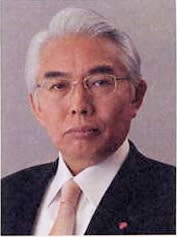
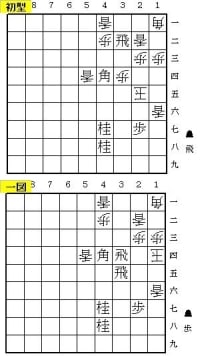
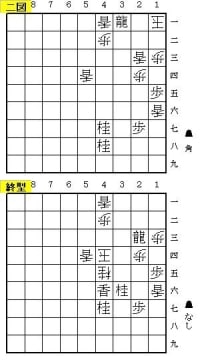
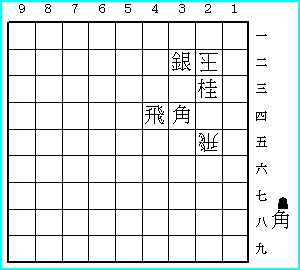







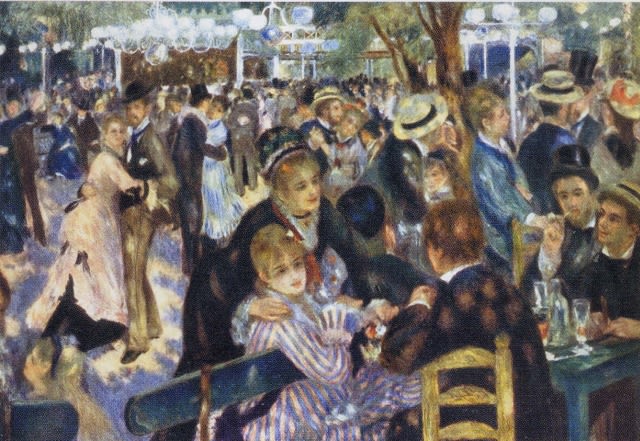
 以前、ビール会社3社の決算書分析したことがある。キリン、アサヒ、サッポロ。サントリーは非上場。目的は、アサヒとキリンの戦略差の解明とサッポロビールの悪さ加減の把握。
以前、ビール会社3社の決算書分析したことがある。キリン、アサヒ、サッポロ。サントリーは非上場。目的は、アサヒとキリンの戦略差の解明とサッポロビールの悪さ加減の把握。 つまり、基本的には、ビール部門を切り離して、キリンかアサヒか外資かの生産工場にするというのが唯一の選択で、不動産部門はどうにもならない感じだ。誰かが借金棒引きしないと収まらないだろう。
つまり、基本的には、ビール部門を切り離して、キリンかアサヒか外資かの生産工場にするというのが唯一の選択で、不動産部門はどうにもならない感じだ。誰かが借金棒引きしないと収まらないだろう。 もちろん、クアーズ、ハイネケン、カールスバーグなどにしてもサッポロ商戦に参戦したいのは山々なのだろうが、後は、爆騰、爆沈を繰り返すだろう今後1ヶ月くらいの株価の行方次第なのだろう。個人的意見としては、国内メーカーが買収すると、価格競争が鈍化して、消費者はガッカリということだろうから、外資系の出資を期待する。ベルギー産の小麦ビールもたまに飲むと美味。
もちろん、クアーズ、ハイネケン、カールスバーグなどにしてもサッポロ商戦に参戦したいのは山々なのだろうが、後は、爆騰、爆沈を繰り返すだろう今後1ヶ月くらいの株価の行方次第なのだろう。個人的意見としては、国内メーカーが買収すると、価格競争が鈍化して、消費者はガッカリということだろうから、外資系の出資を期待する。ベルギー産の小麦ビールもたまに飲むと美味。 だが、どういう結末になったとしても、サッポロのレストラン部門が経営している、サッポロビール園の「生ラム肉ジンギスカン」だけは、地球上に残してもらいたいと切に願っている。札幌出張時の数種類の楽しみの中の一つだからだ。
だが、どういう結末になったとしても、サッポロのレストラン部門が経営している、サッポロビール園の「生ラム肉ジンギスカン」だけは、地球上に残してもらいたいと切に願っている。札幌出張時の数種類の楽しみの中の一つだからだ。
 米国のスターというのは、基本的に「ヒマ」なわけだ。米国内のCMには出ない。所得がべらぼうに高いから、アルバイトはしない。グラミー賞の授賞式に行っても、現場で歌ったりしないから、受賞の時のスピーチを考えるだけでいい。時間を持て余すから、あれこれと騒ぎを起こす。日本のスターは、多忙である。いつ、失脚するかわからないから、走り回って小銭を掻き集める。芸能生活50周年などという貧乏丸出しの人間までゾロゾロ出現する。
米国のスターというのは、基本的に「ヒマ」なわけだ。米国内のCMには出ない。所得がべらぼうに高いから、アルバイトはしない。グラミー賞の授賞式に行っても、現場で歌ったりしないから、受賞の時のスピーチを考えるだけでいい。時間を持て余すから、あれこれと騒ぎを起こす。日本のスターは、多忙である。いつ、失脚するかわからないから、走り回って小銭を掻き集める。芸能生活50周年などという貧乏丸出しの人間までゾロゾロ出現する。 2.アンナ・ニコル・スミス(39)とその関係者
2.アンナ・ニコル・スミス(39)とその関係者 一番、驚いたのは、この容疑者は、翌日、約300万円で保釈される。もちろん足首にGPS用の電波発進装置がとりつけられているのだが、「誘拐」とか「殺人」というのは、未遂と言っても重罪。日本では考えられない。留置場が一杯なのだろうと想像することができる。この行動力から言うと、逃走する可能性だってあるのではないだろうか。
一番、驚いたのは、この容疑者は、翌日、約300万円で保釈される。もちろん足首にGPS用の電波発進装置がとりつけられているのだが、「誘拐」とか「殺人」というのは、未遂と言っても重罪。日本では考えられない。留置場が一杯なのだろうと想像することができる。この行動力から言うと、逃走する可能性だってあるのではないだろうか。