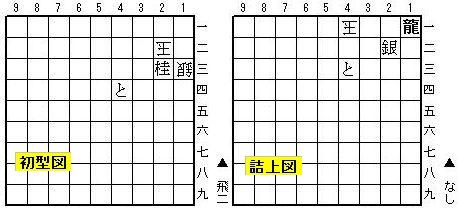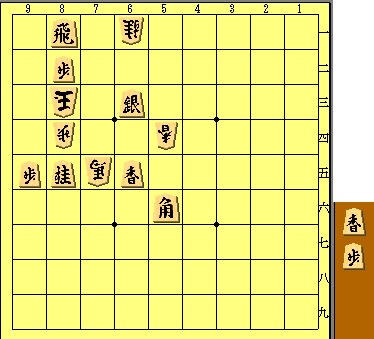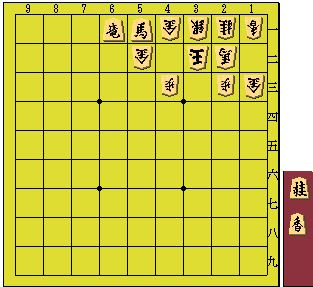ドキュメンタリーといっても分野は様々だが、極めつけは戦記ではないだろうか。要するに生きるか死ぬか。殺すか殺されるか。また、合理と非合理が混じり合う。
ドキュメンタリーといっても分野は様々だが、極めつけは戦記ではないだろうか。要するに生きるか死ぬか。殺すか殺されるか。また、合理と非合理が混じり合う。さらに、日本人が書いた戦記というのも、もう著者の年齢的な問題もあり、これ以上は増加しないだろうと思うのである。
さらに言うと、戦記を書き、そしてそれを読むというのは、「生き残った兵士」がいればこそ、ということになる。
まあ、そういうこともあり、毎年、8月には戦記を読もうと思ったのだ。
「海軍電信兵戦記」。
ごく普通の都内に住む青年がいわゆる赤紙によって招集され、海軍電信兵として南方戦線に送りこまれる。そこには、壮絶な悲壮感というよりも、国家存亡の危機という国民の背負った不可解な命題と、それでも生き延びたいという個人の人間的な気持ちが微妙に混じり合うのである。
一介の電信兵は昭和17年夏に召集され、約一年間の日本国内での研修を終え、ニューギニアの近くであるラバウルに向かう。
が、すでに南太平洋は激戦のさなかにあり、米軍機の急襲を受け、ラバウルの滑走路で被弾してしまう。そして病院戦によって帰還するも、再び戦局不利の中、パラオへ向かうも、時局は日本にとって好転せず、結局フィリピンの山中の秘密基地まで転進。
幸いにして、彼は軍隊生活では唯一の発砲はフィリピンで食糧不足に陥った時に、野生の鶏を食糧とした時だけ。
昭和20年8月15日の玉音放送も、通信機器が故障したままで、うまく聞こえず。陸軍からの伝令でやっと武装解除し連合国に投降。
本土に連絡をつけることはかなわないまま、復員船(帰り船)に乗り込む。その際、誤って戦犯容疑をかけられ無実の罪を着せられ処刑されたものも多いと書かれている。
そして、空襲で焼かれた東京で目指す実家で、電信兵は父母や兄弟と再会することはできたのだろうか。全体に押さえの利いた文章でつづられてはいるものの、読者の緊張は徐々にフィナーレに向かってたかまっていくわけだ。
なんとなく、戦記というのも、何冊かは読んでみたいなあと思うようになったのである。











 東急線沿線の某高級住宅地にある百貨店で笹倉鉄平展が開かれていた。
東急線沿線の某高級住宅地にある百貨店で笹倉鉄平展が開かれていた。 一枚の作品に、「売却済」シールが何枚もついている場合があるが、それは、この作品群がいわゆる版画類であるからだ。といってもそうは見えないところが現代的なのだろう。
一枚の作品に、「売却済」シールが何枚もついている場合があるが、それは、この作品群がいわゆる版画類であるからだ。といってもそうは見えないところが現代的なのだろう。 ただ、美しい絵が好まれて買われているかというと、実際にはちょっと違うなという感じがしていて、「売約済」シールが集まっているのは、どちらかというと、心象的な題材を取り上げたものが多いように思う。心の不安や、未来の社会へのぼんやりとした不確実性というのが周辺住民(=高額所有者)の心にも芽生えているのだろうか。
ただ、美しい絵が好まれて買われているかというと、実際にはちょっと違うなという感じがしていて、「売約済」シールが集まっているのは、どちらかというと、心象的な題材を取り上げたものが多いように思う。心の不安や、未来の社会へのぼんやりとした不確実性というのが周辺住民(=高額所有者)の心にも芽生えているのだろうか。