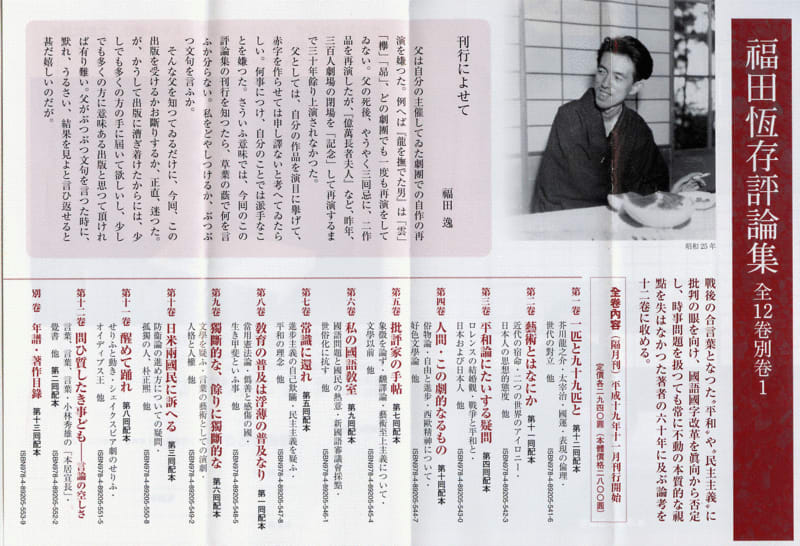(承前)
さて次は、福田恆存と金田一京助の論爭の行司役としての識者のコメントを見てゆきたい。
まづは高橋義孝の「國語改良論の『根本精神』をわらう――金田一博士の『福田恆存氏のかなづかい論を笑う』を讀んで――」である。この論文は、『中央公論』の昭和三十一年六月號に載つたものである。内容はいたつて明快で、この標題が示す通り「國語改良論の根本精神」つまり「一種の合理主義、便宜主義、その言語解釋に看取せられる機械論的偏向、言語道具説」に「全然反對」だといふことだ。論の大半は、このことに費やされ、フロイトの夢分析やら高橋獨特の譬喩で、言語は道具であると同時に内容そのもものだといふことが記されてゐる。
しかし、金田一福田論爭で論じられてゐるのは、果してさういふ觀念的なものであらうか。この場合の「觀念」とは決して惡い意味ではない。絶えず「本質」を重視する福田恆存が、國語問題について本質を論じなかつたわけではないし、言語とは何かといふ問ひ=言語觀といふ觀念から論を起こしてゐることは言はずもがなのことである。しかしこの國語問題なかんづく假名遣ひのことに關しては、本質はまづどのやうな假名遣ひを用ゐるかといふことに表はれるのであつて、言語道具説などといふ抽象論で片が附くものではない。
したがつて、高橋は自分で行司役を買つて出てきたのであるが、今讀むと、何とも話がかみ合つておらず肩透かしの印象が濃い。問題點を整理し切れてゐないのである。この原因ははつきりしてゐる。高橋が國語について調べようともしないのでは、行司はできない。もちろん素人の立場から見たらその程度で良いのかも知れない。しかし、國語にとつては、やはり正確な行司が保しいのは正直な思ひである。望蜀の願ひである。具體的に見ていかう。
高橋の立場は次の一文ではつきりと出てゐる。
「すべて國語問題は成り行きに任せた、天然自然が最上の途だと私は深く信じているから、改良案を試作するのはまだいいとしても、こうすべきだ、これが正しいということをいうのはどうも面白くないと思う。」
この一文が、現代假名遣ひで書かれてゐるのを見ても分かるやうに、時代が變はり、人人が「現代かなづかい」を使ふのだつたら(具體的には、高橋自身が歴史的假名遣ひで書いてゐたとしてもそれを掲載する雜誌や新聞の編輯者が「現代かなづかい」に直しますよと言ふのであれば)それで良いが、國語學者がそれを先導するのは宜しくないといふ程度の意見に過ぎないといふことである。これを以て「穩健」と世間では言ふのだらうが、これでは國語問題の本質に觸れてゐないといふ意味で、「日和見」であるとも言へる。結局、高橋も「假名遣ひ」は手段の次元の問題であると考へてゐるのであるし、いくらフロイトの例を引いて縷縷言語道具説の批判しても、この一文で國語改革の劍の威力は消えてしまふことになる。だから、高橋が次のやうな國語學者への不滿を述べても、説得力がないのである。
次囘にそれを述べる。