久しぶりに八木義徳の本を手にした。大阪の家の本の整理をしてゐてふと目に留まつたのがその理由である。しばし、手を止めて読み始めてしまつた(これだから本の整理には時間がかかる!)。
『家族のいる風景』の中の掌編、「春の死」である。
この題名から大方の人が予想するものとは、いささか内容が違ふだらう。
六十七歳になる作家と二十歳ほど年若い妻との会話から始まる。妻が子宮筋腫になり手術をすることになる。一方、病気と言へばぎつくり腰程度しかしたことがない「私」である。しかし、作家といふ仕事において必ずしも屈強であることが利点となるわけではないといふ(このあたり私小説作家の考へが滲み出てゐる。丸谷才一がこれを聞いたら激情するだらう。だから日本の小説は貧しいのだ、と。八木義徳1911年生まれ。丸谷才一1925年生まれ)。
「あまりに強健すぎる人間は、陰翳の色彩というものを知らない。闇の賑やかさというものを知らない。神経の戦きや感覚の慄えというものを知らない。彼の知っているのは、ただのっぺらぼうに陽の当る平面の世界だけである。」
そこで「私」は自問自答する。「しかし私は、ほんとうに強健な人間なのだろうか。」
そして、「私」は小学校五年生の頃のことを思ひ出す。そして、この場面がこの小説の重要な部分である。
転校生の男の子に惹かれる。
その転校生が、極めて悲惨ないじめにあつてすぐに転校をしてしまふ。
その学校の周辺には精薄の中年男性がゐた。
これらすべてには、性的な関はりが記されてゐる。
そして、場面は再び妻の病気の話になり、アルミ製の盆に載せられた妻の子宮筋腫の物体が描写される。
「私の滑稽で哀れなギックリ腰は、しかし、いつになったら癒るのだろう」でこの小説は終はる。
春の死とは、幾重にも死は暗示されるが、その死は生をも予感させるか。さうとも断言できない。死と再生などとすぐに分かり切つたことを言はれるが、八木はそんなことは言はない。そして、死の痛みを「滑稽で哀れなギックリ腰」としてしか感じない自分を笑つてゐるやうでもある。私小説家としての八木は、丸谷才一の主張にもびくともしない存在である。




















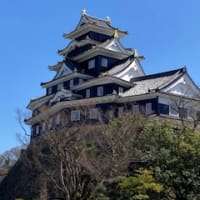








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます