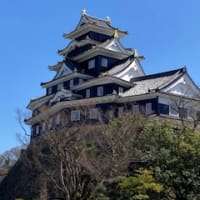今日、岡本かの子の小説「蔦の門」を読んだ。
滋味深い掌編である。
かの子の実体験であらうか。「書き物」をする「私」は蔦の絡まる門のある家に住むことが多かつたやうだ。その家には年老いた女中がゐた。その女中は性格上の問題もあつて二度も離婚をし、身寄りとも仲たがひをしてゐて孤独である。
ある日、その蔦を通りかかつた少女たちが切つて遊んでゐた。それを咎める女中と少女たち。犯人と思しき少女もまけじのやり取り、自分と似た性情を感じたのかその少女に怒りと共に親しみも感じることになる。いつしか蔦を切る遊びに関心が失せ、近寄らなくなる少女に寂しさも感じ始める。その少女はお茶屋の娘で、お茶を買ひにその店に行く。その少女もまた父母に先立たれ、伯母夫婦の養女になるかも知れず、気兼ねしながら生活してゐる境遇であることを知る。
孤独が孤独を引き寄せる。そして、いつしか二人には一定の距離を保つた近しさが生まれる。
強情な老女中(老婢)の心の中に、「人の子に対する愛」が生まれる。
かう粗筋を書くと、味気ない身辺記になつてしまふが、かの子の文学には味はひがある。青空文庫にあるのですぐに読める。
「私」がさうした老婢の変化を見て胸に浮かんできたのが、西行法師の歌である。
年たけてまたこゆべしと思ひきや命なりけり小夜(さよ)の中山
(年老いて、ここを再び越えられるとは思つてもみなかつた。命があればこそなのだなあ。 小夜の中山よ)
来週、掛川に行く。偶然であるが、いい小説がいい出会ひを引き寄せてくれたやうにも感じた。