夏川草介といふ作家の名前は以前から知つてゐた。『神様のカルテ』といふ作品は映画にもなり、それが人気のある原作に基づいてゐるといふことも何となくは知つてゐた。
しかし、その映画も原作も見たり読んだりしようとは思はなかつた。主人公を演じてゐるのが櫻井翔といふあまり好きではない俳優だからかもしれないし、医療ドラマといふだけであまり気が乗らなかつたからかもしれない。理由は特にはないが、気が向かなかつたといふことである。
では、なぜ今回この夏川の小説を読んだのか。これが良くも悪くも日本人的私の生き方であるが、知人に紹介されたからである。
年若き青年二人から、夏川草介を愛読してゐると言はれ、では読んでみるかと重い腰を上げた次第である。
読了第一号が、この『始まりの木』である。
ずゐぶん批評的な小説であつた。漱石の『三四郎』並みの現代日本否定論である。主人公である二人、民俗学者の大学准教授古屋神寺郎とその弟子で修士課程にゐる藤崎千佳とが訪ねる或る寺の住職は「亡びるね」とつぶやく。「金銭的な豊かさと引き換えに、精神はかつてないほど貧しくなっている。私には、この国は、頼るべき指針を失い、守るべき約束事もなく、ただ膨張する自我と抑え込まれた不安の中でもだえているように見える。精神的極貧状態とでも言うべき時代だ」と古屋も語る。柳田國男の民俗学への郷愁やその遺志を受け継がうとの思ひが古屋とそしてそのことに気づき始めた藤崎にはある。それらは師匠の毒舌とそれにもへこたれない弟子の口応へとの軽妙なやり取りから滲み出る。
先に引用した古屋の発言それだけを、私達の日常にぽつんと置いてみれば、その言葉を受け継いで「さうだ」「さうだ」と相槌が打たれ話題が膨らむといふことはなるまい。きつと白けて、周囲から人は離れ、その言葉だけがそこに残つていくことになる。
いやいや単行本が売れ、文庫本になるぐらゐ売れてゐるのだから、そんなことはない。日本人は誰もがかういふ現状認識をもつてゐるはずだとの反論が直ちに返つて来さうだが、それは本当だらうか。「精神的極貧」の人が欲しいのは、「金銭的な豊かさ」なのであつて、こんな言葉を求めてはゐない。この言葉を求めてゐる人が多くゐるのであれば、それは日本は大丈夫だといふことになる。
しかし、もしこの小説のこの言葉が社会的に受け入れられるのであれば、「精神的極貧」であることに気づかない「極貧」といふことであり、もつと深刻な状態なのではないかといふ疑問である。
果たして日本の現状が奈辺にあるのか、それを知るためには、古屋ばりに日本の現状を憂いて見せればよい。「そんなに卑下する必要はないよ」「大丈夫」「ネガティブな言葉を吐くと暗くなるよ」などと親切ごかしに言つてくる人が多いのであれば、日本の現状は相当に貧しいといふことであらう。
「始まりの木」は、さういふ絶望を感じた人だけが発見できる木で、柳田國男の覚悟を受け継いだほんの一握りの人だけがその場所を知ることができるのであらう。
精神的極貧を単純に憂える人、そして無闇にポジティブに生きようとする人、彼らには「始まりの木」は目の前にあつても分からない。そんな気がした。古屋はこの言葉を吐いて問題を克服してはゐない。彼は日常生活に問題を背負ひ込む。しかし気分的絶望家は呟くことで救はれてしまふ。
読者はさてどの位相にゐるか。
夏川といふ人の日本批評の目がどこにあるのか。この一作では分からなかつた。もう少し読んでみようと思つた。




















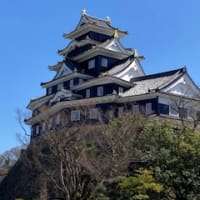








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます