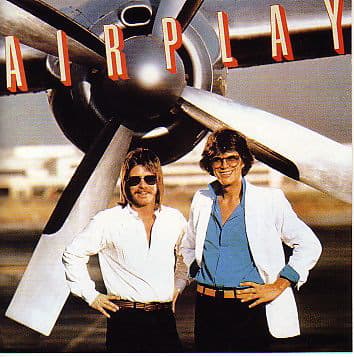今回は情報発信ではない。ちょっとだけ回想してみる。お許しいただきたい。
学生時代、年末年始はバイトに明け暮れていた。むろん数ヶ月後に払うための授業料を稼ぐためである。当時は今ほど労働時間に規制がなかった。そのため働こうと思えばいくらでも働くことができたのだ。
普段でも12時間くらい働くのは当たり前だったが、年末年始の時期だと「正月手当」がつく。加えて大学の授業はないから働きホーダイ。雇用する側も大歓迎で「え?働きたいの?いいよ、どんどん働いてよ!」てな感じ。だからトラックのハンドルを握り続けて1日に17時間なんて珍しくなかった。
とはいえ所詮はバイト。配車係から与えられるトラックは毎回オンボロばかり。そこそこの規模の運送会社であれば大抵「運行前点検」をする。運転前にトラックの外観、タイヤの空気圧、エンジン・オイルの量、ラジエータの水などを確認するのだ。
各項目をちゃんと点検しないと配車係から大目玉を食らう。いや、運行前点検は配車係に怒られるからやるというより、自分の命に関わることなのでやらないわけにはいかない。何せ与えられるトラックの総走行距離は60万kmとか70万kmなのだ。トラックでいえばロートルもいいとこ。
そんなオンボロでも近場をノロノロ走るのなら問題はない。ところが高速に乗って往復500kmも走るのだ。場合によっては1,000kmもジャーニーしなければならない。最近のトラックは知らないが、当時のトラックなんてエンジン・オイルの消費がハンパでなかった。運行前点検の時に規定の量のオイルを入れても、ひとまわりしてくればオイル・ゲージに付かないほどオイルは消費したのである。もしオイルの量を確認しないまま旅立ったら、運が悪ければ途中でエンジンが焼き付き、高速道路上で文字通り「死の旅」に行くことになる。運行前点検を欠かさなかったのはそのためだ。
笑っちゃうのは当時運転中ワシの脳みそのなかで鳴っていたのが《巡礼の年》だったこと。これはリストのピアノ曲集なのだが、なぜ《巡礼の年》なのかは覚えていない。オンボロのトラックなのでエアコンはおろかカーラジオも機能しない。そんななかでこの曲集のなかの《泉のほとりで》とか《オーベルマンの谷》、さらには《ダンテを読んで》が頻繁に「流れて」いた。さすがに《葬送行進曲》が鳴りだした時にはアセッたけどね。死出の旅かよ!…と。
睡魔と闘いながら、よくもまあ走り続けたものだと思う。さすがに今はそんな労働をしていないが、相変わらず正月はない。特に今年は。詳しくは言えないが変更の可能性のある原稿待ちなので遠出できないというわけだ。高速に乗らないのに「拘束」とは、これいかに。
さぶいですか、そーですか。
学生時代、年末年始はバイトに明け暮れていた。むろん数ヶ月後に払うための授業料を稼ぐためである。当時は今ほど労働時間に規制がなかった。そのため働こうと思えばいくらでも働くことができたのだ。
普段でも12時間くらい働くのは当たり前だったが、年末年始の時期だと「正月手当」がつく。加えて大学の授業はないから働きホーダイ。雇用する側も大歓迎で「え?働きたいの?いいよ、どんどん働いてよ!」てな感じ。だからトラックのハンドルを握り続けて1日に17時間なんて珍しくなかった。
とはいえ所詮はバイト。配車係から与えられるトラックは毎回オンボロばかり。そこそこの規模の運送会社であれば大抵「運行前点検」をする。運転前にトラックの外観、タイヤの空気圧、エンジン・オイルの量、ラジエータの水などを確認するのだ。
各項目をちゃんと点検しないと配車係から大目玉を食らう。いや、運行前点検は配車係に怒られるからやるというより、自分の命に関わることなのでやらないわけにはいかない。何せ与えられるトラックの総走行距離は60万kmとか70万kmなのだ。トラックでいえばロートルもいいとこ。
そんなオンボロでも近場をノロノロ走るのなら問題はない。ところが高速に乗って往復500kmも走るのだ。場合によっては1,000kmもジャーニーしなければならない。最近のトラックは知らないが、当時のトラックなんてエンジン・オイルの消費がハンパでなかった。運行前点検の時に規定の量のオイルを入れても、ひとまわりしてくればオイル・ゲージに付かないほどオイルは消費したのである。もしオイルの量を確認しないまま旅立ったら、運が悪ければ途中でエンジンが焼き付き、高速道路上で文字通り「死の旅」に行くことになる。運行前点検を欠かさなかったのはそのためだ。
笑っちゃうのは当時運転中ワシの脳みそのなかで鳴っていたのが《巡礼の年》だったこと。これはリストのピアノ曲集なのだが、なぜ《巡礼の年》なのかは覚えていない。オンボロのトラックなのでエアコンはおろかカーラジオも機能しない。そんななかでこの曲集のなかの《泉のほとりで》とか《オーベルマンの谷》、さらには《ダンテを読んで》が頻繁に「流れて」いた。さすがに《葬送行進曲》が鳴りだした時にはアセッたけどね。死出の旅かよ!…と。
睡魔と闘いながら、よくもまあ走り続けたものだと思う。さすがに今はそんな労働をしていないが、相変わらず正月はない。特に今年は。詳しくは言えないが変更の可能性のある原稿待ちなので遠出できないというわけだ。高速に乗らないのに「拘束」とは、これいかに。
さぶいですか、そーですか。