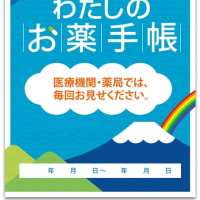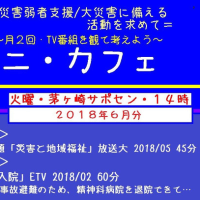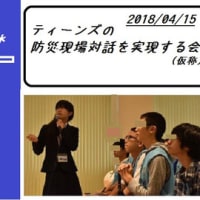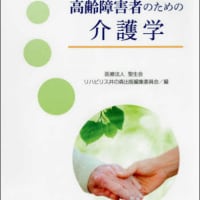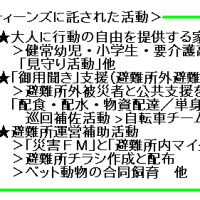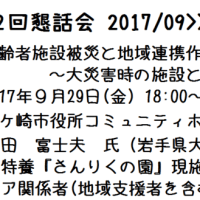2020/03/26 記
--------------
母が頻繁に深夜に起きてくる。頻尿というには尿意がない。まだ起きているのかと、読み上げ機械読書の中断となる。この気分の高まりは反動を生み、母の昼間の眠気を引き起こす。母のこの状態は春先・秋口に現れることがやっとわかってきたが、分かったといって対策のとりようがない。はじまったなあと思いつつ、カモミールの温湯を与え寝室に帰らせる。じんわりとした疲労感が溜まって、昨夜は夜間傾聴を中止した。ブログ構成の集中力が低下し昨夜は頓挫してしまった。申し訳ない。
昨日読んでいたのは、懇話会直結の本ではない。社会活動をする者が常に抱える思いを 取り上げた書だ。そのうち紹介を書くだろう。
>>これです。
●「「助けて」が言えない SOSを出さない人に支援者は何ができるか」松本俊彦 (編)2019/07
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535563797
-----------
石巻から郵便物あり、「まち・コミ」の宮定章さんからだった。「NPO法人 まち・コミュニケーション」の紹介と資金協力依頼の内容だった。しかし私は、都市計画を実現するという立て方自身に空疎な構造を見てしまう。今が消えている。当事者が抱えている困難や情念つの解決するという内側からの眼にこだわりたい。そのボトムアップ的な活動は鳥瞰するまなざしを必要としないということではない。まず「今・ここ」から始まることにこだわりたいのだ。宮定さん、ごめんなさい。
また浦川の「べてるの家」から商品カタログが届いた。宮定さんの郵便物もそうだが、こうした社会活動連絡が今、なんとなく親しみを感じるのは、コロナ・ウィルスのパニックで集会・イベントが封じられているからだろう。
しかし思うのだ。感染症災害の中では、私たちは専門家集団の迷える子羊のとして操作されるだけでいいのだろうか。私からは、潜在感染弱者が、そして子ども・家族の危うさが見え、社会対策の常として弱者対策の遅れが予測される。しかしその自覚を萎えさせるのが、感染対策には専門知識が必要で、感染者への接触は危険という化け物化した特殊性だ。
本当に私たちは何もできないのか。私たちは消費社会の消費者という共同のつながりを覆い隠すアトム化したシステムの中に覆われている。わが身のことはその中でも見える部分がある。しかし感染弱者への思い、これは私たちのエンパシー(相手の立場になって感じ取れる想像性)が、むき出しの形で問われている。他人ごとではないという気づきが問われている。
局面を創造しよう。やれることはあるはずだ。慈善運動のなかに潜む虚妄を超えていくような身動き、そう「身動き」から考えていきたい。
戦時中の国防婦人会のような落とし穴はある。だから世間や国の危機を持ち出すまい。個別性・当事者性にこだわるのは、全体の危機のなかに為政者利益を潜ませたり、医療という専門性の統制に封じ込める動きに飲み込まれない意味も含んでいる。まずは「局面の想像」と「身動き」だ。
-----------
明日は「練馬・産業プラザ」の緊急集会「公的住宅での困窮死・孤立死をなくすために」に出かける。
-----------------
東京の商店会が昨年の19号台風の被害を契機にして、公的設備の拡充計画として、増設照明と防犯カメラ設置の分担金をやっと捻出して先日納めてきたのだが、設置完了の現場確認が必要という連絡がきた。明日、間に合えばいいが無理そうだ。監視国家をつくるみたいでいやだが、監視カメラ映像の集中管理だけは拒否したが。
夜間傾聴:なし
(校正1回目済み)