吉本ばなな、今は「よしもとばなな」と書くやうだが、彼女の作品はあまり讀んだことがない。讀みたいかと訊かれて、「どうしても」と言ふほどの作家ではないが、現代人の心の掬ひ方としてはかういふものもあつてよいだらう、かういふ言葉で救はれる人もゐるだらうといふ思ひはある。決して嫌ひな作家ではない。言葉遣ひはいい加減であるし、今囘讀んだ小説も、斷章の積み重ねといふ印象もあつて、決して讀み易いものではないが、切なさを傳へる筆遣ひは、決して嫌な感じはしなかつた。『哀しい予感』を讀んだ感想である。
しかし、その「哀しさ」の正體や、それが「予感」として題されるについては、説明が結構むづかしい。そして、主人公の書き方について言へば、彼女が自分の氣持をいつも言葉で整理し、きちんと把握していかうとするのである。文體の輕みとは裏腹に、理屈つぽいといふ感じがして、發見であつた。作者自身、結構理屈つぽいのかもしれない。
以下は、その感想。
幼い頃の交通事故で両親と共に過去の記憶を失った主人公の「私」は、不思議な能力を持っていた。ある日、彼女は他人になって赤ん坊を殺す夢を見る。母親にそのことを話すと、かつてその家で起きた事件なのだと知らされた。果たして、こんな夢を見る人の心はどうなっているのだろう。もしかしたら、赤ん坊とは「私」自身なのかもしれない。
過去の記憶がないということは、今の自分を支えるものがないということである。だから、「私は自分がどうしてこんなに淋しがり屋なのか、きちんと考えたことはなかったが、夜一人でいると、時折ものすごい、郷愁としかいいようのない淋しさにかられることがあった」と書かれていたが、これは率直な感想だろう。
ところで、一般に「予感」とは未来に向かって使われる言葉であるが、この小説では過去に対して使われているようだ。作者は「私」以外の人物(実姉の恋人)にもこう言わせている。「僕の中には、もう自分すら忘れてしまった何年間かが眠っている」。そして、その時間は「永遠に誰とも分かち合えない」というのである。つまり、ここでも「予感」として暗示されているのは、哀しい過去なのである。
では、今の「私」はどう自分の人生を考えているのだろうか。こう書かれている。「心細いが、もう前へ進むほかない」と。しかしながら、その「心細さ」は前へ進めば解消されるようなものかと言えば、そうでもない。サーカスで、綱渡りを強いられた者がただその仕事を果たしているようなものなのであって、落ちないこと、絶望しないこと、それだけが生きる指針なのである。どうしてこうなってしまったのか、その理由を自問自答したとしても、「私」の心に浮かんでくるのは、やはり過去への「哀しい予感」に違いない。
小説は、事故現場に登場人物たちを集めて終わるが、それで何かが解決した訳ではない。「私」の空虚は晴れることもない。生きることを確認するばかりである。
| 哀しい予感 価格:¥ 420(税込) 発売日:1991-09 |




















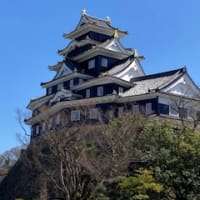








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます