カズイスチカと聞いて何のことかが分かれば、かなりの文学通である。もちろん、国文学出身者でこの名を知らなければモグリでもある。その程度には知られてゐるべき単語である。
森鷗外の短編小説だ。新潮文庫にも入つてゐる(『山椒大夫・高瀬舟』)。
casuisticaラテン語で「患者についての臨床記録」といふ意味らしい。花房といふ名の医者が、診察した人々について記した随筆といふしつらへである。
では、何が面白いかと言へば、花房といふ男の父も医者であり、その父の診察=生き方の迷ひの無さに打ちのめされてゐるところである。さながら息子花房は、患者や父を描きながら、自らの迷ひ(病と言つてもよいかもしれない)を記録してゐるかのやうである。
翁は病人を見ている間は、全幅の精神を以(もっ)て病人を見ている。そしてその病人が軽かろうが重かろうが、鼻風だろうが必死の病だろうが、同じ態度でこれに対している。盆栽を翫(もてあそ)んでいる時もその通りである。茶を啜(すす)っている時もその通りである。
花房学士は何かしたい事若(もし)くはする筈(はず)の事があって、それをせずに姑(しばら)く病人を見ているという心持である。それだから、同じ病人を見ても、平凡な病だとつまらなく思う。(青空文庫より転載)
父と子の生き方のかうした違ひはいづこから生じるのか。そのことについて鷗外が結論を出してゐるわけではもちろんない。山崎正和の『鷗外・闘ふ家長』を読めば、鷗外の生き方は「翁」に近いとも感じるが、しかし、もしそれ一辺倒の人物なら息子花房が登場することもないだらうし、しかもその男をもう一人の主人公にして描くはずもない。相反する二人を描くことで、警戒すべき無気力の訪れを絶えず意識してゐたといふことなのではないか、さう感じる。
卑近な例で言へば、警戒すべき感情に引き裂かれてゐるのが私にとつては夏休みである。夏休みは、退屈と焦燥とに引き裂かれた気分が波のやうに寄せて来る。苦手な季節である。
そのことの辛さに比べれば、外的な気温の暑さなど何と言うこともない。水を浴びれば消えてしまふ。
受験勉強の戦ひも、恐らくさういふところにあると思ふ。「何かしたい事若(もし)くはする筈(はず)の事」を置き去りにしたまま「それをせずに姑(しばら)く」勉強をしてゐる、かういふ無聊(ぶりょう)が辛いのである。目的が明確になることの救ひは、そこにある。



















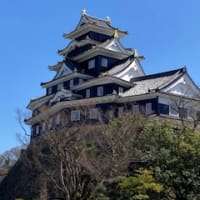








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます