タイトルの両義性が面白い。その人は「すぐそば」に存在してゐるのに、はるか「彼方」にゐるやうに感じる。それは逆にはるか「彼方」にゐるやうに思つてゐたのに、実はすぐ「そば」に存在してゐたといふことにも通じてゐるのかもしれない。
この小説の主人公は、まさに周囲にさう感じて生きてきた存在であつた。しかし、果たして周囲の人からはどう見られてゐたのだらうか。いまこの文章を書きながらそんなことを感じてゐる。主人公は、次期総理大臣を目指す政界の大物の次男として生まれ、経済的には何不自由なく暮らしてゐた。その立場でしか分からない苦労はあるのだらうが、お坊つちやま君のやうにも感じてしまふ。主人公視点で書かれてゐる小説だから、すぐ「そば」にゐながら「彼方」にゐるやうに感じる周囲の人の印象は、主人公から見た存在感である。しかし、俯瞰(周囲の人からの視点)的に見れば、いつも現実から逃げてばかりゐるわがままな人といふやうに見られてゐたのではないか。「すぐそばの彼方とは、あなたのことよ」と周囲の女性たちから言はれてゐるやうにさへ感じた。主人公視線で描きながら、読者にはむしろ逆に周囲の人から見た主人公の姿を印象的に記憶させるといふこの作家の描き方は、それが意図的なのか無自覚なのかは分からないが見事である。
「薫(註 事件を起こして苦しんでゐた時代の主人公を支へてゐた女性)はあんなにもすぐそばにいてくれたのに、自分の心はこんなにも彼方に離れてしまっている。すぐそばにある最も大切なものほどいつも遠い彼方にあるのかもしれず、遠い彼方にある最も大切なものほど本当はすぐそばにあるのかもしれない」
小説の最後のところで主人公が「とりとめなく考えた」ことである。ここだけ読んでも、「いい気なものだな」と思へて来ないだらうか。少なくとも私にはさう読めた。恵まれた人間の成長は、これほどに難しいのかと思つたのである。
ところで、主人公は政治家の息子なので、政治の話題が多い。経済の話が多い白石氏の小説としては珍しいのかもしれない(今まで読んだなかでは初めて)。政治についての作家の考へが興味深かつた。
「理想世界はこの世では決して実現し得ないと確信しておる。であるならば、政治家の唯一の役割は、自分の生まれ育った国家国土国民をその国家国土国民らしく保つことなのだ。日本は日本らしく生きねばならぬ。日本人は日本人らしく生きねばならない。また、そうする以外にこの国もこの国の民も生き延びていく道はないのだ。」
多様性礼賛の時代にあつて、かういふことが小説にまともに書かれてゐることがとても気持ち良い。これが主人公の父親である龍三の言葉である。それに対して、主人公龍彦はかういふ考への持主である。
「いつの時代にも国民が政治に批判的な無関心を示すのは、政治家という職業自体への侮蔑があるからだと龍彦(註 主人公)は思っている。政治などに首を突っ込もうと考える人間そのものが多くの人々は嫌いなのだ。それはさながら宗教者に対して大多数の人間が持つ違和感と似ている。龍三(註 主人公の父親)は人間の合成こそが政治であり、そこにのみ人の世の奇跡があるとさきほど語っていたが、しかし、人間は公共という名の下、あるいは真理という概念の下に個々人ではなく集合として取り扱われることが根本的に不愉快なのだ。」
2022年の現状を思へば、やはり龍彦の言に国民感情は近いのであらう。「日本人らしく」、「公共」を意識して生きる、「真理」を求めて生きることは忌避されてゐる。まさにそこには「どこの国民でもない、私を意識し、無節操に生きる」人だけがゐるのであり、隣にゐる人もまた「すぐそばの彼方」にしか感じられないといふことである。
最後に、この小説の書き方について。ある人物についてほとんど説明なくその人が現れる。そして、その人物と主人公との関係が次に書かれていくといふスタイルである。この作家の描き方であるのかもしれないが、最初は戸惑ひがあつた。言つてよければ読みにくかつた。が、しだいにぐんぐん話に引き込まれていき、大きな世界に連れて行つてくれた。
やはり白石一文はいいと思つた。




















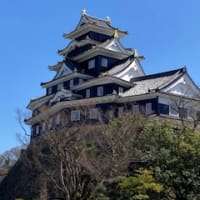








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます