知り合ひのFacebookのタイムラインでこの本が紹介されてゐたので読んでみた。新潮文庫の新版で字も大きく160頁足らずの本であるが、正直すらすらと読めるものではなかつた。
少年が初恋を抱いた年上の少女に裏切られたことから始まる漂泊の人生に共感が抱けぬままに、それでも読み続けたといつた感想である。
しかし、この少年クヌルプが聖書を頼りに自分の生き方を尋ね歩く生き方は、『デミアン』や『車輪の下』に通じるもので、さういふ言葉に出会ふと上質なヨーロッパ人の生き方を感じることができた。
「だが、ね、仕立屋さん、きみは聖書に注文をつけすぎるよ。何が真実であるか、いったい人生ってものはどういうふうにできているか。そういうことはめいめい自分で考えだすほかはないんだ。本から学ぶことはできない。これが僕の意見だ。聖書は古い。昔の人は、今日の人がよく知っていることをいろいろとまだしらなかったのだ。だが、だからこそ聖書には美しいこと、りっぱなことがたくさん書いてある。ほんとのことだってじつにたくさんある。」
さう悟つたかに見えるクヌルプだが、そんなことはない。人生をどんなに美しく生きたとしてもそれは誰かと共有できるわけではない。死んでしまへばそれで終はりだと考へるクヌルプにたいして、時にこんな言葉を投げかけられる時もある。
「それはおもしろくない話だね、クヌルプ。人生には結局意味がなければらない。だれかが、悪い人でなく、敵意を持たず、やさしく親切であったとすれば、それで値打ちがあるということを、ぼくたちはたびたび話しあったじゃないか。だが、いまきみの言ったとおりだとすれば、何もかももともと同じことになる。盗みをしたって人を殺したって同じようにいいことになる。」
クヌルプは考へる。悩んでゐると言つた方が正確かもしれない。しばらく経つた場面で、こんな言葉が記されてゐる。
「人間はめいめい自分の魂を持っている。それをほかの魂とまぜることはできない。ふたりの人間は寄りあい、互いに話しあい、寄り添いあっていることはできる。しかし、彼らの魂は花のようにそれぞれその場所に根をおろしている。どの魂もほかの魂のところに行くことはできない。行くのには根から離れなければならない。それこそできない相談だ。花は互いにいっしょになりたいから、においと種を送り出す。しかし、種がしかるべき所に行くようにするために、花は何をすることもできない。それは風のすることだ。風は好きなように、好きなところに、こちらに吹き、あちらに吹きする。」
風とは何か。それについてクヌルプは答へてゐない。魂の孤独を記すばかりである。
第三部は、「最期」と名付けられてゐる(一部は「早春」、二部は「クヌルプの思い出」である)。雪降る街に疲れ果ててクヌルプは眠つてしまふ。神との対話に安堵してゐるかのやうである。神の言葉が記されてゐる。
「わたしが必要としたのは、あるがままのおまえにほかならないのだ。わたしの名においておまえはさすらった。そして定住している人々のもとに、少しばかり自由へのせつないあこがれを繰り返し持ちこまねばならなかった。わたしの名においておまえは愚かなまねをし、ひとに笑われた。だが、わたし自身がおまえの中で笑われ、愛されたのだ。おまえはほんとにわたしの子ども、わたしの兄弟、わたしの一片なのだ。わたしがおまえといっしょに体験しなかったようなものは何ひとつ、おまえは味わいもしなければ、苦しみもしなかったのだ。」
かういふ境地は、もちろん孤独ではないのだらう。ただ、その感じも味はひも「風」がない限り知らせることも受け取ることもできない。ヘッセは、この小説を書き、それに「風」の役割を持たせた。クヌルプといふ人を私たちは知ることができたのはその小説のおかげである。
神と私。その単独者同士の対話がキリスト教の真髄である。しかし、それが同じく隣の人とも対話を可能とする、いやすべきであるといふことの知らせのために文学がある。この小説の優しい印象は、静かにそれを伝へてくれた。冒頭に記した「上質」とはさういふことだらうと思つてゐる。




















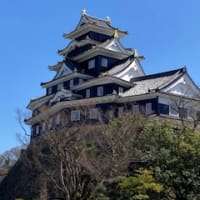









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます