前回、長々と金田一京助の文章を引用したが、「知識人」特有の、その持つてまはつた言ひ方を見て欲しかつたからである。「言語の歴史性へと観入させる」ことが、自分一人の國語學でできると思ふ傲慢ぶりもさることながら、自分だけが「言語の大綱」を知り、「規範意識」に「囚われ」てゐないと考へてゐる無知加減には呆れてものが言へない。學者が學者であるためには、自分がその専門分野について何を知らないかといふことを知つてゐなければならないはずだ。知つてゐるからこそ、學問全體のなかでの自身の研究内容の位置づけができ、新しい研究テーマを發見することができるのではないか。それを「言語の大綱」を知つてゐるのであれば、後世の学者は何もしなくて良いといふことになる。恐れ入る。
しかしながら、もちろん「言語の大綱」など知つてゐるはずがない。ましてや、その誤解に基づいて、現在の國語のあり方を云々するのはもつてのほかである。
「言語の永遠の變化」は數百年の單位で訪れるものなのであつて、己れ一人のわづかの知見と一世代にも及ばない數十年といふ短い時間の流れとによつては、言語の變化を起こさせてはならないとするのが、正統な國語學の立場である。
音韻が曖昧、不安定であれば、表記で私たちの國語の傳統を守る労をとらなければならない、それが國語にたいする正しい姿勢である。福田恆存の姿勢とは、まさにそれである。
「依然としてかな文字は私たちの不安定な音韻を表記するのに最もふさはしい文字であり、歴史的かなづかひはさういふ國語音韻の生理に最も適合した表記法であると言へます。つまり、歴史的かなづかひが表音的でないことに不平をもらすまへに、人々はまづかな文字が表音に適さぬことに不平を言ふべきであり、さらに溯つて、國語音韻そのものが表音を拒否してゐることに著目すべきであります」
まつたくこの通りである。かなは發音記號でないのだから、表音的でないことに目くじらを立てても詮無いことである。それに、そもそも文字とはどの言語でも發音記號ではない。不平を持つ學者たちが手本とした歐米の言語でさへ、發音記號ではない。そして、一見表音文字のやうに思はれる隣國韓國のハングル文字も、陽陰を中心としてきはめて整理された表記の體系をもつてゐるが、發音記號ではない。
文字は、文字で獨立した體系をもつてゐる。それで良いではないか。ちなみに手元にある『新編国語要説』(鈴木真喜男・長尾勇著、学芸図書)といふテキストには、かうある。
「音声は生理的現象であり、表象は心理的現象であって、本来、本質的には、まったく異なる次元に属する。この二つの現象が発生的には恣意的に連合したところに言語の成立があり、かつ、この点に言語の本質がある」
「恣意的に連合」といふところは、いささか氣になるが、音と文字との關係については、正確に捉へた指摘である。



















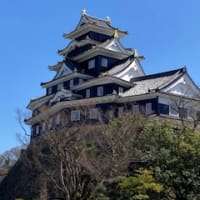









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます