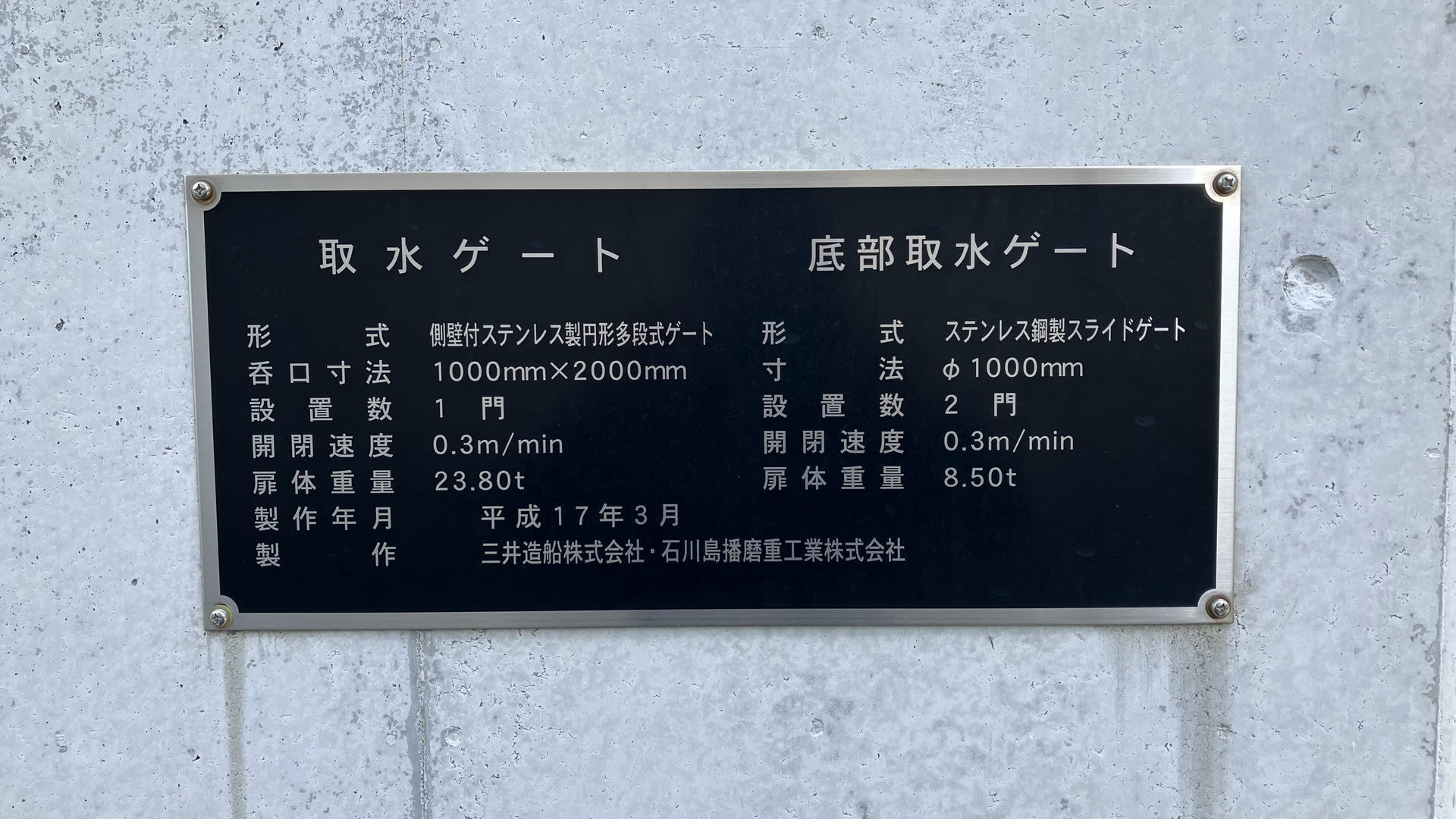どーも、ワシです。今回は岡山県久米郡久米南町南庄(くめなんちょう みなみしょう)にある旭川(あさひがわ)水系誕生寺川の夫入道池(ぶにゅうどういけ)を目指します。アクセスは前回記事にした水越池のすぐ下を通る道を進んでいくと到着します。ただし、この道はとても細いので要注意。
対向車が来ないことを祈りつつ進んでいくと無事到着。これが左岸から見た、いわゆるダム上になります。

下流側の斜面の様子。

池側から見るとこんな感じ。

ダム上を進んでみます。中央のガードレールの隙間には「地蔵菩薩」と記された石碑が…。

そこから池を眺めます。

一方、下流方向の遠景。

右岸側には洪水吐があります。一応越流式のようです。

洪水吐の上に架かる橋の名は「夫入道池橋」で、昭和57年(1982年)3月竣工だそうです。


洪水吐から溢れ出た水は、この水路を通ってあちらへ流れていきます。

右岸、池側から見た洪水吐の様子。

そして、左岸側を見るとこんな感じ。

右岸、下流側から改めて堤の傾斜を眺めます。こう見ると、やはり高さがあるなあと思ったり…。

ここが夫入道池であるのは間違いないんですが、諸元を示すものは見当たりません。そこでダム便覧を見ると、夫入道池は1900年に着工し、1919年に竣工した高さ=15.0m、長さ=67.0mのアースダムとあります(参考)。しかし、池名の由来は記されていません。ネットを検索しても由来についてはわからずじまい。うーん、気になります。
次回、岡山県に行った際に近所の人にでも聞こうかしらん。
対向車が来ないことを祈りつつ進んでいくと無事到着。これが左岸から見た、いわゆるダム上になります。

下流側の斜面の様子。

池側から見るとこんな感じ。

ダム上を進んでみます。中央のガードレールの隙間には「地蔵菩薩」と記された石碑が…。

そこから池を眺めます。

一方、下流方向の遠景。

右岸側には洪水吐があります。一応越流式のようです。

洪水吐の上に架かる橋の名は「夫入道池橋」で、昭和57年(1982年)3月竣工だそうです。


洪水吐から溢れ出た水は、この水路を通ってあちらへ流れていきます。

右岸、池側から見た洪水吐の様子。

そして、左岸側を見るとこんな感じ。

右岸、下流側から改めて堤の傾斜を眺めます。こう見ると、やはり高さがあるなあと思ったり…。

ここが夫入道池であるのは間違いないんですが、諸元を示すものは見当たりません。そこでダム便覧を見ると、夫入道池は1900年に着工し、1919年に竣工した高さ=15.0m、長さ=67.0mのアースダムとあります(参考)。しかし、池名の由来は記されていません。ネットを検索しても由来についてはわからずじまい。うーん、気になります。
次回、岡山県に行った際に近所の人にでも聞こうかしらん。