先日、上京する機会があつた。
約束の時間まで一時間ほどあつたので、神保町に行つてみた。古書店を回る時間はなかつたので、三省堂書店に入つた。今ではさほど大きな書店とは思はないが、学生時代に上京すると訪れたのが、ここと新宿の紀伊國屋だつた。神保町は古書店や岩波映画やこの三省堂、東京堂、書泉グランデなど一日楽しめる街である。今は古書はネットで購入することが多いが、それでも久しぶりに訪れた大型書店は格別であつた。
品揃へはもはやどんな書店もアマゾンにはかなふまい。しかしアマゾンの死角は、本の即物的な情報がないことである。ページ数も書いてはあるが重さは分からない。大きさも寸法だけでは実感されない。紙の質も結構大事で、活字の種類も重要な要素であるが、実物を見ないと分からない。村上春樹の『海辺のカフカ』の紙質は、私の読書史上最高である。それ以前は『福田恆存全集』であつたが、勝るとも劣らない。嫌ひな活字は講談社文庫。あれはひどい。センスを疑ふ。あの活字のせいで読者をずゐぶん失つてゐると思ふ。
閑話休題。それで、その三省堂書店であるが、四階だつたか社会科学系のフロアでは、東京大学出版会と白水社とみすず書房の共催によるブックフェアをやつてゐた。言はずと知れた高額書の出版社である。決して売れる本ばかりではないが、読書かなら何冊かは所有してゐるであらう。私の趣味としてはみすず書房がいちばん合ふ。最近新版が出た『アメリカンマインドの終焉』は学生時代の宝物であつたが、所有欲だけを満たしてゐたものであつたのを二年前にやうやく読了した。それから、昨年の東京大学の入試に出た『アメリカの反知性主義』もみすず書房である。メルロポンティもロランバルトも、みすずである。バーリンの自由論もさうだ。いろいろとお世話になつた。しかし、かういふ本は田舎の書店にはない。名古屋の書店に行つても並んでゐるだけで、今の問題意識を主題にしてコーナーを作るといふ演出はない。大阪でも見たことはない。
しかし、三省堂書店ではさりげなく、これ見よがしといふのではなく、面白さうな三社の本を並べてあつた。効率よく売るといふ点では非常に無駄なスペースであらう。しかし、かういふ並べ方に相応しい本が、その三社からは出てゐるのである。

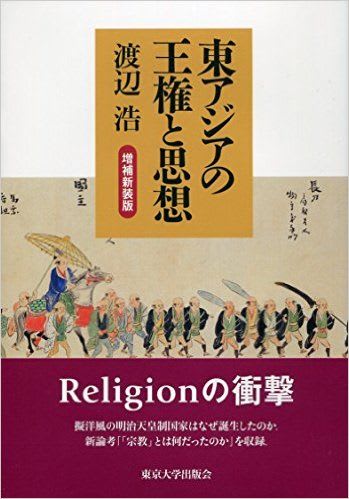


かういふ本を買ふか買はないか、三時間ほどかけて吟味してお財布と相談して一冊だけ買つて帰る。しかもその本はすぐには読まない。それが私の書店巡りの習慣である。書店ではぐるぐる動いてゐる好奇心や読書欲が家に帰ると冷えてしまふ。しかし、時が来るとその本の価値が現れてくる。さういふ経験が自分のこの実に非力な読書習慣を肯定してくれてゐるやうである。
それにしても、やはり東京はいいなと思ふ。生活するときつと疲れてしまふだらうが、たまにはいいものである。





















