 高知城には8年前に行った。現存12天守閣のうち一つ。当時は、写真とかで記録したわけではないが、たまたま半月前に行った宇和島城の天守閣内に全国の「名城の写真」が掲示されていて、それを撮影。高知城は1603年に城造りのスペシャリストである藤堂高虎の設計で築城されたが、1727年の大火で類焼。1753年に再建されたものだ。それなので、戦国時代と江戸時代の思想が混じり合っているそうだ。たしかに、宇和島や、備中松山のような戦闘用の緊迫感は強くは感じない。個人的には、かなり点数は高い。
高知城には8年前に行った。現存12天守閣のうち一つ。当時は、写真とかで記録したわけではないが、たまたま半月前に行った宇和島城の天守閣内に全国の「名城の写真」が掲示されていて、それを撮影。高知城は1603年に城造りのスペシャリストである藤堂高虎の設計で築城されたが、1727年の大火で類焼。1753年に再建されたものだ。それなので、戦国時代と江戸時代の思想が混じり合っているそうだ。たしかに、宇和島や、備中松山のような戦闘用の緊迫感は強くは感じない。個人的には、かなり点数は高い。8年前のことなので、城の話をするほどは覚えていないので、高知の寿司の話にうつる。東京からの出張だったのだが、夕方の飛行機で高知着、市内に泊まり、翌日の午前中に所用をすませ、午後に市内をちょっと拝見し、夕方の飛行機で帰ってくる。部下の社員と二人の出張なので、まあ、夕食は地元の魚でも食べて・・という了見で高知のことをうっすらと知っている人に店を聞くと、「おらんく家」を教わった。「ネタ」が大きいので有名ということらしい。帯屋町(おびやまち)というところにある。いたってアバウト情報だ。
そして空港からバスで市内に入り、ホテルにチェックインしてから「はりまや橋」を見て、がっかりしてから帯屋町に行くのだが、要するにアーケード街で、端から端まで遠くかつ立体的に店舗が展開しているので、困ってしまった。10分程うろうろして、手がかりを得られぬまま、意を決し、ある建物へ向う。
意を決して向ったのは、実は、「交番」。普通、寿司屋の捜索に警察に行く人はいないだろう。が、「ネタが大きい」というのは「魔法のコトバ」だ。おそるおそる、体の大きい警官に道聞きをする。東京からやってきて、地元に不案内なこと、どうしても行きたいのだが場所がわからないこと、本当は警察に頼むようなものではないことを先に言ってから、「おらんく家」と言うと、一瞬にして破顔爆笑された。「ネタの”太い”店じゃがな。あしも連れていっちょくれ。」とのこと。そうか、ネタが「太い」というのか・・・
で店内は、活気にあふれ、ネタは東京感覚の2~3倍。自分の財布か、お店の財布かどちらかが心配になってしまう。そして、一抹の経済的心配を持ちながら、満足な気持ちを最後にカツオで締めようと注文すると、「先ほどお連れの方が注文したのが最後」だったとのこと。何と言うことだろう。欲しいものは先に取れか・・・
ここから話は現代の東京に進む。
東京メトロ駅構内で配付しているフリーペーパー「メトロガイド」というのがある。その中のコラムに文化放送パーソナリティの”おまたまさこ”さんが書いているのだが、3月号「満腹物語」に紹介された話題で、カステラの厚切りの話があった。
どうも、こどもの世界ではカステラを厚く切るのを「太い」。薄く切るのを「細い」と言い出したらしい。おまたさんは、職業上ことばの感覚に鋭いので、将来、「厚い」が「太い」に取って代わられるのか、あるいは定着しないのかを考察され、結論として、厚いは厚いままだろうと推測している(というか、太いは嫌いだと言う)。例として、厚切りパンと太切りパン、厚焼きタマゴと太焼きタマゴ、厚着と太着、厚化粧と太化粧など考えれば、「太いでは気持ち悪いだろう」ということだそうだ。
私は逆に、「太い」は限定的に定着するのではないかと思っている。根拠としては、事実、高知には実在する用例であり、いわゆる流行語ではないこと。そして、限定的という意味だが、普通の状態の約2倍までは「厚い」で、2倍を超えた場合「太い」の領域に入るのではないかと思う。パンの標準が8枚切りとすると、4枚切りがちょうど「厚いと太いの境界線」かな。したがって普通の2倍以上の厚みの化粧をする場合は太化粧ということになるが、それなら実感が伴う。セーター1枚多く着るのは厚着だが、そのうえにコートとマフラーを付けると太着とか・・・
ところで、高知の「おらんく家」だが、「太い」を東京に送り込んだだけでなく、ネット上で調べると大阪北新地に支店を3軒も出店しているようだ。関東にも「はよーきとーせ」。















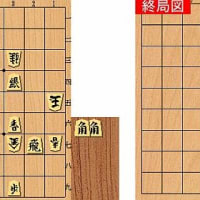


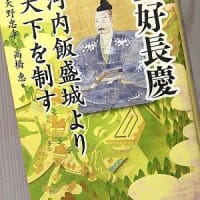

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます