小野小町(おののこまち)といえば世界三美女といわれ、小倉百人一首の「花の色は・・・」は百首の中でも有名度ベスト3に入るだろう。絶世の美女といわれ、百夜(ももよ)伝説というのは、小町に短歌で愛を百回伝えると本懐を遂げるというもので、実際には本懐ではなく呪い殺されるというようなものだったような気がする。

一方、そんなに有名であっても生没年も親子関係も、さらに存在すらも確証がない。小野小町作という短歌の多くは、そうではないと思われていて、紀貫之らが編んだ古今和歌集18首は紀貫之を信じるとして彼女の作ということになっている。
本作にあるように彼女が何かの機会に詠んだ歌が京都の市井に流布している間に少しずつ変化しているということだろうか。
ということで本作では小野小町は小野篁(おののたかむら)の娘ということになっている。一説では、(本作では篁の弟と言われる)篁の子の小野良実の子とも言われるが、篁と小町の推定年齢の差は25歳ぐらいなので孫としては近すぎるかな。
その当時の京都は藤原良房(北家の事実上の始祖)が謀略を持って朝廷を支配していく時代で、文化人は生きにくい時代だったようで、小野篁も世間から引き込みがちで、あちらの世界に通じている人間と恐れられていた。
そして、本作には当時の魅力的な人物が次々に登場している。
そして、意識的なのだろうが、著者の高樹のぶ子氏の文体が、まさに源氏物語風で、小説の語り手がめまぐるしく変わる。物語を語る第三者だったり、小町の心中のことばだったりだが、あまり気にならない。というのも、ほとんどの場面に小町がいるわけだからだろう。
数か月前に紫式部の史跡を京都で巡った時に、雲林院の近くにある紫式部の墓はすぐそばに小野篁の墓があり、どうして時代が100年も違うのに近接しているのかという疑問があった。一説では小野篁は地獄の使いとして思われていて(体も巨大)、紫式部は源氏物語の中で嘘をたくさんついたので地獄に送られたということが共通しているといわれているそうだ。小町の晩年は伝わっていない(小説では生誕地の秋田へ向かう途中、白河の関で亡くなったことになっている)。
著者はあとがきに、今に伝わる小野小町像は男性中心の視点なので、・・・というように小町の名誉回復といようことが書かれていたのだが、そもそも実像が明確に判らない人物の小説なのだから、あえてそういう方向性まで書かない方が良かったかもしれない。

一方、そんなに有名であっても生没年も親子関係も、さらに存在すらも確証がない。小野小町作という短歌の多くは、そうではないと思われていて、紀貫之らが編んだ古今和歌集18首は紀貫之を信じるとして彼女の作ということになっている。
本作にあるように彼女が何かの機会に詠んだ歌が京都の市井に流布している間に少しずつ変化しているということだろうか。
ということで本作では小野小町は小野篁(おののたかむら)の娘ということになっている。一説では、(本作では篁の弟と言われる)篁の子の小野良実の子とも言われるが、篁と小町の推定年齢の差は25歳ぐらいなので孫としては近すぎるかな。
その当時の京都は藤原良房(北家の事実上の始祖)が謀略を持って朝廷を支配していく時代で、文化人は生きにくい時代だったようで、小野篁も世間から引き込みがちで、あちらの世界に通じている人間と恐れられていた。
そして、本作には当時の魅力的な人物が次々に登場している。
そして、意識的なのだろうが、著者の高樹のぶ子氏の文体が、まさに源氏物語風で、小説の語り手がめまぐるしく変わる。物語を語る第三者だったり、小町の心中のことばだったりだが、あまり気にならない。というのも、ほとんどの場面に小町がいるわけだからだろう。
数か月前に紫式部の史跡を京都で巡った時に、雲林院の近くにある紫式部の墓はすぐそばに小野篁の墓があり、どうして時代が100年も違うのに近接しているのかという疑問があった。一説では小野篁は地獄の使いとして思われていて(体も巨大)、紫式部は源氏物語の中で嘘をたくさんついたので地獄に送られたということが共通しているといわれているそうだ。小町の晩年は伝わっていない(小説では生誕地の秋田へ向かう途中、白河の関で亡くなったことになっている)。
著者はあとがきに、今に伝わる小野小町像は男性中心の視点なので、・・・というように小町の名誉回復といようことが書かれていたのだが、そもそも実像が明確に判らない人物の小説なのだから、あえてそういう方向性まで書かない方が良かったかもしれない。












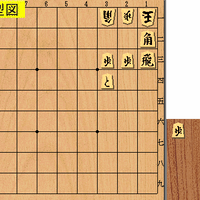







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます