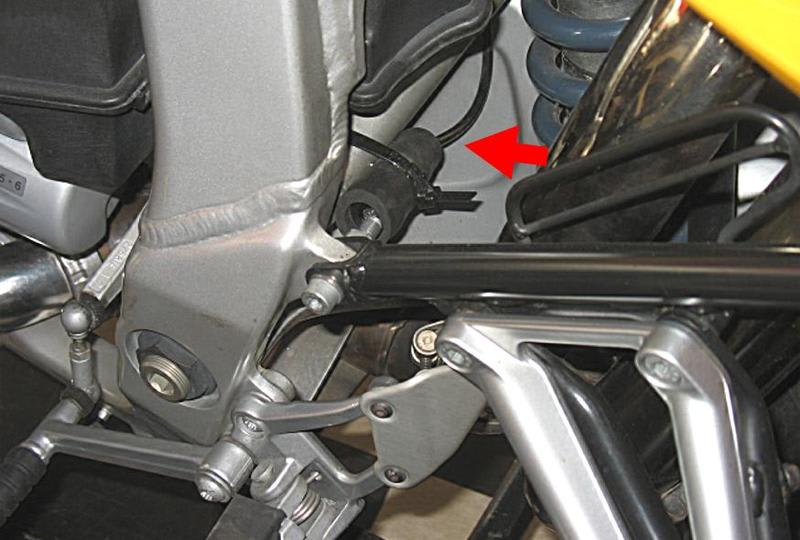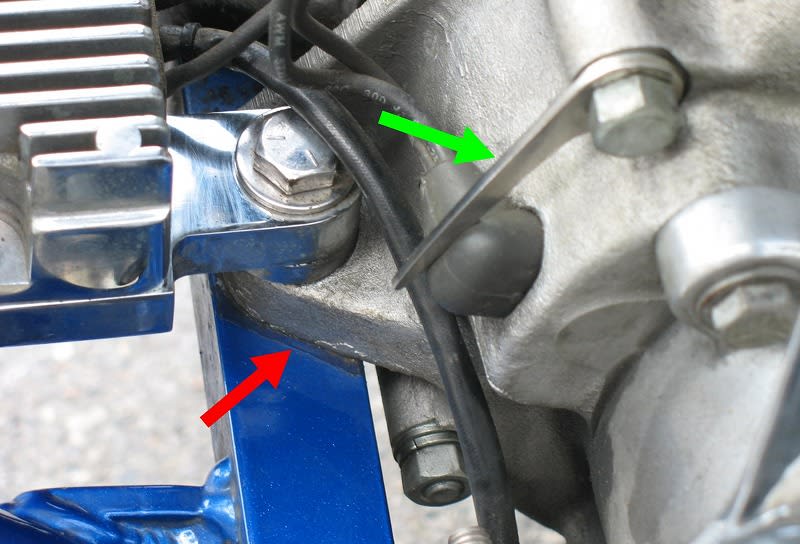人気blogランキングへ
一昨日の「ワールド ビジネス サテライト」でまだ販売前や試作段階のナビ システムが紹介されていました。
日本のナビ市場は世界一で、北欧とヨーロッパを合わせた販売台数340万台を凌ぐ360万台も売れているそうです。
電子製品の例に漏れず、成熟が進むと商品価値を高めるためには、付加価値としての機能を増やすことになってしまうのでしょうか。
パイオニアのナビはハンドルを握った手を通じて心拍数を感知し、ドライバーの眠気に警報をアナウンスしたり、眠気を払う音楽を流すというものです。
パナソニックのナビは最適のセグ放送を受信できるものです。
ハイブリッドのクルマは、”ピストンも”使っている電子製品ともいえるほどデジタルなシロモノですけれど、苦戦を強いられていると言われるレクサスブランドに投入されたGS450hも紹介されていました。
音と振動を隔離しなければならない高級車にハイブリッドはうってつけで、それにエコロジーも加われば・・・・・。
ハリヤーのハイブリッドに乗っている知人の証言では、ビックリするほど速いそうです。
ところでバイクの商品価値を高める機能ってなんでしょうか?
古きを訪ねると、事故の多さで自主規制しなければならなかったほどのハイパワーエンジン、軽量化と高剛性を果たしたアルミフレーム、その当時に多くのライダーを魅了したレーサーのレプリカスタイル、テイストを追求したと謳われた単気筒エンジン。
アレッこれは機能というより基本設計ですね。
付加価値的な機能というのは、ヘルメットの収納やメインスイッチ捻るとシートが開くとかぐらいですか。
日本のメーカーでパフォーマンスを数値化しないで開発に成功したのはヤマハSRくらいのもので、それも
ロードボンバーあってこそだと思います。さすがに数値を目標にして開発したバイクは立派なもので、ココでも何回か書きましたが、300km/hのパフォーマンスを百数十万円で手に入れられるのはイイ事なのか?
エンジンを使って地上をはしる乗り物として、バイクはクルマと最大に違う点は自立できないところにあり、乗り手が車体の一部として機能しバランスをとらなくてはならないので、小型・軽量は必然的ともいえます。
バランスが崩れたときに
1tもあるものを、足で支えるわけにもいきませんから。
そう考えると軽量も付加的な価値もあるわけですが、ハイパワーとバランスのとれた軽い車体は驚くほどの動力性能で、法定速度を維持すのに苦労するほどですね。
ここでハーレーダヴィッドソンの展開を考えてみると、その不変ともいえるスタンスは、日本のメーカーが四半世紀を掛け研ぎ澄ましたハイパフォーマンスのバイクを市場的に凌駕してしまいました。
今から考えると、日本のバイク市場は1970年代に成熟期に達してそのピークは80年代であり、その頃メーカーから新製品がリリースされる数は現在の携帯電話を凌ぐほどでありました。メーカーは出荷台数でも競い合い、その結果はありあまった在庫が叩き売られるという悲しい結末もあったのです。ワタシとしてはこういった経緯も克明に憶えているので「300kmが百数十万円」というのが素直に喜べない理由かもしれません。
ハーレーダヴィッドソンはこうした数値的なパフォーマンスと無縁で、もっと心情的なエモーショナルな部分を訴え続けて、幅広い年齢層に普遍的な広がりをみせて来ました。
つまり、かつて精密なトランジスターラジオで世界中を席巻したのと同じ手法で、壊れない高性能のバイクを提供し続け高水準の販売台数を維持するために、手を変え品を変える必要のあった日本のメーカーと対極のスタンスがあったのです。
バイクのパフォーマンスを語るときは絶対性能を基本データにしていたものが定義であったとすれば、ハーレーダビッドソンの”グッドヴァイブレーション”や”鼓動感”がその定義を変えてしまったまでの思いがあります。
バイクに魅入るエモーション(かきたてるもの)が超ハイスピードに対する憧れから、もっと日常的な快楽にとってかわられたのでしょう。
こうして考えると、バイクの基本的な性能に対する付加価値というものは、その地域における成熟度によって変化するのは当然であり、エコロジーの要求によっても然りです。前述のようにバイクの軽量小型は必然であったので、エンジンは空冷によるものがホトンドでありましたが、超ハイパワーでは水冷が必要になってきました。
ところがエコロジーの要求でも水冷が必須になってきており、もしかしたら空冷が付加価値の時代もすでに来ているのかもしれません。
つまりハナシがややこしくなりましたが、バイクの将来においては今までに持っていた機能や特性を維持できるかどうかが付加価値に・・・・・・?