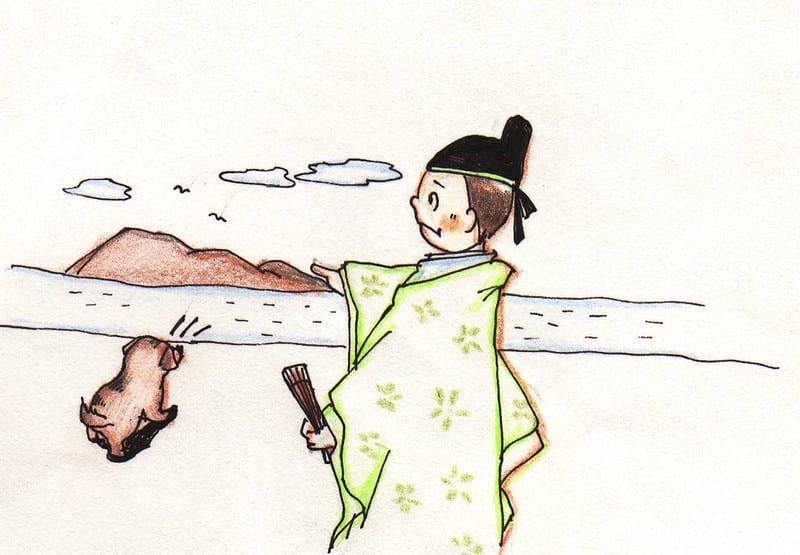平成18年「新野辺西部地区土地区画整理事業」は完成しました。
工事の完成に伴い「完工記念誌・緑はぐくむ街」が編集され、工事概要・かつての新野辺西部地区のようすがまとめられました。
その本の座談会で「土地区画整理組合」の副理事長の山口賢一さん(現:新野辺町内会長)は、次のように語っておられます。
緑の多い街に
 新野辺全体が住みよくて安心できて明るい街になっていけたらと思います。
新野辺全体が住みよくて安心できて明るい街になっていけたらと思います。
区画整理の地区について言えば、せっかくいろいろと整ってきましたので、あとは緑の多い潤いのある街にしていきたいなと思っています。
先程、Hさんもおっしゃいましたが子供の心のふるさとに成る街にしたいという思いがあります。
また、Kさんもおっしゃったように我々はここで育って、遊んできました。
それはどんな環境だったかというと、きれいなため池があって、畑があって、松林があってと今でも鮮明に残っています。
そういうものがこの整備した中で感じられるようにしたいと思います。
そのために公園の整備として、ため池が全くなくなったので、この公園の中に池を作って子供たちが水に親しむことが出来るような環境を今後努力して作りたいと思います。・・・
便利になりました
写真をご覧ください。赤い線で囲まれた地区が土地区画整理事業の対象になった地域です。
事業が行われる前のこの地区の風景です。
新野辺西部地区の風景は一変させました。
道幅は広くなり便利になりました。
ただ、新野辺の昔からの新野辺の中心地区の街づくりの課題が残っています。
*写真:事業前の新野辺西部地区(赤く囲まれた範囲が区画事業対象地区)
範囲右下の大きな建物が新野辺公会堂
*「完工記念誌・緑はぐくむ街」参照