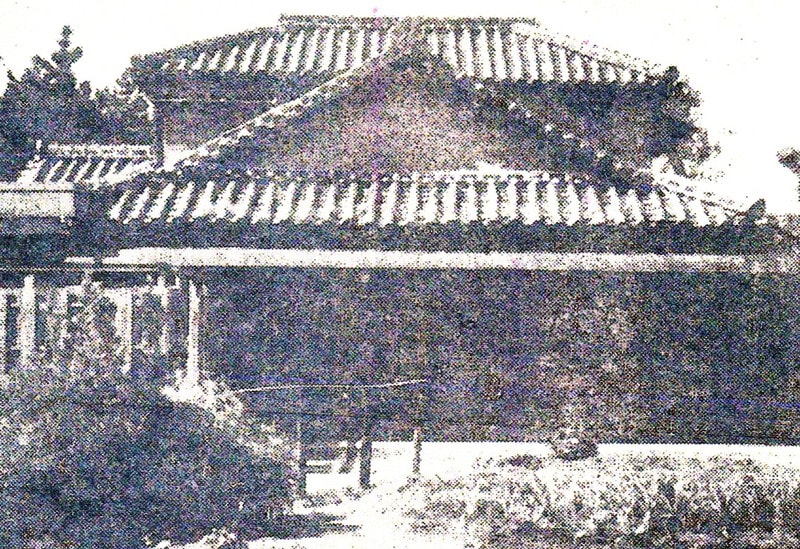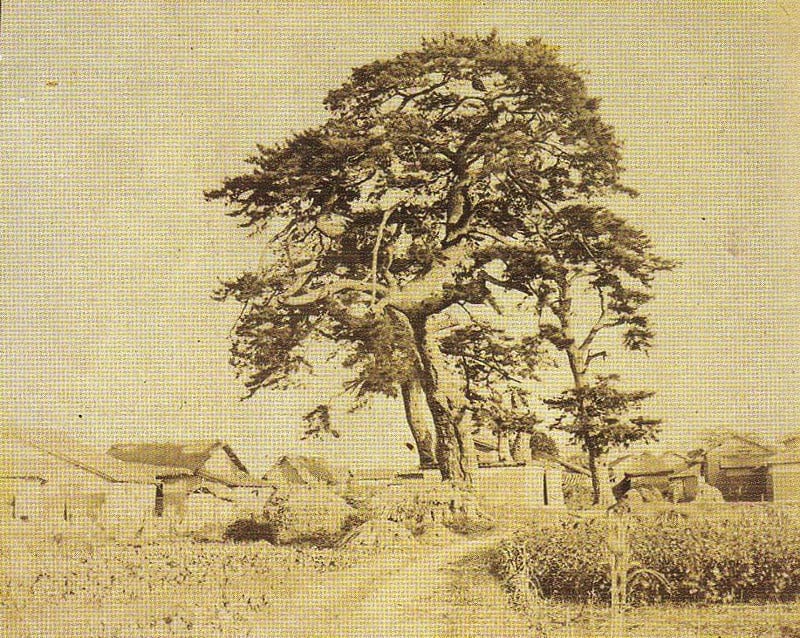仁寿山黌で育った勤王の志士たち
 寸翁がめざした仁寿山黌での教育は、漢学、国学、史学、医学が中心で、開放的な教育を、その基本に置いていた。
寸翁がめざした仁寿山黌での教育は、漢学、国学、史学、医学が中心で、開放的な教育を、その基本に置いていた。
(山崎)闇斎学派の合田麗沢、折衷学派の村田継儒らの外にも山黌を訪れ、門下生たちを教育した。
仁寿山黌に学んだ青年たちの中には、寸翁が意図するところをこえて勤王運動へ突き進んだ者もいた。
そのため、姫路藩に煙たがられた。
仁寿山黌は開校20年後の天保13年(1842)、財政難を理由として藩校・好古堂に吸収された。天保12年(1841)6月24日、寸翁が75歳で永眠した1年後のことで、まるで寸翁の死を待ちかねたかのような閉鎖のタイミングだった。
幕府譜代の姫路藩でも、功ある寸翁の存命中は、表立って仁寿山校に干渉できなかったのであろう。
河合屏山
尊王佐幕で日本中が揺れる幕末、姫路藩の尊王の志士達を指導した一人が河合屏山(かわいへいざん)である。
屏山は、三才で寸翁の養子となった。妻は寸翁の娘琴泉(きんせん)である。
姫路藩の藩主は、幕府の老中を勤めるなど、佐幕府のバリバリと思われており、そんな中で姫路藩の家老の屏山は尊王運動を指導した。
そのため、7年の間自宅謹慎になり身動きが取れなかった。
その間、姫路藩では、佐幕派と尊王派が激しく争った事件(甲子の獄)もあるが、屏山は謹慎中で、ほとんどダメージを受けなかった。
慶応三年の王政復古により歴史の流れは変わり、佐幕派が追われるようになった。
屏山は大活躍する場所ができた。
幕末の混乱の中で、会津藩とともに、佐幕派の中心であるとみられていたった姫路藩が、版籍奉還を進んで行うなど見事な手腕を発揮し、姫路藩がなんとか息をつないだのは、河合屏山の活躍に負うところが大きかった。
*写真:河合屏山の墓碑




















 水楼のあった場所を確認したい。
水楼のあった場所を確認したい。