大阪の仕事先のビルの前にナンキンハゼの街路樹があります。先日、打ち合わせの後、落葉を拾って撮影しました。先が尖った菱形の葉が特徴です。

(大阪・長堀通りのナンキンハゼ)
名前の通り中国から渡来した樹で、日本には自生しません。種子のロウ分から油を採取し、ローソクや石鹸、灯油、頭髪用の油などを生産するために、江戸時代から数多く植栽されました。
奈良のツリーウォッチングの会に参加したとき、「奈良公園にナンキンハゼが多いのは鹿が食べないからだ」と教えてもらいました。同じ理由でアセビが多いのは知っていましたが、ナンキンハゼのことは知りませんでした。確かに、お弁当を広げた場所にもナンキンハゼの幼木が点々とありました。

(奈良公園のナンキンハゼの幼木)
アセビは「馬酔木」と書くように有毒成分が含まれています。ナンキンハゼの白い実はポップコーンみたいで、鳥は食べますが、哺乳類には有害。奈良の鹿は本能的にそれを知っているのでしょう。

(フウの紅葉。葉が三つに分かれています。)
中国では、このナンキンハゼとフウ、マユミを三大紅葉樹と呼んでいます。カエデ類が入っていないのは、種類が少ないからでしょうか。
フウには中国では「楓」の文字を当てます。この漢字は日本では「カエデ」と読みますが、同じように紅葉が美しいのでどこかで混同されたのでしょう。

(マユミの紅葉)
マユミの紅葉の魅力は、少しピンクがかっているところでしょうか。昔、弓の材料にしたのでこの名があります。
なお、ハゼという名前がついていますが、日本でロウを採取するハゼノキはウルシ科、ナンキンハゼはトウダイグサ科で全く別の樹です。

(大阪・長堀通りのナンキンハゼ)
名前の通り中国から渡来した樹で、日本には自生しません。種子のロウ分から油を採取し、ローソクや石鹸、灯油、頭髪用の油などを生産するために、江戸時代から数多く植栽されました。
奈良のツリーウォッチングの会に参加したとき、「奈良公園にナンキンハゼが多いのは鹿が食べないからだ」と教えてもらいました。同じ理由でアセビが多いのは知っていましたが、ナンキンハゼのことは知りませんでした。確かに、お弁当を広げた場所にもナンキンハゼの幼木が点々とありました。

(奈良公園のナンキンハゼの幼木)
アセビは「馬酔木」と書くように有毒成分が含まれています。ナンキンハゼの白い実はポップコーンみたいで、鳥は食べますが、哺乳類には有害。奈良の鹿は本能的にそれを知っているのでしょう。

(フウの紅葉。葉が三つに分かれています。)
中国では、このナンキンハゼとフウ、マユミを三大紅葉樹と呼んでいます。カエデ類が入っていないのは、種類が少ないからでしょうか。
フウには中国では「楓」の文字を当てます。この漢字は日本では「カエデ」と読みますが、同じように紅葉が美しいのでどこかで混同されたのでしょう。

(マユミの紅葉)
マユミの紅葉の魅力は、少しピンクがかっているところでしょうか。昔、弓の材料にしたのでこの名があります。
なお、ハゼという名前がついていますが、日本でロウを採取するハゼノキはウルシ科、ナンキンハゼはトウダイグサ科で全く別の樹です。










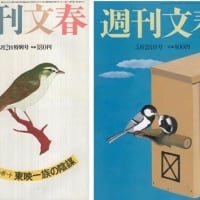
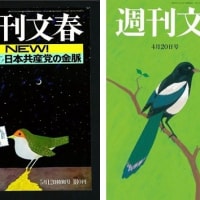













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます