本を出版することを「上梓(じょうし)」と言います。
「梓(あずさ)」という文字や言葉を聞いて、「梓みちよ」を思い浮かべた人は私と同年代、狩人が歌う「あずさ2号」を思い浮かべた人は少し若い人でしょう。この梓も木編ですから、木の名前です。
植物学では、梓ではなく「ミズメ」と呼びます。カバノキ科ですが、横一の皮目や葉っぱがサクラによく似ています。私も「栃の森」にあるミズメを、しばらくヤマザクラと思い込んでいました。

(皮目が横一になるのはサクラかカバノキ)

(葉の付け根がハート型に凹むのはカバノキ、サクラは凹まない)
材もヤマザクラによく似ているため、他のカバノキと一緒にして材木業界では「カバザクラ」と呼んでいます。ヤマザクラは良材で、家具のほか浮世絵の版木にも使われたそうです。
ここで、冒頭の出版の話に戻るのですが、私はヤマザクラによく似たミズメ(梓)を本の版木に使ったので「上梓」という言葉が生れた、と考えていました。
木に関するモンスターサイト「木の情報発信基地」にもそういう記事があります。
ところが、「上梓」という言葉が生れたのは中国。一方、ミズメ(梓)は日本固有種という矛盾に突き当たりました。
で、いろいろ調べた結果、「梓」という漢字は中国ではキササゲという木を意味し、そのキササゲは「百木の王」と呼ばれるほどの良材であることが判明しました。

(トウキササゲの葉・京都府立植物園で撮影)
有用なキササゲは多分、版木にも使われたのでしょう。そして、キササゲ=版木という意味になったのだと思われます。漢和辞典の「梓」には、木の名前のほかに、はっきり「版木」と書いてあります。
キササゲは日本には自生しませんから、「梓」という漢字を(どういう訳か)ミズメに当てはめたのです。
「梓みちよ」からここまで引っ張るか? 込み入った話で申し訳ないです。
「梓(あずさ)」という文字や言葉を聞いて、「梓みちよ」を思い浮かべた人は私と同年代、狩人が歌う「あずさ2号」を思い浮かべた人は少し若い人でしょう。この梓も木編ですから、木の名前です。
植物学では、梓ではなく「ミズメ」と呼びます。カバノキ科ですが、横一の皮目や葉っぱがサクラによく似ています。私も「栃の森」にあるミズメを、しばらくヤマザクラと思い込んでいました。

(皮目が横一になるのはサクラかカバノキ)

(葉の付け根がハート型に凹むのはカバノキ、サクラは凹まない)
材もヤマザクラによく似ているため、他のカバノキと一緒にして材木業界では「カバザクラ」と呼んでいます。ヤマザクラは良材で、家具のほか浮世絵の版木にも使われたそうです。
ここで、冒頭の出版の話に戻るのですが、私はヤマザクラによく似たミズメ(梓)を本の版木に使ったので「上梓」という言葉が生れた、と考えていました。
木に関するモンスターサイト「木の情報発信基地」にもそういう記事があります。
ところが、「上梓」という言葉が生れたのは中国。一方、ミズメ(梓)は日本固有種という矛盾に突き当たりました。
で、いろいろ調べた結果、「梓」という漢字は中国ではキササゲという木を意味し、そのキササゲは「百木の王」と呼ばれるほどの良材であることが判明しました。

(トウキササゲの葉・京都府立植物園で撮影)
有用なキササゲは多分、版木にも使われたのでしょう。そして、キササゲ=版木という意味になったのだと思われます。漢和辞典の「梓」には、木の名前のほかに、はっきり「版木」と書いてあります。
キササゲは日本には自生しませんから、「梓」という漢字を(どういう訳か)ミズメに当てはめたのです。
「梓みちよ」からここまで引っ張るか? 込み入った話で申し訳ないです。

















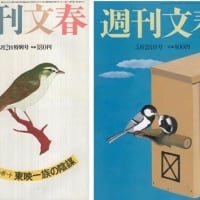
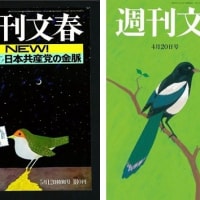





それからキササゲですが私のいる地方ではお庭に一本という感じで植えられています、結構大木になるし「ササゲ」のような種子がいつまでもぶら下がっているので目立つ樹木です。それから花も綺麗ですね。
「ミネバリ」が「オノオレカンバ」の別名とは知りませんでした。「夜糞・・」といい「斧折れ・・」といい、昔の人の命名の想像力にはいつも感心します。私が樹の名前に興味を持つ所以です。
こちらでは、キササゲが一般の庭に植えられているのは見たことありません。ある宿泊施設の庭で、長い豆みたいな実をつけているのを見たことがあります。