第15代応神天皇の皇子・莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)は、頭脳明晰だったので次期天皇と目されましたが、異母兄弟である(後の)仁徳天皇との政争を避けて宇治に逃れてきました。その際、ウサギが道案内したので「莵(うさぎ)の道」と書き(「稚郎子」は皇子を意味する敬称)、それが「うじ」という地名になった…というのが当地の伝説です。
その伝説の人物の陵墓が、現在は京都府最大のサギのコロニーになっています。宮内庁が管理する森なので誰も近づかないことや、宇治川の横なので餌の魚や巣材の枝がたくさんあることがサギには好都合なのでしょう。
4月頃から巣材の枝をくわえて飛ぶサギが見られます。撮影した6月上旬は、卵を抱いたり、雛に給餌したりしていました。
日曜日、午前中はここで観察会を実施し、午後は近くの文化施設で野鳥の会の総会を開催する予定でしたが、雨模様だったので観察会は中止しました。
今までこのコロニーでアマサギを見たことがなかったのですが、対岸の河畔林にアマサギを発見。前回の記事でご紹介したアマサギは、ここから2kmほど離れた干拓地で撮影しましたが、多分ここで子育てするのでしょう。
「コロニー」とは「集団繁殖地」のことで、普通のコロニーでは同一種が繁殖しますが、サギの場合は(同じ仲間とはいえ)異なる種類が同居することが特徴です。
その伝説の人物の陵墓が、現在は京都府最大のサギのコロニーになっています。宮内庁が管理する森なので誰も近づかないことや、宇治川の横なので餌の魚や巣材の枝がたくさんあることがサギには好都合なのでしょう。
4月頃から巣材の枝をくわえて飛ぶサギが見られます。撮影した6月上旬は、卵を抱いたり、雛に給餌したりしていました。
日曜日、午前中はここで観察会を実施し、午後は近くの文化施設で野鳥の会の総会を開催する予定でしたが、雨模様だったので観察会は中止しました。
今までこのコロニーでアマサギを見たことがなかったのですが、対岸の河畔林にアマサギを発見。前回の記事でご紹介したアマサギは、ここから2kmほど離れた干拓地で撮影しましたが、多分ここで子育てするのでしょう。
「コロニー」とは「集団繁殖地」のことで、普通のコロニーでは同一種が繁殖しますが、サギの場合は(同じ仲間とはいえ)異なる種類が同居することが特徴です。

















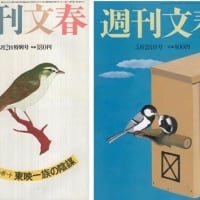
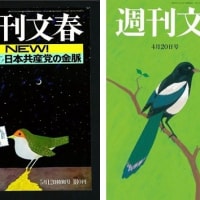





>莵道が由緒ある地名、皇子の名前からなのですね。皇室の御陵は立ち入り禁止だから、鳥... への返信
そうなんです。鳥にとっては、安心して子育てできる場所です。ただ、15年ほど前、宇治川花火大会をやっていた頃は、このコロニーn前が打ち上げ場所だったので、昼間から空砲を打ち上げたり、夜は花火を打ち上げるたびに驚いてサギが飛び出していました。