私が住んでいる宇治市は「源氏物語のまち」として観光PRしています。
『源氏物語』全54帖のうち最後の10帖が、「宇治十帖」と呼ばれる宇治を舞台にした物語だからです。近所には「源氏物語ミュージアム」という博物館がありますし、紫式部にちなんで女性作家を対象にした「紫式部文学賞」も創設しています。
源氏物語ミュージアムには、当然のことながらムラサキシキブが植えてあります。散歩コースなので、毎朝通りながら実が紫色になるのを楽しみにしていました。

この樹の名前はもちろん紫式部に由来すると思っていたのですが、ルーツはどうも違うようです。江戸時代のある俳人の記録には、「たまむらさき、京にてむらさきしきみと言う。筑紫にてこむらさきと言う」と記されています。つまり、江戸では「玉紫」、京都では「紫しきみ」、九州では「小紫」と呼んでいると言うのです。
そして、ある学者は「紫重き実(しきみ)」が語源で、紫色の実を重いほどたくさんつけることに由来すると言っています。よく考えれば、紫式部が有名になる前は「ムラサキシキブ」なんて誰も呼ばないはずです。
正確に言えば、写真はコムラサキシキブ。本来のムラサキシキブは山に自生しています。庭に植えてあるのはほとんどがコムラサキシキブです。
この樹の学名Kallos Carposはギリシア語で「美しい実」。英語でもBeauty Berry(美しい実)と言います。その名前の通り実ばかり注目されますが、材は堅くて粘り強いので大工道具やコウモリ傘の柄に使われるそうです。
うちの庭にも2本植えていますが、名前や見た目のイメージよりもしたたかな樹で、繁殖力も強く、ぐんぐん大きくなります。
「玉紫」や「小紫」のほかに、鳥が実を食べるので「鳥紫」という別名もあったそうです。そう言えば、うちのコムラサキシキブにもヒヨドリが群がっていました。
『源氏物語』全54帖のうち最後の10帖が、「宇治十帖」と呼ばれる宇治を舞台にした物語だからです。近所には「源氏物語ミュージアム」という博物館がありますし、紫式部にちなんで女性作家を対象にした「紫式部文学賞」も創設しています。
源氏物語ミュージアムには、当然のことながらムラサキシキブが植えてあります。散歩コースなので、毎朝通りながら実が紫色になるのを楽しみにしていました。

この樹の名前はもちろん紫式部に由来すると思っていたのですが、ルーツはどうも違うようです。江戸時代のある俳人の記録には、「たまむらさき、京にてむらさきしきみと言う。筑紫にてこむらさきと言う」と記されています。つまり、江戸では「玉紫」、京都では「紫しきみ」、九州では「小紫」と呼んでいると言うのです。
そして、ある学者は「紫重き実(しきみ)」が語源で、紫色の実を重いほどたくさんつけることに由来すると言っています。よく考えれば、紫式部が有名になる前は「ムラサキシキブ」なんて誰も呼ばないはずです。
正確に言えば、写真はコムラサキシキブ。本来のムラサキシキブは山に自生しています。庭に植えてあるのはほとんどがコムラサキシキブです。
この樹の学名Kallos Carposはギリシア語で「美しい実」。英語でもBeauty Berry(美しい実)と言います。その名前の通り実ばかり注目されますが、材は堅くて粘り強いので大工道具やコウモリ傘の柄に使われるそうです。
うちの庭にも2本植えていますが、名前や見た目のイメージよりもしたたかな樹で、繁殖力も強く、ぐんぐん大きくなります。
「玉紫」や「小紫」のほかに、鳥が実を食べるので「鳥紫」という別名もあったそうです。そう言えば、うちのコムラサキシキブにもヒヨドリが群がっていました。










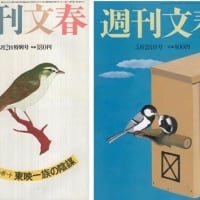
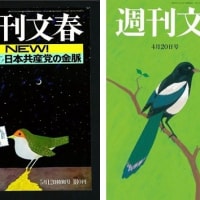













http://blog.kansai.com/hitoha
樹に詳しくない私も、ムラサキシキブなら実がなっていたらわかります。
ところで、hitohaさんって「一葉」さんですかね? すみません、何でもかんでも木に結び付けて考えるものですから。
ムラサキシキブとコムラサキシキブをさがしていたらたどりつきました。
知らなかったのですが、コが付くと違うのですね~。
ムラサキシキブは随分高く生長するようですね。
宇治は雰囲気がいいところですね。
山が近くて川が流れていて。
平等院には鳳凰を見によく行きます。
また宇治の木々情報を見に寄らせていただきますね。
ムラサキシキブとコムラサキシキブの違いですが、前者は葉っぱ全体に鋸歯(ギザギザ)がありますが、後者には上半分にしかありません。
庭や街の植栽に使われているのは、ほとんどコムラサキです。
ぜひ、また訪れてください、こちらにも、宇治にも。
山の中に入るとムラサキシキブが多いですね。私も先日、タカの渡りを見に岩間山に登ったとき、ムラサキシキブを見つけましたが、実が成っていませんでした。
多分、小鳥が食べたのでしょう。