週末に栃の森へ行ってきました。今年初めての森歩き。
この冬は雪が少なかったようで、例年なら日陰に雪が残っていますが、今回はどこにも見当たりません。その分、樹木の開花が早かったようで、いつもは咲いている花が見られなかったり、盛りを過ぎていたりしました。
この森は今が早春。枝から新芽が出て、葉が展開し始めています。やわらかな黄緑色の葉に包まれた森は、見ているだけで気持ちよく、思わず深呼吸してしまいます。

ミズキの展葉
林道の脇に立つタラノキからは頂芽が伸びています。タラノメとして重宝されますが、私は数少ない2回羽状複葉の樹として注目しています。

カツラも小さな丸い葉を規則正しく並べています。わが家のカツラはすでに展葉が終りましたが、こちらはまだ生まれたばかり。こういう葉の感じがこの樹の魅力です。

花も少し紹介します。ムシカリ(別名オオカメノキ)の装飾花と本来の花が両方ともきれいに咲いていました。周囲の大きな白い花が虫を集めるための装飾花、中央の小さい花が本当の花です。

帰路、キャンプサイト近くでウスギヨウラクを見つけました。ツツジの仲間で、漢字で書くと「薄黄瓔珞」。「瓔珞」は珠玉や貴金属に糸を通して作った釣鐘型の装身具のことで、仏像や寺院の装飾品に使われます。

一方、毎年4月下旬の訪問時に見られるキンキマメザクラ(別名ヤマヒガン)やマルバマンサク、ヤマヤナギは花が見られませんでした。アセビやヒサカキは盛りが終っていました。こんな年もあるんですね。
この冬は雪が少なかったようで、例年なら日陰に雪が残っていますが、今回はどこにも見当たりません。その分、樹木の開花が早かったようで、いつもは咲いている花が見られなかったり、盛りを過ぎていたりしました。
この森は今が早春。枝から新芽が出て、葉が展開し始めています。やわらかな黄緑色の葉に包まれた森は、見ているだけで気持ちよく、思わず深呼吸してしまいます。

ミズキの展葉
林道の脇に立つタラノキからは頂芽が伸びています。タラノメとして重宝されますが、私は数少ない2回羽状複葉の樹として注目しています。

カツラも小さな丸い葉を規則正しく並べています。わが家のカツラはすでに展葉が終りましたが、こちらはまだ生まれたばかり。こういう葉の感じがこの樹の魅力です。

花も少し紹介します。ムシカリ(別名オオカメノキ)の装飾花と本来の花が両方ともきれいに咲いていました。周囲の大きな白い花が虫を集めるための装飾花、中央の小さい花が本当の花です。

帰路、キャンプサイト近くでウスギヨウラクを見つけました。ツツジの仲間で、漢字で書くと「薄黄瓔珞」。「瓔珞」は珠玉や貴金属に糸を通して作った釣鐘型の装身具のことで、仏像や寺院の装飾品に使われます。

一方、毎年4月下旬の訪問時に見られるキンキマメザクラ(別名ヤマヒガン)やマルバマンサク、ヤマヤナギは花が見られませんでした。アセビやヒサカキは盛りが終っていました。こんな年もあるんですね。

















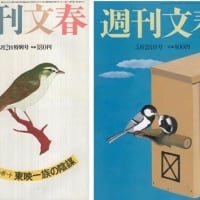
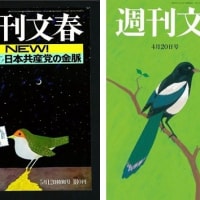





拝見しているだけで、深呼吸したくなります。
栃の森は懐かしい思い出の森です。
ときどきアップして下さいね。楽しみにしています。
思い出の森、ということは以前は何度か訪れておられたのですね。
多分、その頃と比べると、林床部の植生がシカの食害で大きく変化していると思いますが、それでも多様性豊かな森であることには変わりはありません。
私はあまり関心がないので写しませんが、同行のメンバーは珍しい野草やキノコの写真を撮っています。
鳥のことは来週に報告します。
あの頃はまだ長治谷に京大の小屋があり、その前の芝生広場でお弁当を食べたりしましたね。
長治谷の作業小屋は7~8年前の大雪で潰れました。現在は倉庫だけが残っています。
今も同行メンバーと一緒に最後の休憩場所として利用しています。時々タカが飛びます。
木々の新葉は形が面白くて思わず写真を撮りたくなりますよね。
マメザクラがあるんですね、今年は見られなかったということで残念ですが。
桜の本を読んでから桜への興味が高まったのですが、こちらには自生で4種(オオヤマ、カスミ、ミヤマ、タカネ)しかないのでいつか本州の山で野生の桜を見てみたいです。
この森に行くと、オオヤマザクラ、キンキマメザクラが見られます。
お花見の名所にはいろんな栽培品種が咲いているようですが、種類が多すぎて覚えられませんし、あまり興味がないです。
そちらは、今が満開のようですね。