尾形光琳は『燕子花(かきつばた)図』や『紅白梅図』でよく知られていますが、花だけでなく鳥も描いていて、2つの代表作と同じく華麗な画風の『群鶴図』があります。
左隻(させき)に9羽、右隻に10羽描かれているのはナベヅル。写実的ではなく、工芸デザインも手掛けた光琳らしく、単純化されています。『紅白梅図』にも描かれている流水紋と金箔を配した背景に、ナベヅルが並んだ豪華な屏風絵です。
 左隻
左隻
 右隻
右隻
光琳が鳥をスケッチした「鳥獣写生図巻」には66種の鳥が描かれていますが、実物の鳥を写生したわけではなく、江戸時代初期の絵師・狩野探幽(たんゆう)の写生帖を模写したようです。カメラはもちろん双眼鏡も望遠鏡もなかった当時、絵師たちは飼い鳥やはく製を写生するか、先人たちの写生図を模写する以外にスケッチの方法がなかったわけです。
ある研究者によると、光琳は探幽の写生図をそのまま模写するだけでなく、配色をアレンジしたり細部をデフォルメしているとのこと。つまり、実際の鳥とは異なるものをスケッチしていたわけです。
私たちは何となく「日本画の鳥は写実的で、本物のように生き生きと描かれている」と思いがちですが、伊藤若冲(じゃくちゅう)のタンチョウに鳥にはないはずの歯が描かれているように、必ずしも写実的とは限りません。にもかかわらず見る者を魅了するのが、作家の感性であり技でしょう。
光琳の死後に活躍した円山応挙も『群鶴図』を描いています。光琳のナベヅルに対して、こちらはタンチョウとマナヅル。
 左隻
左隻
 右隻
右隻
光琳がデザイン的に単純化して描いたのに対して、応挙は写実的。近世の日本画家の中でも特に写実を重視した応挙は、常に写生帖を持ち歩いてスケッチを繰り返したそうです。
しかし、光琳と同じく、鳥の実物を写生することが難しいので、先人の写生図を模写せざるを得ませんでした。応挙が模写したのは、先輩の絵師・渡辺始興(しこう)の「真写鳥類図巻(しんしゃちょうるいずかん)」。63種類の鳥が部分拡大図などと共に描かれた17メートルにもおよぶ巻物です。
面白いのは、光琳が狩野探幽の写生図をアレンジしながら模写したのに対して、応挙は始興の元絵をそのままコピーしたように模写していること。
ツルの元絵が始興のものかどうか不明ですが、12羽のタンチョウと5羽のマナヅルがそれぞれ異なる動きや向きで描かれています。光琳の『群鶴図』は19羽のナベヅルがほとんど同じ向きと姿勢であったのとは対照的です。構図(デザイン)を優先した光琳と、写実(リアル)を優先した応挙の違いがよく分かります。
私の好みは、長年仕事でデザインに関わってきたので、やはり光琳です。
左隻(させき)に9羽、右隻に10羽描かれているのはナベヅル。写実的ではなく、工芸デザインも手掛けた光琳らしく、単純化されています。『紅白梅図』にも描かれている流水紋と金箔を配した背景に、ナベヅルが並んだ豪華な屏風絵です。
 左隻
左隻 右隻
右隻光琳が鳥をスケッチした「鳥獣写生図巻」には66種の鳥が描かれていますが、実物の鳥を写生したわけではなく、江戸時代初期の絵師・狩野探幽(たんゆう)の写生帖を模写したようです。カメラはもちろん双眼鏡も望遠鏡もなかった当時、絵師たちは飼い鳥やはく製を写生するか、先人たちの写生図を模写する以外にスケッチの方法がなかったわけです。
ある研究者によると、光琳は探幽の写生図をそのまま模写するだけでなく、配色をアレンジしたり細部をデフォルメしているとのこと。つまり、実際の鳥とは異なるものをスケッチしていたわけです。
私たちは何となく「日本画の鳥は写実的で、本物のように生き生きと描かれている」と思いがちですが、伊藤若冲(じゃくちゅう)のタンチョウに鳥にはないはずの歯が描かれているように、必ずしも写実的とは限りません。にもかかわらず見る者を魅了するのが、作家の感性であり技でしょう。
光琳の死後に活躍した円山応挙も『群鶴図』を描いています。光琳のナベヅルに対して、こちらはタンチョウとマナヅル。
 左隻
左隻 右隻
右隻光琳がデザイン的に単純化して描いたのに対して、応挙は写実的。近世の日本画家の中でも特に写実を重視した応挙は、常に写生帖を持ち歩いてスケッチを繰り返したそうです。
しかし、光琳と同じく、鳥の実物を写生することが難しいので、先人の写生図を模写せざるを得ませんでした。応挙が模写したのは、先輩の絵師・渡辺始興(しこう)の「真写鳥類図巻(しんしゃちょうるいずかん)」。63種類の鳥が部分拡大図などと共に描かれた17メートルにもおよぶ巻物です。
面白いのは、光琳が狩野探幽の写生図をアレンジしながら模写したのに対して、応挙は始興の元絵をそのままコピーしたように模写していること。
ツルの元絵が始興のものかどうか不明ですが、12羽のタンチョウと5羽のマナヅルがそれぞれ異なる動きや向きで描かれています。光琳の『群鶴図』は19羽のナベヅルがほとんど同じ向きと姿勢であったのとは対照的です。構図(デザイン)を優先した光琳と、写実(リアル)を優先した応挙の違いがよく分かります。
私の好みは、長年仕事でデザインに関わってきたので、やはり光琳です。

















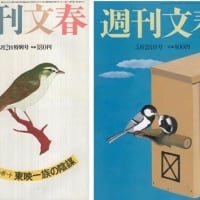
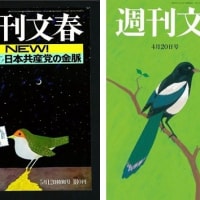





光琳が住んでいたころ、京都にはナベヅルが多かったのでしょうね、きっと。
絵になるツル=丹頂と思い込んでいましたので。
花冷えが少し和らぎそうで、嬉しいです。
そうですね、日本画に描かれるツルはタンチョウが多いですね。ナベヅルやマナヅルが描かれることは少ないです。
ようやく花見できそうです。そちらのお庭も花盛りのようですね。