毎年、冬の間に一度は琵琶湖にカモを見に出かけますが、今年は2ヶ月ほど前に滋賀県中部の能登川町(現・東近江市)まで足を伸ばしました。
ここには水車公園があって、その前に広がる伊庭内湖(いばないこ)という小さな湖にカモがプカプカ浮いています。でも、今日はカモではなく水車のお話。

(直径13mの関西一の大水車。実用ではなく観光用)
昭和17年の調査では日本に78,500基もあった水車が、40年後の昭和57年には496基に減ったそうです。能登川町にも昔は40基ほどあったものの、昭和46年に姿を消したので、ふるさと創生事業で水車公園として復元しました。

(半実用の水車。中では精米しています)
水車はもちろん木製。一般的に、水の流れを受ける部分(水輪)にはスギなど耐水性のある針葉樹が使われました。また、最も磨耗の激しい心棒にはケヤキが使われましたが、大きなケヤキは高価なので、昔の人々は磨り減る部分だけ取り替えるようにカシの巻き板を使うという工夫をしたようです。「菊座」と呼ばれる歯車にもケヤキ、カシ、クリなどの硬い木が使われました。

(菊座と呼ばれる歯車。これはケヤキ製)
この水車公園には、観光目的の大水車とは別に、希望者が精米できる半実用の水車があります。精米には約60時間かかるそうですが、精米機のように熱が発生せず、胚芽も傷つかないので、おいしくて高品質の白米になるそうです。

ゴトン…、ゴトン…と杵が超スローテンポで上下しながら、石臼の中にある玄米をついています。水車小屋の中には、眠くなるくらいゆったりとした時間が流れていました。
ここには水車公園があって、その前に広がる伊庭内湖(いばないこ)という小さな湖にカモがプカプカ浮いています。でも、今日はカモではなく水車のお話。

(直径13mの関西一の大水車。実用ではなく観光用)
昭和17年の調査では日本に78,500基もあった水車が、40年後の昭和57年には496基に減ったそうです。能登川町にも昔は40基ほどあったものの、昭和46年に姿を消したので、ふるさと創生事業で水車公園として復元しました。

(半実用の水車。中では精米しています)
水車はもちろん木製。一般的に、水の流れを受ける部分(水輪)にはスギなど耐水性のある針葉樹が使われました。また、最も磨耗の激しい心棒にはケヤキが使われましたが、大きなケヤキは高価なので、昔の人々は磨り減る部分だけ取り替えるようにカシの巻き板を使うという工夫をしたようです。「菊座」と呼ばれる歯車にもケヤキ、カシ、クリなどの硬い木が使われました。

(菊座と呼ばれる歯車。これはケヤキ製)
この水車公園には、観光目的の大水車とは別に、希望者が精米できる半実用の水車があります。精米には約60時間かかるそうですが、精米機のように熱が発生せず、胚芽も傷つかないので、おいしくて高品質の白米になるそうです。

ゴトン…、ゴトン…と杵が超スローテンポで上下しながら、石臼の中にある玄米をついています。水車小屋の中には、眠くなるくらいゆったりとした時間が流れていました。

















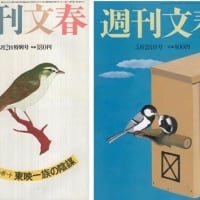
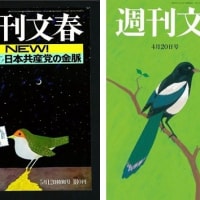





そんな名残りの穴のいっぱい空いた緑っぽい色の板が何枚か残っていたのを覚えています。
水車からモーターに切り替えてうまくいかなかったところには、どんな事情があったのでしょうね。エネルギーの転換によって、いろんな分野で激変があったのでしょう。
水車って、要するに引力を動力に変換するものですね。自然エネルギーとして、風力発電みたいな応用はできないのでしょうか。
カモはこっちでも少なくなりましたが、でも道南に行く時、
どこかにまだオオハクチョウがいてびっくりしました。
それと道南の川を通った時車から一瞬ですがチュウサギが見えました。
札幌周辺ではチュウサギはかなり珍しいので、
車を止めて撮りたかったのですが、国道で車が連なっていて
泣く泣く諦めました。
私もいつもの散歩コースで、先日まだシロハラがいたので驚きました。「もう、帰れよ」と言っておきました。渡り鳥の初認日はギタバさんも記録されていますが、終認日というのは普通、記録するものなんでしょうか?
記録すべきですね。私は何も記録していませんが。