日本で観察できる主なフクロウ類は8種類。このうちフクロウとシマフクロウ以外は「○○○○ズク」と名付けられています。「ズク」は漢字で「木菟」。ウサギのような耳を持った鳥が木に止まっている姿を表しているのでしょう。
トラフズクをモデルにしたといわれる「となりのトトロ」にも耳があります。
正確にはフクロウ類の聴覚器官は顔面の目の横あたりにあって、耳のように見える部位は耳角(うかく)と呼ばれています。
この耳角が小さいので「小耳木菟(コミミズク)」と命名されたフクロウが、この冬、淀川の河川敷に7~8羽まとまって飛来し、連日多くのバードウォッチャーやフォトグラファーを集めています。
私も先日、2度目の観察に行ってきました。杭の上にとまっている姿には、小さい耳が出ています。
この耳角が聴覚器官でないとすると、何のためにあるのでしょう?
調べてみると、いくつかの説があります。一つは、カムフラージュ説。耳を立てることによって木の枝を模しているというもの。
しかし、それなら常に耳を立てておくべきですが、「木の菟」はウサギと同じように耳を立てたり寝かしたりします。
「なるほど」と納得したのは、ペットとして外来種のフクロウを飼っている人の見解。そのフクロウは眠る時に耳角を立てることが多いそうです。
以前「フクロウの首」でご紹介したように、起きているときは首を左右270°回転させて音をキャッチしますが、眠っているときは首を回せません。睡眠中に後方の音をキャッチするために耳を立てているのではないかという説です。
その人の説明では、耳角は本来の聴覚器官の真上あたりに位置し、根本に少し窪みがあるそうです。
私が撮った動画を見ても、他の人の写真を見ても、飛翔中のコミミズクは耳角を立てていません。飛んでいるときは後方の音が必要ないからでしょう。
しかし、フクロウの耳にはもう一つ疑問があります。フクロウとアオバズクには耳角がありませんが、これはなぜか? 「後方の音キャッチ」説ではこの疑問は解けません。
フクロウとアオバズクには生態的に後方の音をキャッチする必要がないのか、あるいは、目立たないだけで耳角と同じ働きをする部位があるのか。疑問は次々に湧いてきます。
トラフズクをモデルにしたといわれる「となりのトトロ」にも耳があります。
正確にはフクロウ類の聴覚器官は顔面の目の横あたりにあって、耳のように見える部位は耳角(うかく)と呼ばれています。
この耳角が小さいので「小耳木菟(コミミズク)」と命名されたフクロウが、この冬、淀川の河川敷に7~8羽まとまって飛来し、連日多くのバードウォッチャーやフォトグラファーを集めています。
私も先日、2度目の観察に行ってきました。杭の上にとまっている姿には、小さい耳が出ています。
この耳角が聴覚器官でないとすると、何のためにあるのでしょう?
調べてみると、いくつかの説があります。一つは、カムフラージュ説。耳を立てることによって木の枝を模しているというもの。
しかし、それなら常に耳を立てておくべきですが、「木の菟」はウサギと同じように耳を立てたり寝かしたりします。
「なるほど」と納得したのは、ペットとして外来種のフクロウを飼っている人の見解。そのフクロウは眠る時に耳角を立てることが多いそうです。
以前「フクロウの首」でご紹介したように、起きているときは首を左右270°回転させて音をキャッチしますが、眠っているときは首を回せません。睡眠中に後方の音をキャッチするために耳を立てているのではないかという説です。
その人の説明では、耳角は本来の聴覚器官の真上あたりに位置し、根本に少し窪みがあるそうです。
私が撮った動画を見ても、他の人の写真を見ても、飛翔中のコミミズクは耳角を立てていません。飛んでいるときは後方の音が必要ないからでしょう。
しかし、フクロウの耳にはもう一つ疑問があります。フクロウとアオバズクには耳角がありませんが、これはなぜか? 「後方の音キャッチ」説ではこの疑問は解けません。
フクロウとアオバズクには生態的に後方の音をキャッチする必要がないのか、あるいは、目立たないだけで耳角と同じ働きをする部位があるのか。疑問は次々に湧いてきます。

















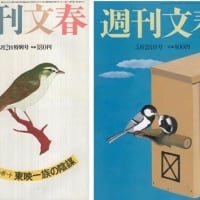
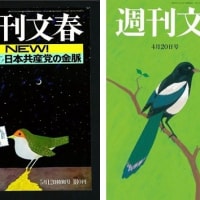





そういえばフクロウとアオバズクはないですね。
私は、本文で書かれているように、これらの種はなんらかの理由でその必要がない、としか考えたことがなかったことに気づきました。
余談ですが、例えばうちにいるラブラドール・レトリバーなどたれ耳の犬は、その方が後ろからの音を捉えやすいのだろうなと(改良された)、実際に犬を見ていてそう考えました。
ちょっとしたことでも、「何故だろう?」と考えると、次々に疑問が湧いてきます。
淀川河川敷にはたくさんいるのですね。「昔の巨椋どころではないよ」なんだそうです。
一度行ってみたいと思ってはいますが・・・。
私もそちらのブログ毎回拝見しています。ほとんどコメントしておりませんが…。
巨椋のコミミズクを見ようと、昨年も今年も何度か足を運びましたがダメでした。
一方、淀川のコミミズクは、数も多いし、確実に出現してくれます。何回も足を運んでいる人のブログを見ると、出ない日もあるようですが、私は2回とも堪能できました。
あの場所は来年は何かの施設ができるそうで、コミミズクが渡来するのも今年だけ、という人もいます。
ぜひ、今のうちに行かれることをお勧めします。駅から歩いても5分くらいです。