愛車のラストランで奈良に出かけた際、正倉院にも寄ってきました。東大寺や聖武天皇の宝物が保存されていた建造物です。
断面が三角形の木材を組み上げた校倉(あぜくら)造りは、湿度が高い時は木材が膨張して湿気を防ぎ、乾燥している時は木材が収縮して風を通すので宝物の保存に適している…。みなさんもそうでしょうが、私は学校でそう習いました。
でも、あれはウソ。実際には屋根の重みで校木(あぜぎ)が膨張したり収縮する余地はないそうです。

(天気が悪くて暗いですが、奈良の正倉院)
元旦にNHKが正倉院のドキュメント番組を放映していました。それによると、校木(あぜぎ)はすべてヒノキ。内部の棚にスギ製の唐櫃(からびつ=収納箱)が並び、その中に宝物が保存されていました。
宝物はヒノキとスギで二重に守られていたわけですが、湿気を吸ったり吐いたりする木の調湿作用によって、正倉院内部は湿度の変化が少なく、さらに唐櫃(からびつ)の中はほぼ一定に保たれていたそうです。
しかも、スギはオゾンや二酸化窒素など宝物を劣化させる物質を吸着することが最近になって分ってきました。ヒノキやスギのおかげで、宝物の美しい色や微妙な形、さらには香りまで1300年もの間保たれてきたわけです。
これほど保存性の高い倉庫は世界に例がなく、正倉院は「世界の宝庫」と言われているそうです。

(三角形の木材を組み上げた校倉造り)
現在は鉄筋コンクリートの宝物館の中で、温度や湿度を一定に保つコントロールシステムによって保存管理されています。内装はすべて木製で、宝物は一点一点和紙に包んだ上、桐の箱に収納されています。また、チョウジとジンコウとビャクダンを混ぜた昔ながらの防腐剤を使っているとか。
木が膨張したり収縮するという説は間違いですが、木が湿気を呼吸して宝物を守ったわけですから、全くのウソというわけではないですね。
断面が三角形の木材を組み上げた校倉(あぜくら)造りは、湿度が高い時は木材が膨張して湿気を防ぎ、乾燥している時は木材が収縮して風を通すので宝物の保存に適している…。みなさんもそうでしょうが、私は学校でそう習いました。
でも、あれはウソ。実際には屋根の重みで校木(あぜぎ)が膨張したり収縮する余地はないそうです。

(天気が悪くて暗いですが、奈良の正倉院)
元旦にNHKが正倉院のドキュメント番組を放映していました。それによると、校木(あぜぎ)はすべてヒノキ。内部の棚にスギ製の唐櫃(からびつ=収納箱)が並び、その中に宝物が保存されていました。
宝物はヒノキとスギで二重に守られていたわけですが、湿気を吸ったり吐いたりする木の調湿作用によって、正倉院内部は湿度の変化が少なく、さらに唐櫃(からびつ)の中はほぼ一定に保たれていたそうです。
しかも、スギはオゾンや二酸化窒素など宝物を劣化させる物質を吸着することが最近になって分ってきました。ヒノキやスギのおかげで、宝物の美しい色や微妙な形、さらには香りまで1300年もの間保たれてきたわけです。
これほど保存性の高い倉庫は世界に例がなく、正倉院は「世界の宝庫」と言われているそうです。

(三角形の木材を組み上げた校倉造り)
現在は鉄筋コンクリートの宝物館の中で、温度や湿度を一定に保つコントロールシステムによって保存管理されています。内装はすべて木製で、宝物は一点一点和紙に包んだ上、桐の箱に収納されています。また、チョウジとジンコウとビャクダンを混ぜた昔ながらの防腐剤を使っているとか。
木が膨張したり収縮するという説は間違いですが、木が湿気を呼吸して宝物を守ったわけですから、全くのウソというわけではないですね。

















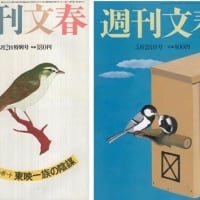
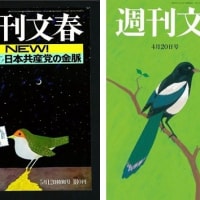





このようなことはやはりずっと遠い昔に発見した人が
いるわけなんですよね。
どうして気づいたのか、と同時に、観察眼が鋭い人というのは、
昔からいたんだろうなと思います。
漢方など伝統医学なども同じ経過をたどってのことでしょうが、昔の知恵はすごいです。