栃の森では野鳥や樹木を観察しますが、いろんな動物やその痕跡も見られます。
先月はリスが姿を見せましたし、これまでにもツキノワグマ、サル、カモシカ、イノシシなどに遭遇しました。シカもよく「クィ~ン」という高い声で鳴いています。
最近はこのシカが増え過ぎて、従来の生態系が変化しつつあります。どこの野山も同じ状況のようですが、栃の森ではササが激減して乾燥化が進んだり、樹皮が食害を受けて樹が枯れたり、周辺の農林業にも被害が出ています。

先週は、上の写真のような枝が散乱している場面に遭遇しました。表側の樹皮はきれいに剥がされて白い木部が露出していますが、ひっくり返して裏側を見ると樹皮はついたまま。最初は意味が分かりませんでしたが、どうやらシカの食痕のようです。

(別の枝に残っていたシカの食み跡)
枯れたり、風で折れて地面に落ちた枝の皮をシカが食べているのです。枝をひっくり返す知恵や技がないので、表側だけ食べたのでしょう。立木の樹皮が食害を受けているのはよく見ますが、ついに枯れ枝の樹皮まで口にするようになったのです。

(立木のカエデも樹皮を剥がされています)
周囲の植生から推測すると枝はハウチワカエデやヤマモミジのもの。しかも、この一帯では立木の被害もカエデ類に集中しています。シカはカエデが好きなのでしょうか。
イタヤカエデから甘い樹液を採取してメープルシロップを作るくらいですから、カエデ類の樹皮は甘いのかも知れません。「そう言えば、花札では鹿とカエデがセットになっていたな」と閃きましたが、関係ないですね。

(?)
別の場所ではトチノキに被害が集中していましたし、ある人の情報では別のエリアでオオバアサガラに被害が集中しているそうです。その場所でとりあえず口にしたものがおいしかったら、次々と同じ樹種を狙うのかも知れません。家族で行動しているので、食べ始めれば一気にやられるのでしょう。
シカによる生態系の撹乱を放置すべきか、それともシカを駆除するべきか、難問です。私には答えられません。
先月はリスが姿を見せましたし、これまでにもツキノワグマ、サル、カモシカ、イノシシなどに遭遇しました。シカもよく「クィ~ン」という高い声で鳴いています。
最近はこのシカが増え過ぎて、従来の生態系が変化しつつあります。どこの野山も同じ状況のようですが、栃の森ではササが激減して乾燥化が進んだり、樹皮が食害を受けて樹が枯れたり、周辺の農林業にも被害が出ています。

先週は、上の写真のような枝が散乱している場面に遭遇しました。表側の樹皮はきれいに剥がされて白い木部が露出していますが、ひっくり返して裏側を見ると樹皮はついたまま。最初は意味が分かりませんでしたが、どうやらシカの食痕のようです。

(別の枝に残っていたシカの食み跡)
枯れたり、風で折れて地面に落ちた枝の皮をシカが食べているのです。枝をひっくり返す知恵や技がないので、表側だけ食べたのでしょう。立木の樹皮が食害を受けているのはよく見ますが、ついに枯れ枝の樹皮まで口にするようになったのです。

(立木のカエデも樹皮を剥がされています)
周囲の植生から推測すると枝はハウチワカエデやヤマモミジのもの。しかも、この一帯では立木の被害もカエデ類に集中しています。シカはカエデが好きなのでしょうか。
イタヤカエデから甘い樹液を採取してメープルシロップを作るくらいですから、カエデ類の樹皮は甘いのかも知れません。「そう言えば、花札では鹿とカエデがセットになっていたな」と閃きましたが、関係ないですね。

(?)
別の場所ではトチノキに被害が集中していましたし、ある人の情報では別のエリアでオオバアサガラに被害が集中しているそうです。その場所でとりあえず口にしたものがおいしかったら、次々と同じ樹種を狙うのかも知れません。家族で行動しているので、食べ始めれば一気にやられるのでしょう。
シカによる生態系の撹乱を放置すべきか、それともシカを駆除するべきか、難問です。私には答えられません。










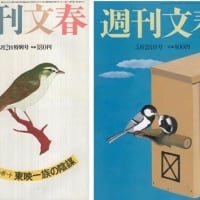
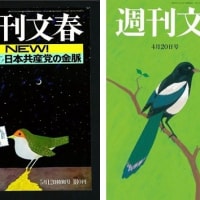














カエデはあまり聞いたことがありません。
量的にはいちばん多い樹木のように思えるのですが・・・
不思議ですね。
シカはシラカンバは食べないらしいですが、それは納得できますね(笑)。
ちなみにネズミの食害は、A公園ではナナカマドがいちばん多いです。
こちらでは、記事に書いたカエデやトチノキ、オオバアサガラのほかに、クサギやバイケイソウ、シダ類まで食べているようです。
クサギは名前の通り臭い木ですし、バイケイソウは人間には有毒です。こんなものまで食べるようになったということは、それだけ食べるものがなくなった、というか個体が増え過ぎたということでしょうね。