吉村昭氏の著書は26冊を読んでいて、これが27冊目。彼の小説は、多くは実話を再調査して歴史に埋もれていた人々の苦しい生活や阿鼻叫喚に、彼なりの客観性を与えて、まざまざと蘇らせるものが多いが、まれに歴史的事実ではないものや、歴史的事実を少し変えて書く場合もある。
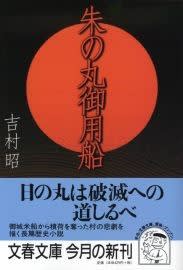
本書『朱の丸御用船』はノンフィクションなのかフィクションなのか。読んでいる途中でページを一旦閉じて、スマホで調べればわかるのだが、時間遅れでテレビ放映されるゴルフ中継の結果を途中で調べるようなもので無粋もいいとこだ。
ただ、なんとなくフィクションのような感じを持っていた。話がうま過ぎるわけだ。さらに、読み進むにつれ結末の恐ろしさが読者に重くのしかかってくる。そして、事態は破滅の方向に進んでいくわけだ。まったく小説的なのだ。
時代は江戸時代末期の天保年間、場所は三重県の漁村である。この漁村にかかわらず日本には古来忌まわしい風習が残っていた。それが難破船からの残留貨物の抜き取り。沈みそうな船が沖を通る時、船員は筏で逃げたり、泳いだり、あるいは船に取り残されたりするものだが、その船の荷物はいずれ海に沈むものとして、沿岸の漁民が群がるように奪い取っていた。なかには口封じのため生き残っていた船員をなんとかしたこともあっただろう。この漁村でもそうだった。
そして、ある時、沖合で難破した船がいて、米俵が相当量積まれた状態で水没に向かっていた。夜になり人目がなくなった頃、漁民たちが米俵を船から下ろし、漁村全体で山分けし、さらに物理的証拠を隠滅した。ところが沈みそうだった船は幕府の調達船(朱の本御用船)で、全国の幕府直轄地の米を江戸に運ぶ途中であった。幕府の財産の横領は関係者の死罪と定めがあった。しかし、漁民たちの行為は完全犯罪のはずだった。
ところが、沈んだ船の方にも事情があった。こちらも犯罪者だったのだ。幕府は米の輸送中の転売を恐れ、常に2隻で運航し相互監視するよう命じていた。しかし、犯罪はこの二隻の共謀で行われる。一隻目の船は各地で米を売り払い、二隻目の船も相当量の荷抜きを行った上、二隻とも海の難所と言われる大王崎付近で沈没させてしまったのだ。それが、三重の漁村の前を流れていったわけだ。
そして、沈没船の調査の方から犯行が露見していくわけだ。
この小説が書かれたのは1997年だが、それに先立つ1982年に『破船』が発表されている。こちらも難破船からの収奪品の話だが、どこかの集落で天然痘の患者に赤い服を着せ、海に流した話である。その患者船から天然痘と見抜けず略奪した服を着ているうちに村の大半が亡くなってしまうという恐ろしい話なのだが、この小説の怖さは、それほどでもない。結末が予想できるからだ。さらに発表後38年経っても、実話であるとは思われていないわけだ。
その『破船』が実話でないと考えられていることから『朱の本御用船』も実話ではないと感じていた。それでも十分に怖い。幕府の調査は日に日に事件発覚に近づいていて、ついに強制捜査の日になったのだが、この村は直前にニセ役人がきて口止め料を百両も奪われたばかりで、次にニセ役人が来たら打ち殺すことにしていた。そこに現れたのが本物の役人であったわけだ。
実は、この話は実話があったわけだ。地方の歴史愛好家の方が掘り出していて、それを吉村昭氏が過去の印税収入のうちいくばくかを投じて調べ直し、筆を執ったわけだ。
著者の膨大な作品群の中でも、かなり上位の小説だろうと思う。
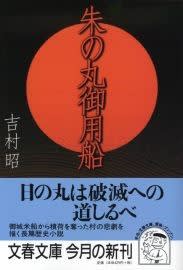
本書『朱の丸御用船』はノンフィクションなのかフィクションなのか。読んでいる途中でページを一旦閉じて、スマホで調べればわかるのだが、時間遅れでテレビ放映されるゴルフ中継の結果を途中で調べるようなもので無粋もいいとこだ。
ただ、なんとなくフィクションのような感じを持っていた。話がうま過ぎるわけだ。さらに、読み進むにつれ結末の恐ろしさが読者に重くのしかかってくる。そして、事態は破滅の方向に進んでいくわけだ。まったく小説的なのだ。
時代は江戸時代末期の天保年間、場所は三重県の漁村である。この漁村にかかわらず日本には古来忌まわしい風習が残っていた。それが難破船からの残留貨物の抜き取り。沈みそうな船が沖を通る時、船員は筏で逃げたり、泳いだり、あるいは船に取り残されたりするものだが、その船の荷物はいずれ海に沈むものとして、沿岸の漁民が群がるように奪い取っていた。なかには口封じのため生き残っていた船員をなんとかしたこともあっただろう。この漁村でもそうだった。
そして、ある時、沖合で難破した船がいて、米俵が相当量積まれた状態で水没に向かっていた。夜になり人目がなくなった頃、漁民たちが米俵を船から下ろし、漁村全体で山分けし、さらに物理的証拠を隠滅した。ところが沈みそうだった船は幕府の調達船(朱の本御用船)で、全国の幕府直轄地の米を江戸に運ぶ途中であった。幕府の財産の横領は関係者の死罪と定めがあった。しかし、漁民たちの行為は完全犯罪のはずだった。
ところが、沈んだ船の方にも事情があった。こちらも犯罪者だったのだ。幕府は米の輸送中の転売を恐れ、常に2隻で運航し相互監視するよう命じていた。しかし、犯罪はこの二隻の共謀で行われる。一隻目の船は各地で米を売り払い、二隻目の船も相当量の荷抜きを行った上、二隻とも海の難所と言われる大王崎付近で沈没させてしまったのだ。それが、三重の漁村の前を流れていったわけだ。
そして、沈没船の調査の方から犯行が露見していくわけだ。
この小説が書かれたのは1997年だが、それに先立つ1982年に『破船』が発表されている。こちらも難破船からの収奪品の話だが、どこかの集落で天然痘の患者に赤い服を着せ、海に流した話である。その患者船から天然痘と見抜けず略奪した服を着ているうちに村の大半が亡くなってしまうという恐ろしい話なのだが、この小説の怖さは、それほどでもない。結末が予想できるからだ。さらに発表後38年経っても、実話であるとは思われていないわけだ。
その『破船』が実話でないと考えられていることから『朱の本御用船』も実話ではないと感じていた。それでも十分に怖い。幕府の調査は日に日に事件発覚に近づいていて、ついに強制捜査の日になったのだが、この村は直前にニセ役人がきて口止め料を百両も奪われたばかりで、次にニセ役人が来たら打ち殺すことにしていた。そこに現れたのが本物の役人であったわけだ。
実は、この話は実話があったわけだ。地方の歴史愛好家の方が掘り出していて、それを吉村昭氏が過去の印税収入のうちいくばくかを投じて調べ直し、筆を執ったわけだ。
著者の膨大な作品群の中でも、かなり上位の小説だろうと思う。









