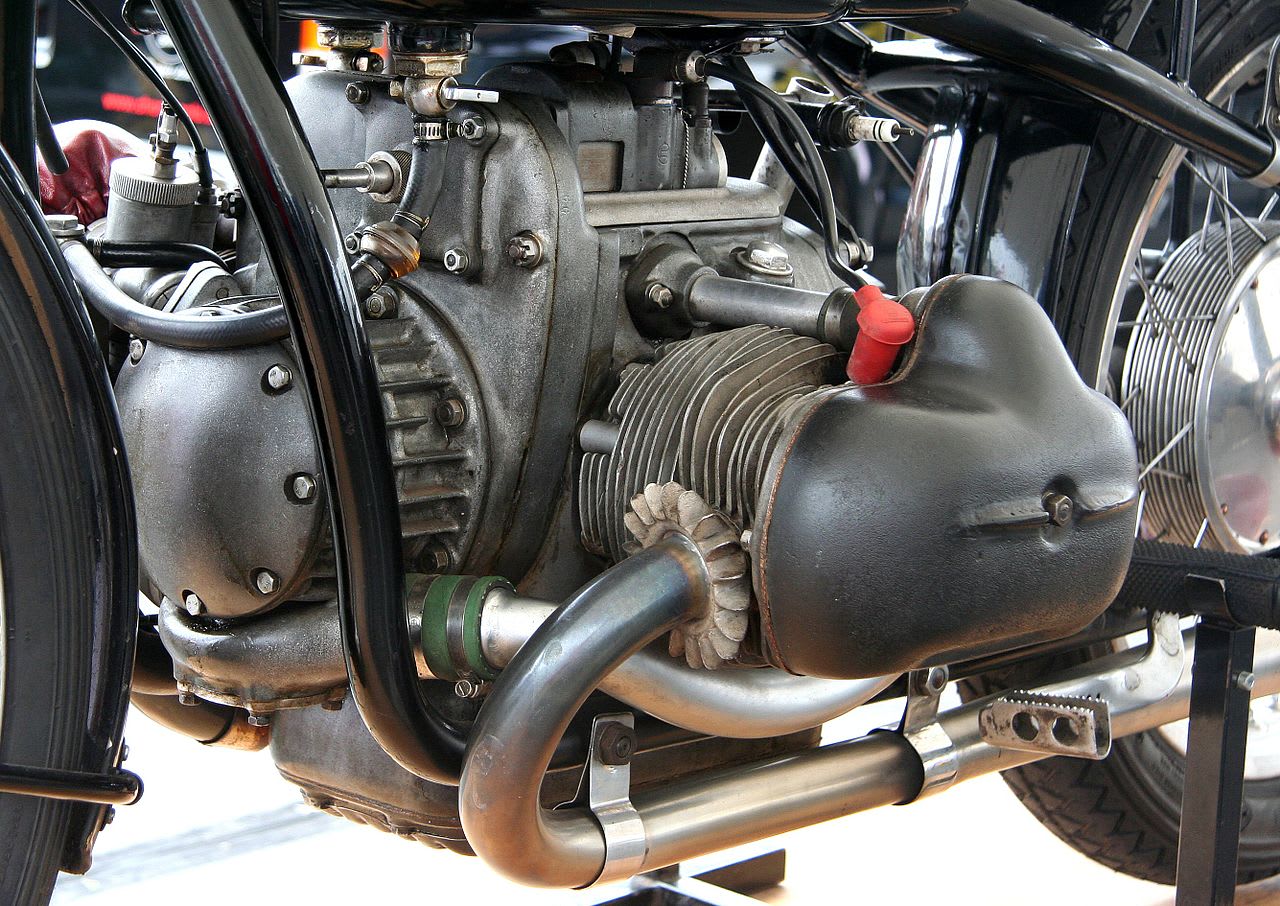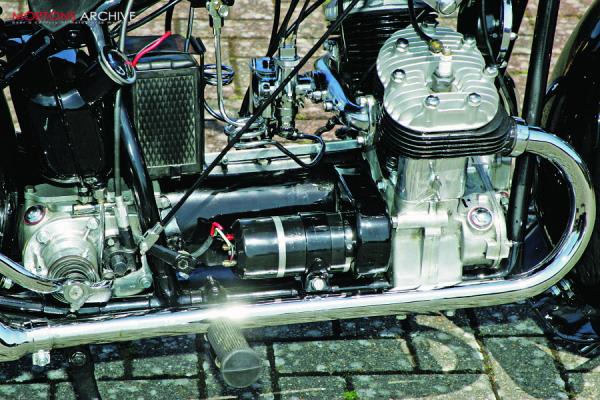2015年のR1はメカニズムとともに外観も大きく変わって、サーキットを更に意識するデザインになりヘッドライトがLEDになり本来の役目に徹することになった。

まあ、他のメーカーもそうだが、ヘッドライトのレンズは大きくカウル全体の1部となっていた。

Ninja H2もLEDなのか必要最小限の大きさだが、志向がだいぶ異なる。今後流れがどうなるか気になるところ。

ところで、日本の量産車の中で一番早い時期に採用されたカウルはこのZ1R(1978年)あたりだろうか。

Z1Rは輸出モデルだったが、国内モデルの1981年CB750FボルドールⅡにはオプションでカウルが用意され、納車前に取り付ける必要があった。

いわゆるレーサーレプリカ元祖のガンマだが、スクリーンがやけに立っているものの他社のツーリング向けフレームマウント大型カウルやハンドルマウントミニカウルとは大きく異なる。

それまでは汎用やそれに近いヘッドライトを用いていたのでカウルのスタイリングに制約があったが、このあたり(1985年GPZ1000RX)からカウルに対してフラッシュサーフェイスが可能になった。

しかし、ヘッドライトレンズを専用設計にできたのは、生産台数が多いスクーターなどのほうが先であった。これは1981年発売のスカッシュ。ロードパルやパッソルも小さい角型レンズだったが複数モデルに使い回していたと思う。
現在のヘッドライトはクルマもバイクもポリカーボネイトなどの樹脂で、全体のデザインの一部になっているのは当たり前で、その変遷の過程には発光メカニズムそのものの変化(白熱電球→シールドビーム→ハロゲン→HID→LED)もあったわけで、こうして振り返ってみるとこの30年余りの変化は大きい。
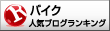 只今5位になっています。クリック宜しくお願いします。
只今5位になっています。クリック宜しくお願いします。