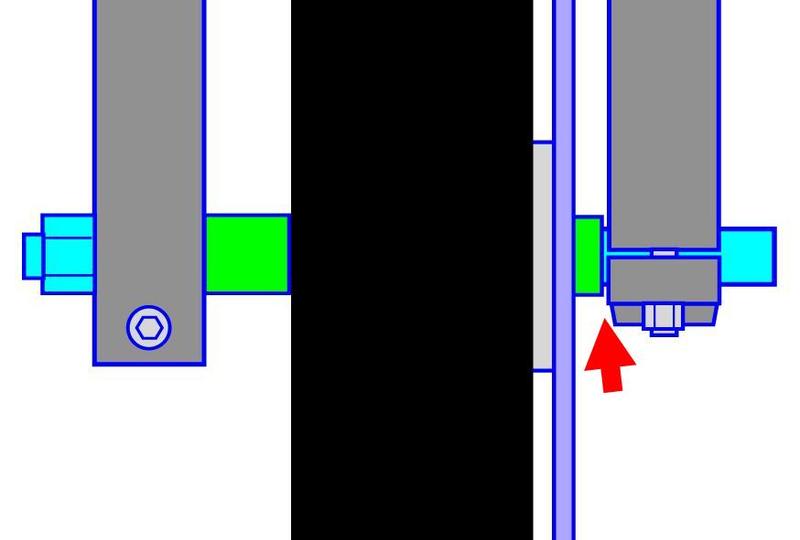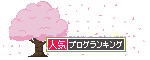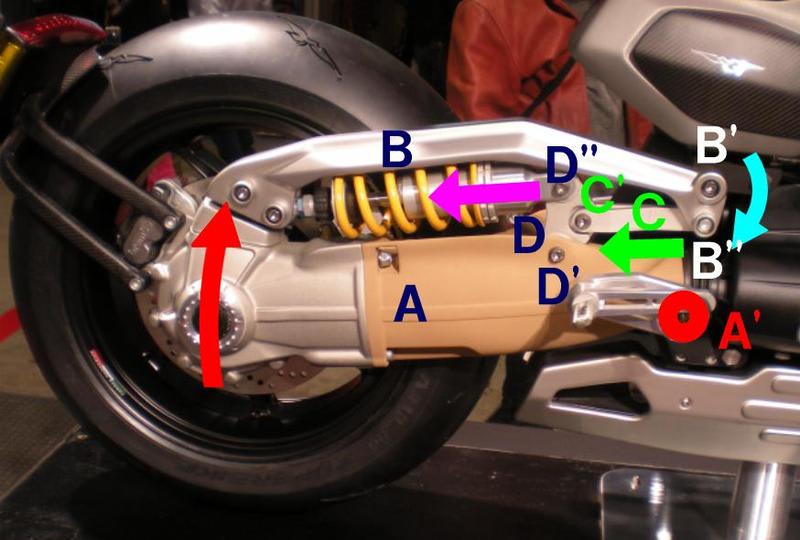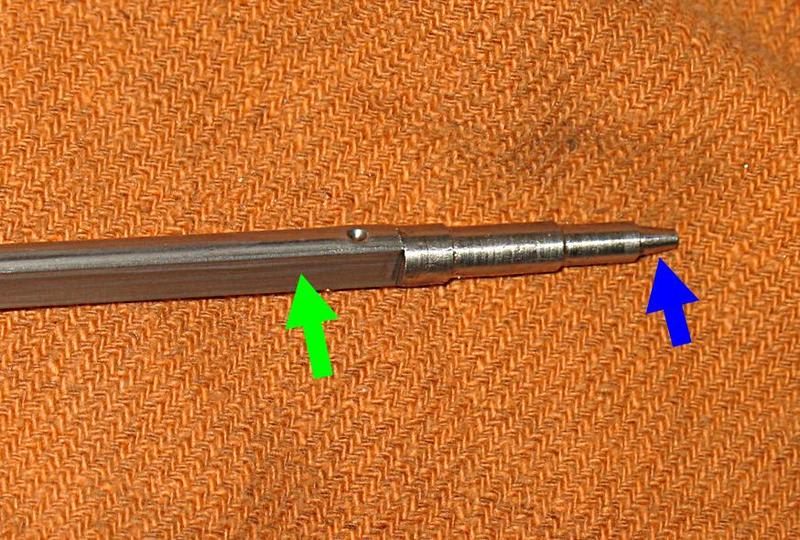アクスルシャフトのディスタンスカラーに関してご質問をいただきましたが、文章では中々難しいので図解を試みます。
フロントフォークとタイヤの関係は、タイヤがフォークの間の中心にあり、タイヤとフォークの中心線は平行になっているのが望ましい。
 スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。
スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。
ご質問は矢印の部分の隙間に関して。
組みなおしたら以前と変わったしまったということです。
アクスルシャフトの形状がこのようになっていると、タイヤの位置は赤いカラーの長さで決められてしまいます。
シャフトの形状が分かりやすいようにもう一つ。
こういう形状のシャフトではカラーの長さでフォークの幅が決められてしまい、高い精度が要求されることになります。
フロントサスペンションの動きを重視するなら、左右のフォークが平行であるのが望ましく、それにはA=B でなければなりません。
しかし実際にBの距離を測定するのは困難なので、できる作業方法としたらアクスルナットをまず締め付けて、ナットの反対のフォークのクランプを緩く仮締めして、フォークを大きく上下に動かしてからクランプを本締めします。
クランプを締め付ける前は、フォークの下端部が意外に動くことを確認してみてください。
正確に作業を行うには、左右のフォークの長さが同じであることを確認しフェンダーがある車両は外すことが望ましい。かなり前のことですが、Fタイヤが偏磨耗するトラブルを追求したら、タイヤとフォークが平行ではなく、その原因はFフェンダーの変形でした。
 スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。
スミマセン2位に落ちてしまいました応援クリック よろしくお願いします。