宇治川にカワウが増えてきました。留鳥ですが冬になると数が多くなるようです。
翼を広げて休憩しているカワウの姿をよく見ます。カモなど他の水鳥は脂分を羽にこすりつけて防水処理しますが、ウの仲間は脂分の分泌が十分ではないので、水に濡れた後はよく乾燥させないと溺れるからだそうです。水鳥としては決定的な弱点ですね。
ウはことわざや慣用句にもよく登場します。たとえば、よく理解しないまま納得することを「鵜呑み」と言いますし、逆に、納得いくまでよく調べることを「鵜の眼、鷹の眼」と言います。
翼を広げて乾かすカワウ
最近知ったことですが、私たちが風邪の予防として喉を洗う「うがい」は、鵜飼に由来するそうです。捕えた魚を飲み込まずに吐き出す様子にたとえて名づけたのでしょう。
漢字表記は「嗽」ですが、1444年(文安元年)に成立した国語辞典「下学集」には「鵜飼(うがい)嗽(くちすすぎ)也」と書いてあるそうです。「うがい」という言葉ができるまでは、「くちすすぎ」と表現していたわけですね。
しかし、語源の説はどこまでいっても推測に過ぎず、古書に記されているとしても、それが正しいかどうかは立証できません。私はこの手の話はいつもは眉に唾をつけて聞いていますが、この「うがい」は他に考えようがないので90%の確率で信用します。
宇治川には鵜飼もあることですし…。










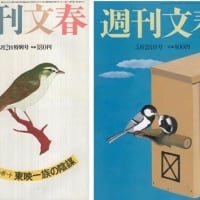
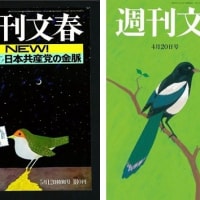













「うがい」の語源が「鵜飼」であるらしいのはなるほどと思いました、私も信じます。
ところで私はつい先日新潮文庫の「井上ひさしの日本語相談」を読んだのですが、そこで日本語の濁点についての考察があったので以降濁点についていろいろ考えるようになりました。
まずは「鵜飼」は私は「うかい」と言っています。
鵜飼をしている地元では「うかい」か「うがい」のどちらなのかなとそもそも疑問でしたが、fagusさんがこのような記事を上げるのだから「うがい」が一般的なのかなと思いました。
また私はいつも「うかい」と言っているので喉を水ですすぐ行為と鵜飼がまったく結びつかなかったのかもしれないです(元々私は鈍いですが)。
鳥の名前でも「カラ」類といい「シジュウカラ科」というのにヒガラ、ヤマガラ、コガラ、ハシブトガラとシジュウカラ以外はみんな濁点になっていますよね。
「ヒタキ科」なんてキビタキを筆頭にすべて濁点ですし。
日本語は不思議な言語だなと思います。
もしこれが英語なら"bet"と"bed"や"dock"と"dog"ではまったく意味が違うから。
まあ日本語は文字が基本で英語は音が基本だからというような説明がその本でもなされていたのですが、それにしても日本語を学ぶ外国人は「カラ」と「ガラ」が同じであることに最初は気づきにくいかもしれないですね。
なんて長くなってすいません、思ったことを一気に書きました(笑)。
繰り返し、うがいの語源は納得しました。
ただ、昔の人たちは「うがい」と発音していたのではないでしょうか。具体的には思いつきませんが、私の祖父や祖母が使う言葉は濁点が多かったように記憶しています。
私も言葉が仕事なので濁点の考察には興味がありますが、確かに何が濁音で何が清音かよく分からないですね。
外国人にも分からないでしょうね。
井上ひさしの日本語論は私も以前本を読んだことがあって、大変面白かったです。