京都大学で「木」をテーマにした公開講座があったので聴講してきました。今回は宇治キャンパスではなく、京都市内の本校。伊東隆夫名誉教授による「木と文化財」という講座です。
この先生は先日ご紹介した平城京の遺跡や古寺に使われた木材を鑑定した人で、日本だけでなく中国の文化財も調査されています。私が特に興味を持ったのは船の木材。
ジンギスカンは1274年と1281年の2回、日本を攻めました。この元寇に使われた船が中国に遺っていて、先生がその木材を鑑定されたそうです。
材として多かったのは、マツ、ニレ、クスノキ。マツとニレは属名までしか鑑定できていません。クスノキは、『日本書記』でもスサノオノミコトが船に使うように指示しており、日中で共通しています。このほか、水に強いチーク材も使われていました。

(丹後郷土歴史博物館に展示してある和船の模型)
びっくりしたのは船の数。最初(文永の役)は900隻(兵士4万人)でしたが、2回目(弘安の役)は4,400隻(兵士14万人)もの船が襲来。このうち、いわゆる神風によって3,000隻(兵士10万人)が海に沈んだといいます。大小さまざまな船があり、最も大きな船は長さ40m。
今年の夏に帰省した際、丹後郷土歴史博物館を訪れましたが、そこに和船の模型が展示してありました。いわゆる千石船で、実際の長さは約28m。
日本の船にもさまざまな木が使われていますが、竜骨にはカシやケヤキ、帆柱にはヒノキ、船体にはスギというのが一般的なようです。
公開講座では、船のほかいろいろな木の文化財について勉強できました。有名大学の立派なホールで、名誉教授の講義が無料で聴ける…。公開講座は「貧乏の木好き」にはありがたい制度です。
この先生は先日ご紹介した平城京の遺跡や古寺に使われた木材を鑑定した人で、日本だけでなく中国の文化財も調査されています。私が特に興味を持ったのは船の木材。
ジンギスカンは1274年と1281年の2回、日本を攻めました。この元寇に使われた船が中国に遺っていて、先生がその木材を鑑定されたそうです。
材として多かったのは、マツ、ニレ、クスノキ。マツとニレは属名までしか鑑定できていません。クスノキは、『日本書記』でもスサノオノミコトが船に使うように指示しており、日中で共通しています。このほか、水に強いチーク材も使われていました。

(丹後郷土歴史博物館に展示してある和船の模型)
びっくりしたのは船の数。最初(文永の役)は900隻(兵士4万人)でしたが、2回目(弘安の役)は4,400隻(兵士14万人)もの船が襲来。このうち、いわゆる神風によって3,000隻(兵士10万人)が海に沈んだといいます。大小さまざまな船があり、最も大きな船は長さ40m。
今年の夏に帰省した際、丹後郷土歴史博物館を訪れましたが、そこに和船の模型が展示してありました。いわゆる千石船で、実際の長さは約28m。
日本の船にもさまざまな木が使われていますが、竜骨にはカシやケヤキ、帆柱にはヒノキ、船体にはスギというのが一般的なようです。
公開講座では、船のほかいろいろな木の文化財について勉強できました。有名大学の立派なホールで、名誉教授の講義が無料で聴ける…。公開講座は「貧乏の木好き」にはありがたい制度です。










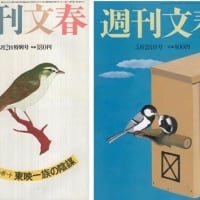
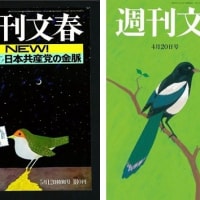













この記事を読んで、昔は、大量の樹木がいかにしてなくなったのかを
なんとなく想像できました。
しかも、昔はチェーンソーなんてなかったので、それを人力で切るのも
並大抵のことじゃないですよね。
ましてや木が太かったわけでしょうし・・・
想像を絶する世界ですね。
それから読んでいて映画「ベン・ハー」をなんとなく思い出しもしました。
おっしゃるように、ものすごい量の木材だったでしょうね。船を造る人的エネルギーも想像を絶します。