小学校の裏に桑畑があって、休み時間によく幼友達と桑の実を食べに侵入しました。ある時、先生に見つかって、「お前ら、また桑の実を食べただろう?」と問い詰められ、私は否認して放免されましたが、桑の実の汁で口の周りが紫色になっていた幼友達は、「嘘をつけ!」と張り倒されました。大人になってから、その思い出話をしては笑ったものです。

お盆の帰省で泊まったミニホテルの樹木園にマグワが植えてあったので、懐かしくて写真に収めました。ヤマグワは近くの山や河原で繁茂していますが、マグワはほとんど目にしません。昔はカイコの餌を確保するためにあちこちに植えられていましたが、今では信州あたりに行かないと見られないでしょう。マグワは中国からの移入種、ヤマグワは日本でも自生します。
さて、今年の夏は雷が多かったですが、昔の人は雷が鳴ると「くわばら、くわばら」と呪文を唱えました。その「くわばら」が桑原だと知ったのは、つい最近。木の本を読んでいたら、面白いことが書いてありました。

(クワ科の樹の葉は不定形の切れ込みがあるのが特徴)
菅原道真が藤原氏の策略で福岡に左遷されたのは有名な話。道真の死後、京都には異変が続き、御所も落雷を受けて多くの死傷者が出ました。祟りと恐れた朝廷は、道真の名誉を回復したのですが、この落雷事件以来、雷神=道真の怨霊と結び付けられました。道真が祀られている北野天満宮も、もともとは火雷天神が祀られていた場所だったそうです。
その道真の領地が丹波にあり、養蚕業が盛んなために桑の木が多く、桑原という地名だったそうです。そこで、雷が鳴ると、「ここはあなたの領地の桑原ですから、雷を落とさないでください」という意味で、「桑原、桑原」と唱えるようになったと言うのです。
雷だけでなく、何か恐ろしいことが起きそうなとき、あるいは誰かの逆鱗に触れたとき、昔の人は「くわばら、くわばら」と唱えて難を逃れました。桑の木のパワーはすごいのです。

お盆の帰省で泊まったミニホテルの樹木園にマグワが植えてあったので、懐かしくて写真に収めました。ヤマグワは近くの山や河原で繁茂していますが、マグワはほとんど目にしません。昔はカイコの餌を確保するためにあちこちに植えられていましたが、今では信州あたりに行かないと見られないでしょう。マグワは中国からの移入種、ヤマグワは日本でも自生します。
さて、今年の夏は雷が多かったですが、昔の人は雷が鳴ると「くわばら、くわばら」と呪文を唱えました。その「くわばら」が桑原だと知ったのは、つい最近。木の本を読んでいたら、面白いことが書いてありました。

(クワ科の樹の葉は不定形の切れ込みがあるのが特徴)
菅原道真が藤原氏の策略で福岡に左遷されたのは有名な話。道真の死後、京都には異変が続き、御所も落雷を受けて多くの死傷者が出ました。祟りと恐れた朝廷は、道真の名誉を回復したのですが、この落雷事件以来、雷神=道真の怨霊と結び付けられました。道真が祀られている北野天満宮も、もともとは火雷天神が祀られていた場所だったそうです。
その道真の領地が丹波にあり、養蚕業が盛んなために桑の木が多く、桑原という地名だったそうです。そこで、雷が鳴ると、「ここはあなたの領地の桑原ですから、雷を落とさないでください」という意味で、「桑原、桑原」と唱えるようになったと言うのです。
雷だけでなく、何か恐ろしいことが起きそうなとき、あるいは誰かの逆鱗に触れたとき、昔の人は「くわばら、くわばら」と唱えて難を逃れました。桑の木のパワーはすごいのです。












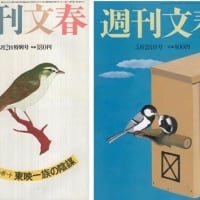
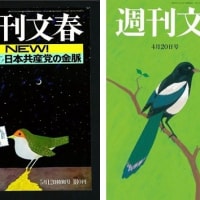













祇園祭のちまきの「蘇民将来子孫也」と同じような発想ですね。
ちなみに、
八坂神社の祭神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)が旅の途中でもてなしてくれた蘇民将来に対し、お礼として子孫に疫病を免れさせると約束し、その印として茅(ち)の輪を腰に付けさせたのが起こりといわれ、それからちまきに「蘇民将来子孫也」と書いて疫病を逃れようとしたそうです。もともとはちまきではなくて、茅の輪がちまきと混同されて変形したそうです。
さきほど「茅」を漢和辞典で調べたら「かや」「ちがや」とありました。これは草本なので、私の守備範囲ではないのですが、私の故郷は「加悦」と書いて「かや」と読みます。樹にもカヤがあるのですが、以前から「草のカヤが地名のルーツではないか」と思っていました。
京都育ちのscopsさんらしい情報、ありがとうございました。
ヤマグワは庭にもあって、毎年実がなり、
カラス、ヒヨドリ、スズメが食べに来ます。
雨が降ると幹の色が赤茶色になってきれいです!
小さい頃食べたマグワの実はもっと甘くて、美味しかったと思うのですが・・・。
図鑑を見ると、マグワの実はジャムにすると書いてあるので、やっぱりマグワの方が美味しいんでしょうね。
guitarbirdさんは庭のヤマグワの実は食べないんですか?