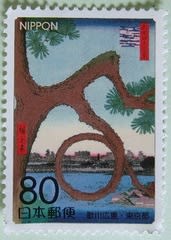仕事で大阪府池田市を取材しました。ここは「池田の猪買い」「池田の牛ほめ」など上方落語の舞台になっていることから、「落語の町」として町興しするべく市立の「落語みゅーじあむ」を開設しています。また、古くから「炭の町」として知られ、良質な池田炭は茶席の必需品です。
そして、日清食品発祥の地でもあり、住宅地の真ん中に「インスタントラーメン発明記念館」が建ち、駅前には「インスタントラーメンの町」という標識もあります。
さらにもう一つの顔があって、植木の四大産地のひとつ。400年以上の歴史があり、江戸時代中期には盆栽の生産も始まったそうで、「植木と盆栽の町」でもあります。市内には盆栽専門の園芸業者がいくつかあり、お店やネットで販売しています。

(仕事の途中に立ち寄った盆栽のお店)
ある店で商品を見てビックリ。10cm程度のエノキやエゴノキが1,500円! 挿し木して数年の苗木がこんな値段で売れるんですね~。形のいいクロマツには100万円近い値段がついています。この世界も奥が深いようで、玩物喪志に陥る人も多いんでしょうね~、同情します(笑)。

(形のいいクロマツは10万円単位)
私は樹木は大好きですが、盆栽には興味がありません。偏見かも知れませんが、樹木を人工的に矮小化したり、人間の力で自然を弄ぶことに抵抗があるからです。
でも、町興しを仕掛けている3セクの店で、盆栽にちなんだサイダー「ぼんサイダー」を見つけて即買いしました(笑)。

ラベルには、盆栽のクロマツを背景に何故かレトロな女性が印刷され、その横にキャッチコピーが書いてあります。
甘さスッキリ盆栽ダー
植木のまちだよ盆栽ダー
こころときめく盆栽ダー
わたしのことは聞かないで…
最後の思わせぶりな1行は意味不明。盆栽は好きになれませんが、こういう遊びゴコロは大好きです。なお、「ぼんサイダー」の味は三ツ矢サイダーとほぼ同じでした。
そして、日清食品発祥の地でもあり、住宅地の真ん中に「インスタントラーメン発明記念館」が建ち、駅前には「インスタントラーメンの町」という標識もあります。
さらにもう一つの顔があって、植木の四大産地のひとつ。400年以上の歴史があり、江戸時代中期には盆栽の生産も始まったそうで、「植木と盆栽の町」でもあります。市内には盆栽専門の園芸業者がいくつかあり、お店やネットで販売しています。

(仕事の途中に立ち寄った盆栽のお店)
ある店で商品を見てビックリ。10cm程度のエノキやエゴノキが1,500円! 挿し木して数年の苗木がこんな値段で売れるんですね~。形のいいクロマツには100万円近い値段がついています。この世界も奥が深いようで、玩物喪志に陥る人も多いんでしょうね~、同情します(笑)。

(形のいいクロマツは10万円単位)
私は樹木は大好きですが、盆栽には興味がありません。偏見かも知れませんが、樹木を人工的に矮小化したり、人間の力で自然を弄ぶことに抵抗があるからです。
でも、町興しを仕掛けている3セクの店で、盆栽にちなんだサイダー「ぼんサイダー」を見つけて即買いしました(笑)。

ラベルには、盆栽のクロマツを背景に何故かレトロな女性が印刷され、その横にキャッチコピーが書いてあります。
甘さスッキリ盆栽ダー
植木のまちだよ盆栽ダー
こころときめく盆栽ダー
わたしのことは聞かないで…
最後の思わせぶりな1行は意味不明。盆栽は好きになれませんが、こういう遊びゴコロは大好きです。なお、「ぼんサイダー」の味は三ツ矢サイダーとほぼ同じでした。