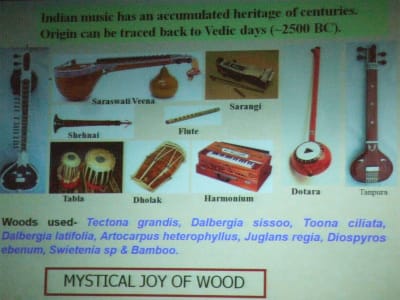このオリーブは平和のシンボルとして人間社会に貢献してくれています。よく見かけるのは国連の旗。

北極から見た地球をオリーブの枝が囲んでいるというデザイン。平和を守るのが国連の使命という意味でしょう。
国連の旗には規則があって、他の旗を並べる場合、これより大きいものを掲げたり、高く掲揚してはいけないそうです。
オリーブはアメリカの硬貨にも登場します。下は10セント(1ダイム)硬貨の裏面。

左のオリーブは「平和」、真ん中の松明は「自由」、右のオーク(ナラ)は「勝利」を意味するそうです。10セント硬貨のデザインは何度か変更されていますが、オリーブはモチーフとして代々受け継がれています。さらに、25セント硬貨や50セント硬貨の裏にもオリーブがデザインされています。
アメリカは「平和」が大好きなようで、国章にもオリーブを使っています。

国鳥のハクトウワシが文字通り“鷲づかみ”にしているのは、左がオリーブ、右が矢。オリーブの葉と矢が13あるのは、最初に独立した13州に由来するそうです。
オリーブが「平和」、矢が「戦争」を意味し、ハクトウワシがオリーブの方を向いているのは「平和」を優先するためとのこと。
平和を求めるけれども戦争も辞さないという、いかにもアメリカらしいデザインです。